|
(2)教材
教材は、事務局が作成した資料よび副読本を用いた。また、資料を保存するためのドキュメントファイルとビニール袋が配布された。なお、WGでの提案により考えた内容を整理しやすいようにワークシートが用意された(写真III−1−3、表III−1−2)。
また、11月からは、学習意欲への刺激を目的として、隙間時間を利用してのコラムを提供することとし、チューター持ち回りによる交通と環境に関するコラムシート「Passe−temps」(全9号)を発行し、授業時間中の合間に話題提供を行った(表III−1−3)。
写真III−1−3 教材(左から副読本、資料、ワークシート、コラムシート)
表III−1−2 教材一覧
| (拡大画面:117KB) |
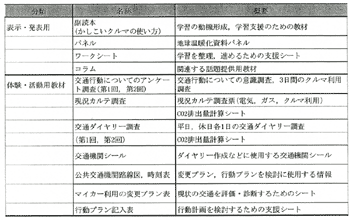 |
表III−1−3 コラムシート「Passe−temps」の話題提供内容
| (拡大画面:114KB) |
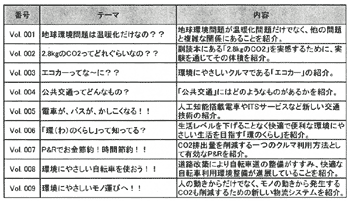 |
(3)その他の取り組み
経過報告や学校側からの要望などの速報性を確保するため、インターネットサイト(非公式)を公開し、チューターレポートや交通・環境コラムシートのほかWG議事録のダウンロードサービスを行った。
| (拡大画面:95KB) |
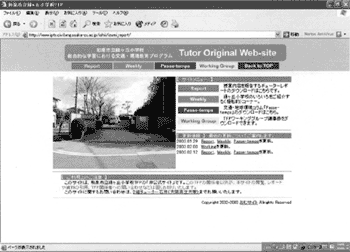 |
写真III−1−4 インターネットサイト
(3)本年度のプログラムの評価
(1)総合的な学習の時間におけるプログラム実践の評価
本年度のプログラムを、当初に掲げた目標とねらいに対して達成されたかどうかという視点で評価する。表III−1−4はカリキュラムに着目して、表III−1−5はツールに着目して評価したものである。
評価の結果を概括的にまとめると、次のとおりである。
本年度のプログラムの評価の要約
◆プログラムの実施によって期待した学習内容に対する成果は概ね達成された
・テーマは新鮮な興味を持って受け入れられた。
・用意したプロセスは全て実行された。
・カリキュラムのねらいは、概ね達成された。
◆しかし、進め方や教材などについては工夫する必要があることがわかった
・全体的に児童及び保護者の負担が大きく、ワークシートや調査、作業方法、5年生の教科との整合性など、ツールに工夫したほうがよいことがわかった。
・一つのテーマとしては期間が長すぎること、毎回の授業で子どもたちが興味を持って取り組めるような工夫が必要であることなど、プログラムの薦め方についての再検討が必要であることがわかった。
|