|
ですから、ITのツール、いろいろございますが、目的と手段とをうまく組み合わせて、何でもかんでもITで装備すればいいということはなく、必要なものに対して必要なものを配置するというのが一番ポイントじゃないかと思われます。
では、具体的にIT技術がどんなことが出来るのかということをお話していきたいと思います。
これ、「イングリッシュタウンのウェブ授業」というんですが、いわゆる双方向のシステムです。ウェブを使って、まあNOVAなんかで皆さんお馴染みだと思いますが、いわゆるテレビ電話みたいな形ですね。それで実際に授業をすることが可能になっています。それから「大原の合格ウェブ税理士講座」の画面イメージなんですが、実際にこれで授業を受ける形になっています。だから、先生が目の前にいて見えると。まさにリアルタイムで先生の授業を聞くことができます。これの良いところは必ず録画してありますので、いつでもどこでも誰でも、もう一度繰り返して聞くことができることです。だから、最近、いわゆる通信教育というのはこのような形に全部変わってきています。(図8)
イングリッシュタウンのウェブ授業
大原合格ウェブ税理士講座
画面イメージ
図8 双方向システムによる通信教育
こういったものを、観光に応用したら、どういうことができるのか。今まで対面販売で、旅行代理店でいろんなご相談をしますよね、それが画面の向こうにいる方と相談するのが可能になってくるんですね。これは他の会社がやっていることと考えないでほしいんです。観光業にすべて応用可能なんですね。で、その時にどういうふうにしたらいいんだろうかということを一番早くやった所が、今、観光業界で新しいことをやってるところになってくるわけです。例えば、今、対面販売の相談の方が画面の向こうにいて、「どんなご希望ですか」とお話しながらあなたのプランを作っていく。ある意味ではインターネットだけを使ってるよりは、もっと温かみをホスピタリティを感じさせる、そんな仕組みになるかもしれません。
もうひとつ、「空想生活」というウェブページがございます。これは究極のオリジナル性をもって、カスタマイズされたものでございます。なぜご紹介するかというと、私は、これが旅行において成り立つんじゃないかと思ってるんですね。これは消費者が、自分の欲しい商品を、こういうのを作ってよと頼むんですよ。そうすると、メーカーが商品提案プロセスでデザインを検討して、実際に作ってみて、プロトタイプを作って、どうですかと消費者に問いかけて、消費者がじゃあ実際に価格やデザインに対して、こんなふうに変えたいと思いますけれど、何人か好きな方集めましょうとか。そういったことを全部ウェブ上でやっている、多品種少量で自分の欲しいものを作ってくれるという、究極のオーダーメイドなんです。
これを例えば旅行の中でやってみたらどうでしょう。先程言ったように、双方向の画面の中で、「私、今度九州でも全然誰もいないような、人里離れた島に行きたいんだけど、それにちょっとプランを作って欲しいんだけど」と、誰かが言って、その相手の方が「じゃあこんなの、どうですか」といろいろやり取りしながら作っていく。それに対して「こういうもの、持ってるんだけど」、「もう2〜3人集まるとこの価格はこのぐらいになるから、やれるんじゃないかしら」。そんな双方向のやり取りをしながら、自分が好きなカスタムメイドの旅行を自分でアレンジすることができる。だから、価格に対しても安ければいいとかそういうこと言ってこない。そんな顧客が増えてくるんじゃないかと思われるわけです。実際に、こういう試作品に関しましては、もうすでに動いております。(図9)これがサービスにおいて出来ないということは、決してないわけです。だから、今までのサービスというような既成概念にとらわれることなく、新たなやり方にチャレンジすることも、観光業界にとって一番大切なんじゃないかと思われるわけです。
| (拡大画面:40KB) |
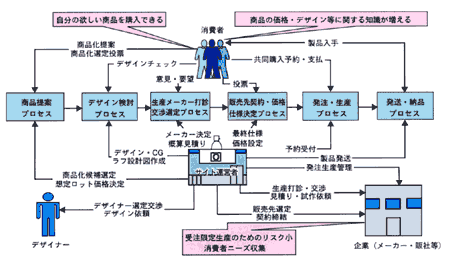 |
図9 「空想生活」の消費者参加型商品開発プロセス
「Q州マイ−コンシェルジェ」
図10 Q州 マイ−コンシェルジェ トップページ
さて、ここで簡単に「Q州マイ・コンシェルジェ」という、私共のやっているサイトのご紹介をさせていただきたいと思います。(図10)
そもそもは地方自治体などは、非常に充実した観光情報を出していらっしゃいます。ただ、そこに出ているのは市町村情報、観光情報、宿泊情報、交通情報、イベント情報で、データベース型の検索情報が中心なわけです。ところが、観光の方のお話を聞いてみたりとか、自分が観光客になって考えてみると、どちらかというと地元の口コミ情報とかそういったものの方が、旅行に出た時は欲しい情報であるわけです。地元の口コミ情報というのは誰が出しているかというのが非常に大切なもので、得体の知れない人が出してくるんじゃなくて、やっぱり顔の見える地元の方が出して欲しいなというのが観光客の偽らざる心境だと思います。
そこで、デジタル観光情報に対しての補完関係になるアナログ観光情報としてのコンシェルジェシステムというのを、九州では平成12年12月12日にオープンしました。これは消費者の観光ニーズにあったコンシェルジェというものを組織化したものです。コンシェルジェというのは、ホテルなんかで、痒い所に手の届くサービスをしてくれる方々、案内人という形なんですが、この観光情報におきましては、現地にいながら地元の口コミ情報だとか、あなたの欲しがっている情報を発信してくれる方々でございます。ですから、コンシェルジェは地元のボランティアの方々です。この方々がコンテンツを作成して情報を提供して下さいます。
もうひとつ、双方向コミュニケーションというのがあります。先程からずっと言っておりますが、そこではコミュニケーションというものがポイントになってまいります。インターネットを介して一番大切なのは時空間を越えたコミュニケーションです。ですから、東京にいる方が、九州を訪ねたいと思った時に、具体的に何人で、例えば「母と一緒に行くんです。ホテルはどこそこに泊まります。近くでおいしいもの食べれる所教えて」というような時に、教えていただけるようなそんなサイトを考えたわけです。
これを作りました時にも、インターネットのユーザーの方に皆さん、観光に行く時にインターネットでどんな情報が必要なんですかと、それからどういう情報だったら喜びますかと調査いたしました。で、そこから出てきた内容を合わせて、こういうふうな形のサイト作ったわけです。やっぱり肝心なのは、こういうのを出したいから作るというのではなくて、お客様が何を望んでいるのか、具体的にどんな情報を欲しがっているのかを、きちんとマーケティングをするというのが必要だなとつくづく思いました。
会場風景
今、このコンシェルジェシステムについて、どうなっているのかということを簡単にご紹介させていただきたいと思います。
これは我々が事務局をやっているのですが、九州、大阪、京都、神戸のコンシェルジェの方が集まりまして、この活動をずっと続けていきたいと、ボランティアで続けていくためにはどうしたらいいのかというのに、ご相談にのりながら出来上がりましたのがNPO法人「マイタウン・コンシェルジェ協議会」で、今年の1月に法人格を取得いたしました。この法人は日本人・外国人の市民及び地域ボランティアが地域情報を国内外に発信する案内人、すなわちコンシェルジェを務める活動の支援を行う。コンシェルジェ組織の運営・支援、コンシェルジェの教育や広報を行うという形で国際交流やまちづくりに寄与するような形のNPOでございます。コンシェルジェ活動の支援事業、広報事業、教育事業で実際はまだNPOとしてはできたばかりで、そんなに活動はしていないんですが、今後、今までボランティアになった方々を横をつないで、NPOとして活動が出来るように支援していきたいと思っております。
さて、今までITからみて、どんなふうに観光というのが変えられるのか、IT活用の視点で観光業というのが、これからどんなふうに変わっていくのかということを、お話してきたわけですが、観光業界というのは、私ども、ITの活用からみていますと、やはり、まだ遅れているんじゃないかと思われるんですね。使える部分と使えない部分がたくさんありますので、何もかもITでやればいいというものではございません。観光業界の場合は、とりわけ、ホスピタリティとか、人の心と心を結ぶところがとても大切です。ITで解決できないことはたくさんございます。ただ、ある意味での効率化だとか、ある意味での時空間を越えたコミュニケーションをとるというところにおいては、IT活用をもっと導入してもいいのではないかなと思われるところがございます。
例えば製造業の業界で行われているIT活用が、流通業の業界まで普及してくるのに2〜3年かかってくるわけです。その中で、観光業界というのは、結構、流通業界に似てるなという感じがいたしまして、やはり、人が中心で、わりと装置産業であるということがございますので、もうちょっと、旅館の経営だとか、そういったものの中でITの活用をやることによって、もっと効率的な部分ができるという部分と、それからお客様をどうつなぎとめていくか、どういうふうにお客様とコミュニケーションをとっていくかというところに、IT活用のひとつの可能性があるんじゃないかと思います。
私どものご紹介しました「Q州マイ・コンシェルジェ」というのはITといいながらも、これは完全にツールです。人と人をどうやって結ぶか。そこにございますのは、人はもしかすると口コミ情報のような、本当は内緒の情報をそっと欲しいのではないかと、そういうふうに思ったからです。でも、それを可能にするのはインターネットでした。結局、インターネットがなければ、こういう情報をこういう形で発信することも受信することもできないわけですね。逆にこういう時代だからこそできるサイトだと思いますし、じゃあ、これで商売になるかというと、なかなか、それは難しいです。ですから、最終的にはNPOという形を考えたわけですが、ただPPP(public−private−partnership)でやるというやり方、ああいうやり方をとった時には、いろんな方法論もあるかもしれないと思っております。
で、一番ポイントになるのは、単体でやると非常に投資がかかり、なかなかその投資効果が得られないというところがございますけど、ある程度やりたいところがまとまった時に、非常に大きいものが出てくるわけです。ですから、同じような問題を抱えている所がまとまってやってしまうと、それをASP(Active Server Pages)として提供していくというのがIT活用の中では一番効率がいいんじゃないかと思われます。
電子自治体についていろいろ調べた結果なんですが、今、地方自治体が財政難の中で、いろんなIT活用をやらなくちゃいけないと考えている。で、その時にどのような形をやろうかと思っているかというと、一番最初にやろうとしているのは、やはりASPなんですね。アウトソーシングかASPだと。要するに自前でやるのはやめよう、自前でやるとお金がかかりすぎると。だから、皆で集まってコストが安くなるような仕組みを考えようというのが、今、地方自治体の流れになっています。それと企業が一緒になってやった時に、新しいITをいかに安く上手く使っていくかというのが可能になるのではないかと思います。
結論としまして、まず第一に、ITというものは全てのことを解決してくれる魔法の小箱ではないということなんですね。だから、ITが全てではないとわかったうえで、どこの部分でITを使って効率化させるか、どこの部分で人を使ってホスピタリィ的な部分で良くするかというのを、分けていかなければならないという部分がひとつあると思います。
もうひとつは世代別のニーズというものが、大分変わってきているということなんです。要するに、代理店に行って、何もかもお任せでやっていただきたいと思う方は、大体50才台以上の方だと思うんですね。まあ40才台の半ばぐらいからそうかもしれません。だけど、今の10、20、30才台はインターネット当たり前の世界で育っています。この方々があと20年後になった時にどうなるか、旅行業というのも観光業界も変わってると思うんです。若い方はいかに安く、いかに気持ちよくサービスを手に入れられるかという形で考えますんで、やはりそれに対抗するものも、今から考えておかないと、20〜30年経ってからでは、遅すぎるということを肌で実感するような、今日この頃だと思っております。
|