|
■長崎県における海上旅客輸送のバリアフリー化促進調査
三点目に、昨年、(財)九州運輸振興センターが主体で行った「長崎県における海上旅客輸送のバリアフリー化促進に関する調査」についてご説明します。この調査では、事業者や港湾管理者など提供者のアンケート調査と、利用者のアンケート調査を行っています。
まず提供者、ここでは海上輸送なので、長崎県で旅客船事業を行う全40事業者が対象となっていますが、そちらのアンケート結果をご紹介します。
最初に、バリアフリー対応船舶数(図7)ですが、例えば出入口の幅を見てみると、フェリーだと200トン以上、旅客船だと50トン以上の船の7〜8割が現状でも法律の基準をクリアしているのに対して、小型の船だと3〜4割ぐらいにとどまっている。通路幅に関しても同じような状況にあります。
■船舶のバリアフリー化の実態
・バリアフリー対応船舶数
図7 バリアフリー対応船舶数
また、出入口の段差や車椅子のスペースについては大型船であっても3割ほどしか対応が出来ておらず、さらに身障者用のトイレの設置についてはほぼゼロに近いという状況です。
このことから、船自体が非常にバリアフリー化が難しいということと、小型の船になるとさらにそれが大変であるということがわかります。
次に、ソフト面の方で事業者にバリアフリー化に関する教育・指導についてお伺いしたのですが、この段階では約7割の事業者がバリアフリーといった視点での指導をしてないという状況にあります。
■船舶のバリアフリー化の実態
・バリアフリー化に期待される効果
| (拡大画面:12KB) |
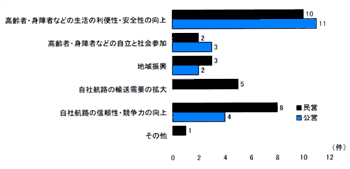 |
図8 バリアフリー化に期待される効果
バリアフリー化に対して期待される効果(図8)ですが、民営の事業者は高齢者・身障者などの生活の利便性・安全性の向上、これだけではなく、輸送需要の拡大や航路の信頼性・競争力の向上に非常に強い関心を持っています。一方、公営の方はこれらの項目にほとんど反応がない状況で、バリアフリー化の捉え方は公営と民営でかなり違うということがわかります。
新船導入時におけるバリアフリー化の課題についても、船舶構造に関する法規制との両立の困難さを公営、民間ともに挙げているのですが、コスト負担についての回答は、公営の方はほとんどゼロに近い状態で、経営的な感覚にかなり温度差があるとはっきり言えます。
■高齢者・身障者のニーズ
・船舶利用時の問題点(上位5位)
| (拡大画面:31KB) |
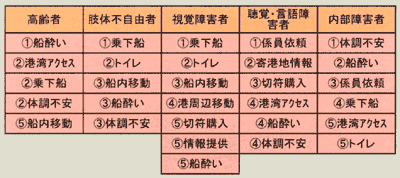 |
図9 船舶利用時の問題点(上位5位)
続いて、利用者のアンケート結果ですが、船舶利用時の問題点で上位5つを挙げているのですが(図9)、例えば高齢者全体でみると、船酔いや一般的なアクセスの問題を挙げているのに対し、肢体不自由の方や視覚障害の方は乗下船、トイレ、船内移動といった移動の不自由さに関心が強く、聴覚・言語障害の方は係員に頼みにくいとか、寄港地の情報がほしいとか、切符が買えないといったもの、また、内部障害の方は、体調、船酔いで、ひとくちにバリアフリーといってもニーズが全然違うので、先ほど申し上げたきめの細かさが各々必要になってくるというのが、これでわかると思います。
次に、バリアフリー化されれば外出が増えるかということですが、移動範囲が拡大する、離島から本土への外出頻度が増加する、といった回答が多くなっており、バリアフリー化によって外出行動が大きく変わってくる可能性があると言えます。
この調査のまとめですが、バリアフリー化の位置づけを考えると、まず行政からみれば、離島航路は道路に準じる基幹的なインフラで、生活に不可欠なものとして整備していく必要があるということがあります。
事業者側にしてみれば、法律による責務として当然推進するということ以外に、特に先ほど民間の事業者から回答があった需要拡大の部分を注目していく必要があり、特に離島の場合には住民は減少傾向で、住民自体の利用は促進するとはいえ限界があるので、やはり観光を中心として、島外から来てもらうということにかなり意識を払っていく必要があると思われます。
利用者ニーズヘの対応の考え方でも、利用者の視点に立ってやっていくこと、利用者ニーズにきめ細かく対応していくということ、これが重要です。
具体的に船で考えていく場合に、どうしたらいいかということですが、特に小型船のところで触れたように、船はバリアフリー化が重要であるにもかかわらず、技術的に非常に難しいわけで、利用者の身体障害者団体の方からも調査の中でお話があったのですが、船とか港全部をバリアフリー化するというのは理想ではあるけれども、ある一部の区切られた部分でもいいから優先度の高いもの、あるいは出来るものからやってほしい。例えば、車椅子の方、目の見えない方が船の隅から隅まで行けなくても、ちゃんと乗れる場所が確保され、あるいはトイレぐらいは一人で行けるというレベルまで行うなど、ターゲットを絞って進めるのが大事だろうということです。
そのためには、かなりバリアフリー化のレイアウト、施設の配置を考えてやっていく必要があるということと、特に小さな船舶、港湾施設の十分でないボーディングブリッジのないような小さな港では、どうしても乗下船時に人的な支援が必要で、この点もあわせて対応を強化していくことが大事だと思います。
■まちづくりと連携した交通のバリアフリー化に向けて
最後にまとめということで、お話ししたいと思います。
まず、バリアフリー化の意義ですが、行政からみれば、ノーマライゼーションの実現、福祉的な目的がひとつ目にあります。もうひとつは住民が活発に外出出来るようにしたり、域外から人に来てもらうことで交流人口を拡大し、地域の活性化を図るという視点を持っておく必要があると思います。
それから、事業者の方からみれば、需要の拡大という効果、具体的にはバリアフリー化することで高齢者や障害者の方が利用しやすいようにしていくというのは勿論ですが、そういう対応をすることで、信頼性の向上というかアピールする手段として、もっと積極的に打ち出していくということもあると思われます。
それから、まちづくり等との連携の必要性ですが、例えば交通事業者からみれば、法律範囲では旅客施設や車両等を改善すればよいことになりますが、利用者にとっては、家から目的地まで移動しやすいということが大事ですので、一連の経路を全体でみていく必要があり、当然まちづくりや都市計画はこの分野と連携し、シームレスなバリアフリー化を推進する必要があります。
それから、交通手段自体が貧弱な所であればモビリティの確保もしなければなりません。これは特に過疎バス等、規制緩和で自治体の役割、特に市町村の役割が重要になってきているわけですが、その部分とバリアフリーの連携が必要になってくる。あるいは、移動の制約の大きい方に関しては、別途スペシャルトランスポート的なものも必要になるということになります。
そしてもうひとつ、医療・福祉分野との連携ですが、これは例えば、コミュニティバスを走らせることで寝たきりの方が減り、医療・福祉の出費が減らせるということで、バリアフリー化、交通サービスの充実をやっている市町村もあり、そういった部分との連携も必要ということです。
いろいろな部分で跨ってくるということで、連携の必要性ということで次に書いていますが(図10)、公と民の連携、これはここに書いてあります。
また、広域連携、要するにドア・ツー・ドアの経路の中で考えていくということになると、生活圏、交流圏の中で自治体同士の地域間の連携も必要になってきます。
図10 各関係主体の連携の必要性
それから、事業者、行政だけではなく、利用者も参画を促していく。その中で、NPO等のセクターの連携、具体的には利用者ニーズの集約や評価、こういった部分で参画してもらう必要が出てくると思います。
こういった全体の調整というのは非常に難しいわけで、例えば市町村で誰かが全体を調整していくというとなかなか大変だと思うんですが、イギリスでは、アクセス・オフィサーといって、国で認定する資格をもった人が就く行政のポストがあり、全体の目配り、調整をやっています。ひとつには、そういうやり方がありうるかなと思います。
最後に費用負担の話ですが、現状だと基本的に施設整備については、国あるいは自治体で各々補助制度があり、その補助を受ける中で事業者がやるのがメインだと思います。
逆に運営の方は、身障者あるいは介助者の割引がありますが、これについては特に公的な負担というのは日本ではありません。
これをどの補填でやっていくかということですが、要するに事業者の経営戦略の一環としてやるのは当然あって然るべきですが、逆にそこで損をするような状況になると、他の利用者へ(運賃転嫁の形で)それを負担してもらうことも論点として出てくると思います。
ひとつは、事業者負担を原則とするもの、あるいは、バリアフリーという社会的な要請にもとづいて、もっと公的な負担を拡大するというような、いろいろな考え方があると思います。
例えばドイツですと、基本的には公共負担という考え方が非常に強く、少なくもハード面は公で作るというところが出ており、それを原則とするのもひとつの考え方だと思います。
逆にフランス等は、受益に応じて負担する、つまり、事業者の経営の範疇を越える部分は、国なり自治体が補助を出すけれども、事業者も一定の利益の部分は負担しなさいという考え方もあるかと思います。
あるいは、イギリスでは入札の要素を入れてきており、公共がサービスを買うという形で、民間が複数参入するという考え方もあると思います。
今後日本の場合には、その辺をしっかり議論する必要があると思います。
討議について
|
原田講師の講演後の討議では、参加者から活発な意見交換が行なわれました。ここでは、その一部を紹介します。
・日本は島国なので、たくさんの有人離島があるが、これは海がバリアになっている。
・(船舶のバリアフリー化は)航路の持続という面では採算を無視しては行えない部分であるが、武蔵野市のように、コミュニティバスが黒宇化を実現したという例もあり、やり方によっては需要拡大につながることもあり得る。そういうところを今後考えて、推進していくべきである。
・小型や中型のフェリーしか通らないような離島では特に高齢化率が高い。このような島が一番バリアフリー化を必要としているのではないか。(バリアフリー化対象施設の基準が)1日5千人(の利用)という話があるが、離島の人口はどんどん減っている。そういう意味では人手による介助が一番現実的かもしれない。
・介護タクシーの利用については介護保険の方で積極的に面倒をみるよう、国の方でしっかりとやってもらいたい。
・NPOやボランティアの活用も、奉仕の精神ばかりに期待しても限界があると思われるが、その場合の経費をある程度行政や受益者が負担するということも考えられるのではないか。
・交通バリアフリー法は交通事業者に対して最低限の基準を設け、それを超えるところや街づくりは自治体の責任でやることを明示したところに意味があるが、その「最低限」は変わってくるだろうし、「自治体の責任」は今後重くなると思われる。
・民間が経営を追求するなかで、そこで出来ない部分は自治体の役割となるが、国の規制緩和の基本設計の中では、自治体の役割までは、まだ姿が見えていない部分が多いものと思われる。
・具体的に離島航路で市町村、都道府県、国と航路事業者がどういう関係を作っていくかを、今までと違う形にしていく必要があり、そこはまだ、これから答を出していくところで、そこが大きな課題である。
|
|
|