|
収録した傾斜計データを、図104〜図105に示す。図より、計測可能範囲を超えているデータが多く存在していることがわかる。このため、収録した傾斜計データが、計測可能範囲である+5.00〜−5.00度の範囲に収束しているかについて計測点数を調査した。調査は測線ごとに実施した。結果を表38及び表39に示す。表より、x(1)については、ほとんどの測線で有効データ率が95%を超えている。しかし、y(1)及びx(2)については、半分以下であることがわかる。なお、傾斜計(2)のy軸に対する傾斜角度は、センサーが故障していたため−5.00度または5.00度を示し、測定していない。
傾斜計(1)のx軸に対する傾斜角度。
傾斜計(1)のy軸に対する傾斜角度
傾斜計(2)のx軸に対する傾斜角度
図104 傾斜計の角度 825測量。
傾斜計(1)のx軸に対する傾斜角度
傾斜計(1)のy軸に対する傾斜角度
傾斜計(2)のx軸に対する傾斜角度
図105 傾斜計の角度 8/26測量
表34. 測線ごとの傾斜計データの有効データ率。8/25測量
| (拡大画面:127KB) |
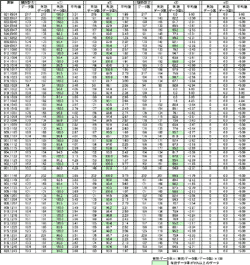 |
表35. 測線ごとの傾斜計データの有効データ率。8/26測量
| (拡大画面:128KB) |
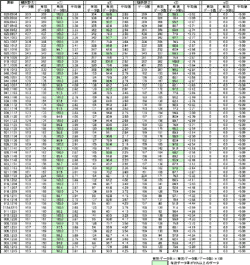 |
これに対し、y(1)及びx(2)データの有効データ率は全体の半分以下であるため、ほとんどの測線で有効データ率が95%を超えているx(1)を使用し、POS/MV動揺センサーで収録した動揺データとの比較し、傾斜計データの有効性について検討する。
x(1)はロールの向きと一致する。そこで、測線ごとにx(1)とPOS/MV動揺センサーのロールデータの平均値を求め比較した。比較結果を図106に示す。図より傾斜計データは、東西測線のときは変化せずほぼ一定の値を示している。これに対し、南北測線では2つの値の間を移動して示している。このうち、3度付近を示しているときの測線は南から北へ向かっており、4度前後を示しているときは測線が北から南へ向かっているときであった。一方ロールは、8月26日の東西測線のように傾斜計の変動とほぼ同期している場合もあるが、25日の終了近くの時刻部分のようにまったく同期していない場合もある。これより、船体の動きと測深機を接続してある支柱の動きが一致していない場合があることが考えらえる。そこで、傾斜計とロールデータの変動が一致しているときと一致していないときの水深図を作成し比較した。
比較した場所は、クロス測線で測量を実施し、かつ東西測線で、傾斜計とロールデータの変動が一致している8月26日のデータを使用した。このうち、傾斜計データとロールデータの変動のパターンにより、南北測線を3つの区域に分けた。これらから1測線だけを抜き出して作成した水深図を図107に示す。この水深図は、左から南北測線(1)、(2)、(3)に対応する。比較対象として東西測線から作成した水深図を図108に示す。
これらより傾斜計とロールデータの変動が一致している南北測線(1)の水深図は、水深の境界の波状のパターンが同傾向であるが、南北測線(1)とは異なる変動を示している南北測線(3)の水深図は、図108で示した水深図と比較すると水深の境界部分が大きく蛇行しているのがわかる。これにより、船体と支柱の動きがが異なっているため、動揺センサーのロールデータだけの処理では、完全に処理できない可能性が考えられる。一方、傾斜計は加速度データを検出することができないため、単純にロールデータの代わりとして使用することはできない。このため、この傾斜計データを使用して動揺補正を実施するためには、さらに検討を要する。
今回のように支柱に測深機を固定して収録したマルチビームデジタルデータから作成した水深図に蛇行パターンが表われている場合には、船体と支柱の動きが異なる可能性がある。このような、船体と測深機が異なった動きをする可能性がある場合には、支柱に傾斜計を取り付け、船内取得データと比較することは有効であると考えられる。
図106 傾斜計(1)のx軸とPOS/MV動揺センサーのピッチデータとの各測線における平均値の比較030_134、016_209)(間隔:20cm)
図107 南北測線より作成した水深図(左から040_1106、
図108 東西測線より作成した水深図(間隔:20cm)
|