|
(配電方式)
第173条 配電方式は次に掲げるものでなければならない。
| (1) |
直流2線式 |
| (2) |
直流3線式 |
| (3) |
交流単相2線式 |
| (4) |
交流単相3線式 |
| (5) |
交流三相3線式 |
| (6) |
交流三相4線式 |
2. 船体は、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合を除き、これを導体として使用してはならない。
(関連規則)
1. 船舶検査心得
173.2(配電方式)
(a)「管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次に掲げる回路を設ける場合とする。
| (1) |
外部電源式陰極防食装置の回路 |
| (2) |
絶縁監視装置の回路 |
| (3) |
セルモーター、雑音防止用コンデンサを備えた無線装置、接地を要する本質安全防爆構造の装置等の限定的かつ局地的に接地する装置の回路。ただし、タンカー及びタンク船の回路にあっては、いかなる場合にあっても派生電流が危険場所を直接流れないときに限る。 |
2. NK規則
2.2.1 配電方式
配電方式は次の(1)から(5)のいずれかにすることができる。
| (1) |
直流2線式 |
| (2) |
直流3線式(3線絶縁式又は中性線接地式) |
| (3) |
単相交流2線式 |
| (4) |
三相交流3線式 |
| (5) |
三相交流4線式 |
3. 〔説明〕配電方式について
配電方式を図で示すと次のようになる。
| (拡大画面:20KB) |
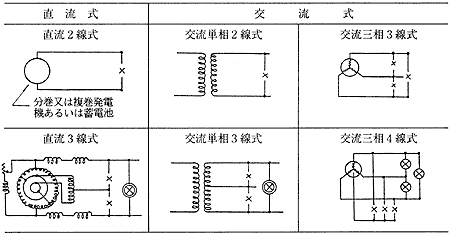 |
注:×、○、◎は負荷を示し、それぞれの図において◎は×の2倍の電圧を○は×の1.732倍の電圧を示す。
集魚灯発電機のように照明と動力を同一の発電機から給電する場合は三相4線式が用いられる。
(配置)
第174条 電気機械及び電気器具は、次項から第4項目までに規定する場合を除くほか、次に掲げる場所に設備してはならない。
| (1) |
通風が悪く、引火性ガス、酸性ガス又は油蒸気がうっ積する場所 |
| (2) |
水、蒸気、油又は熱により障害を生ずるおそれのある場所 |
| (3) |
他動的損傷を受けるおそれのある場所 |
| (4) |
燃焼し易いものに近接する場所 |
2. 水滴、油等の落下又ははねかえりのおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。
3. 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具で、機関室床板より下方に設置し、かつ、ビルジ等により浸水のおそれのあるものは、適当に保護されたもの又は防水型若しくは水中型のものでなければならない。
4. 爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設置する電気機械及び電気器具は、防爆型のものでなければならない。
第175条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機、電動機その他の回転機械の軸方向は、なるべく船首尾方向と一致させなければならない。
(解説)
回転機械の据付方向について(第175条関係)
船体は、ピッチングの方がローリングより傾斜角度が少なく、また、その頻度が少ないので、回転機械の軸方向はローリング方向を避けて船首尾方向に合わせ、運転中の回転機械の軸受等の損耗を防ぐことを考慮したものである。
(関連規則)
船舶検査心得
174.3(配置)
(a)「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具」とは、次のような設備に使用するものをいう。
| (1) |
船舶の推進に関係のある機関(機関規則心得附属書〔1〕「用語の定義」参照) |
| (2) |
セルモーター |
| (3) |
昇降設備 |
| (4) |
端艇揚卸設備 |
| (5) |
非常消火ポンプ |
| (6) |
水密戸開閉装置 |
| (7) |
自動スプリンクラ装置 |
| (8) |
高圧ガス圧縮機 |
| (9) |
通風機(危険物ばら積船ポンプ室等、機関区域及び居住区域用) |
| (10) |
航海用具 |
| (11) |
船内照明設備(集魚灯等業務用に用いられるものを除く。) |
| (12) |
無線電信装置(義務船舶局の場合に限る。) |
| (13) |
固定式イナート・ガス装置 |
| (14) |
暖房機 |
| (15) |
冷房機 |
| (16) |
サニタリーポンプ |
| (17) |
飲料水ポンプ、造水機 |
| (18) |
汚物処理機 |
| (19) |
レンジ、電気炊飯器等の調理器具 |
| (20) |
(1)から(19)に掲げる設備に給電するための発電機、蓄電池及び変圧器 |
175.1
(a)「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機、電動機、その他の回転機械」については、174.3(a)を準用する。
船舶機関規則心得「附属書(1)」による船舶の推進に必要又は関係のある補機は次のとおり規定されている。
7 船舶の推進に関係のある機関
次に掲げるもの
| (1) |
主機及び主要な補助機関 |
| (2) |
推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系並びに発電機(非常電源用に供するものを除く。)及び第1種補機に動力を伝達する動力伝達装置及び駆動軸 |
| (3) |
第1種ボイラ、主ボイラ及び主要な補助ボイラ |
| (4) |
船舶の推進に関係のある補機 |
| (5) |
(1)から(4)までに掲げる機関の運転に必要な圧力容器 |
| (6) |
(1)から(5)までに掲げる機関の運転に必要な管装置(タンクを除く。)及び制御装置 |
24 第1種補機(船舶の推進に必要な補機)
次のいずれかに該当する補機
| (1) |
主機、主要な補助機関、推進軸系又は推進軸系に動力を伝達するための装置のための補機にあっては、次に掲げるもの |
i 潤滑油供給ポンプ
ii 冷却水ポンプ、冷却油ポンプ及び循環ポンプ
iii 燃料油供給ポンプ
iv 復水ポンプ及び真空ポンプ
v 燃料油清浄機及び潤滑油清浄機(主機の運転に必要なものに限る。)
vi 制御用又は始動用の油圧ポンプ及び空気圧縮機
| (2) |
主ボイラ又は主要な補助ボイラのための補機にあっては、次に掲げるもの |
i 給水ポンプ
ii 燃料ポンプ
iii 強制給排気送風機
| (3) |
ビルジポンプ |
| (4) |
その他管海官庁が指示するもの |
25 第2種補機(船舶の推進に関係のある補機)
次のいずれかに該当する補機
| (1) |
第1種補機 |
| (2) |
バラストポンプ及び消火ポンプ(非常用のものを除く。) |
| (3) |
操船補機(操舵装置等をいう。)、甲板補機(揚錨機、係船機等をいう。)及び荷役装置冷蔵設備等に用いられるもの |
| (4) |
通風機(機関室、ボイラ室、タンカーの貨物油ポンプ室等の取扱者の健康に障害を与えるガス又は火災の危険性を有するガスが発生するおそれのある場所に設置するものに限る。) |
| (5) |
その他管海官庁が指示するもの |
(取扱者の保護)
第176条 電気機械及び電気器具は、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
2. 電気機械又は電気器具の故障により、その露出金属部が帯電するおそれのある場合は、取扱者を保護するための適当な措置を講じなければならない。
(関連規則)
1. 船舶検査心得
176.2(取扱者の保護)
(a)「取扱者を保護するための適当な措置」とは、次に掲げるいずれかの措置をいう。
| (1) |
接地すること。この場合において、移動用の電気機械及び電気器具にあっては、その金属製枠をケーブル又はコード内の導体によりプラグ及びレセプタクルを通じて接地すること。 |
| (2) |
導体間電圧が50V(交流にあっては実効値)を超えない電圧による給電とすること。ただし、単巻変圧器により給電する場合を除く。 |
| (3) |
1の電気機械又は電気器具のみに対する給電であって 250Vを超えない電圧による給電とすること。ただし、当該給電は安全絶縁変圧器により行うこと。 |
| (4) |
電気機械又は電気器具を二重絶縁構造とすること。 |
(性能)
第177条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具は、船舶が縦に10度若しくは横に15度(第6章の規定により備え付ける非常電源及び臨時の非常電源にあっては22.5度)傾斜している状態又は22.5度横揺れしている状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。
ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないものと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。
2. 電気機械及び電気器具は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
177.1(性能)
| (a) |
「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具」については、174.3(a)を準用する。 |
| (b) |
10°のトリム及び15°のヒール並びに22.5°のローリング状態において、本項の規定を満足していること。 |
(解説)
電気機械及び電気器具は船体に取付けた状態のもとで船体が次に示す角度で動揺又は傾斜しても性能に支障を生じないものであることが第177条で規定されている。
|