|
(2)簡易計算法
NK規則によれば回転機の短絡電流が明らかでない場合には短絡電流を下記により決定することが出来ることになっている。
(a)直流の場合
接続される発電機(予備機を含む)に対し:
定格電流の総和の10倍
同時に使用される電動機に対し:
定格電流の総和の6倍
(b)交流の場合
接続される発電機(予備機を含む)に対し:
定格電流の総和の10倍
同時に使用される電動機に対し:
定格電流の総和の3倍
(3)短絡電流計算例
今、300〔kW〕の発電機が3台並行運転されており、運転中の電動機負荷が480〔kW〕ある場合の負荷への給電線( 図2.15のB点)における短絡発生後1/2サイクル時点の短絡電流を求める。 なお、発電機の諸定数は次のとおりとする。
U0=450 〔V〕(実効値)
In=480 〔A〕
X''d=0.158 〔P.U〕
X'd=0.208 〔P.U〕
T''d=0.0046 〔sec〕
Tdc=0.0167 〔sec〕
(a)IEC方式
(i)発電機短絡電流の交流分実効値及び直流分
(式4)及び(式5)から単位法に換算し発電機短絡電流の交流分実効値及び直流分の値は次のようになる。
| (拡大画面:14KB) |
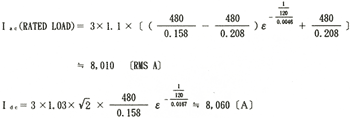 |
(ii)発電機短絡電流の最大値
(式6)から発電機短絡電流のピーク値は次のようになる。
| (拡大画面:2KB) |
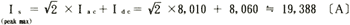 |
(iii)電動機短絡電流の交流分実効値
(式10)から電動機短絡電流の交流分実効値は次のようになる。
(iv)電動機短絡電流の最大値
(式11)から電動機短絡電流の最大値は次のようになる。
交流分実効値=8,010+3,160=11,170 〔A〕
ピーク値=19,388+7,900=27,288 〔A〕
(v)給電線端短絡電流
| (拡大画面:37KB) |
 |
| (拡大画面:52KB) |
 |
| (拡大画面:12KB) |
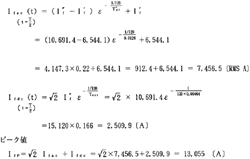 |
(b)簡易計算法
(i)発電機短絡電流
3×10×480=14,400 〔A〕
(ii)電動機短絡電流
3×790=2,370 〔A〕
14,400+2,370=16,770 〔A〕
この値はIEC方式の交流分実効値(11,170〔A〕)に相当するのである。
|