|
3. 電路金物の取付け
本章でいう電路金物とは、ケーブル布設に関する金物類(主電路金物、電線馬、電線管、電線貫通金物など)をいい、第4章のケーブル布設に先立って甲板、隔壁などに取付け、ケーブルを支持あるいは保護するものをいう。
電路布設位置などの位置出しは、電気機器配置図、金物取付図などを基に、曲尺、定規、張糸などを使用して寸法及び形状を、石筆など消えにくいもので、正確に明示する。単位はミリメートル(mm)を用いる。なお、複雑な場所や重要な機器及び電路には、模型や形棒を用いて行う場合もある。
なお、配管類や他の装備品と関係のある機関室などでの位置出しに当たっては、関連部門と十分協議を行い、総合的に検討しなければならない。
(1)電路の位置出し
電路の位置出しに当たっては、次の事項に注意する。
(1)電路布設場所としての適否。
(2)屈曲を避け、できるだけ直線的な位置決め。
(3)屈曲させる場合のケーブル屈曲の許容最小半径。
(4)電路と通風トランクやパイプ類との交錯場所の位置決め。
(5)壁面からの出張り具合。
(6)電路幅の適否。
(7)貫通金物やコーミングなどの取付け、締付けスペースの適否。
(2)機器の位置出し
機器の位置出しに当たっては、次の事項に注意する。
(1)機器の周囲の温度及び湿度の予測。
(2)雨水などの滴下の可能性、及び蒸気管、水管などパイプ類の継手部と弁類の位置。
(3)取付け方向及び取付台の適否。
(4)電線貫通金物の位置及びケーブル導入口の適否。
(5)防振ゴムを使用する機器における交換のためのスペース。
ケーブルの支持・固定間隔については、船舶設備規程及びNK鋼船規則で表3.1のように規定されているが、一般的には、以下に記述するような間隔を標準としている。
| (拡大画面:24KB) |
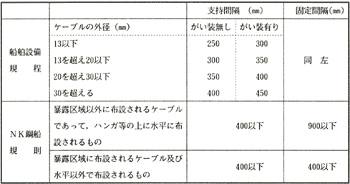 |
電気艤装金物類を鋼船体に溶接して、取付ける場合には、下記による。
(1)溶接方法
金物類の溶接は、原則として、暴露部、便所、ギャレー、浴室など水が直接かかる場所では全周溶接を、その他の場所では片面及び両端巻込み溶接以上の溶接を行う。
図3.1 溶接法の例
(2)溶接脚長
金物類の溶接脚長は、次式による値を目安とする。ただし、最小3mmとする。
w:溶接脚長(mm)
t:金物の板厚(mm)
ケーブルの布設の際はできるだけ船体構造物に開口を設けない。ただし、やむを得ず開口する場合、開口はできるだけ小さくする。
なお、規定値を超えて開口する場合、並びに、特殊船型船及び特殊材料の使用場所などの開口については、船体主務者と十分協議を行う。
開口禁止区域を図3.2に、補強の必要な開口区域を図3.3に、補強を要しない開口区域を図3.4に示す。
| (拡大画面:27KB) |
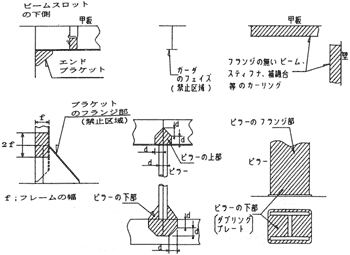 |
図3.2 開口禁止区域の例
図3.3 補強の必要な開口区域の例
| Aの範囲に入る箇所のケーブル穴は補強をしなくても良い。 |
| A |
: |
開口面積 |
A≦1/3SH |
|
| D |
: |
穴深さ |
D≦1/4H |
|
| L |
: |
穴長さ |
L≦1/3S |
|
| F |
: |
穴下側母材深さ |
F>1/4D |
Fmin=75mm |
| E |
: |
穴上側母材深さ |
E>1/3D |
Emin=75mm |
| a |
: |
穴端とビームスロットの距離 |
a>1/5S |
a>1/2(l1+R) |
| b |
: |
穴と穴の距離 |
b>2/3H |
b>1/2(L1+L1) |
| r |
: |
穴コーナ |
r≧1/10D |
rmin=25mm |
図3.4 補強の不必要な開口区域の例
|