|
1.3.2 鋼材の強さ
鋼材の強さを材料試験で求めるには、第1.2図のような試験片(1号試験片で、主として鋼板、平鋼及び形鋼に用いる)を作り、両端部分を試験機のチャックでつかみ、引張荷重を加える。これを引張り試験といい、中央の並行な部分(厚さTmm、幅Wmm)は荷重がかかるにつれて伸び、荷重がある限度に達するとくびれが生じ、それからは伸びがどんどん増して荷重はすこしずつしか上がらず、遂にはくびれの部分から破断する。中央平行部の中に設けた2個の標点マークの間の最初の長さをLとし、その間の伸びxを試験中刻々に測定し(精密伸び計にて)、これと加えた荷重Pとの関係を図示すると図1.3のようになる。
第1.2図 1号引張試験片
| (拡大画面:21KB) |
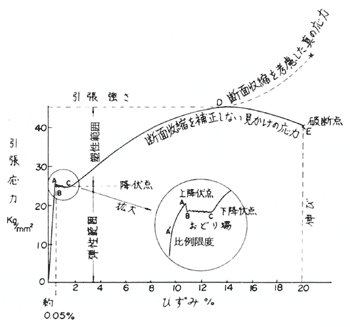 |
1.3図 鋼材の応力ひずみ曲線
第1.3図はあとでいろいろと応用するのに便利なように、縦軸に引張応力S=P/W×T(kgf/mm2)を、横軸にひずみe=x/L(単位なし)をとっている。これを応力ひずみ曲線という。
鋼材の応力ひずみ曲線の特長について説明しよう。OからはA'までは非常に急な立ち上がりをもつ直線である。しかしA'−Aではこの直線からややずれている。Aに達すると応力はBまでやや下り、B−C間では応力はこまかい上下をくりかえして上がらず、ひずみだけが増える。C点からゆっくりと応力とひずみが増し、D点で応力の最高値に達し、これから先は断面がくびれ出し、見かけの応力は下がりひずみは増し、遂にE点に至って破断する。図に示すようにO−A'間を比例範囲、O−A間を弾性範囲、B点以降を塑性範囲といい、A'点を比例限度、A点を上降伏点、B点を下降伏点、B−C間をおどり場と名付ける。D点の応力を引張り強さ、E点のひずみを破断時の伸びといい、重要な値である。
比例限度内、すなわちOからA'までは応力ひずみ曲線が直線であるが、このことは、応力を2倍とすれば、ひずみも2倍となることを示しており、応力をひずみで割った値をEで示せば、E=S/eが材料によって一定の値をとることとなる。別の言葉で表わせば応力とひずみは比例することとなる。そしてこのEは比例係数の意味があり、これをとくに発見者の名にちなんでヤング係数(または縦弾性係数)とよび、鋼材では21,000kgf/mm2(205,94ON/mm2)である。
弾性限度内、すなわちOからAまでの間の弾性範囲では、力を加えて変形させ(応力を加えてひずみを起こさせ)、また力をとり除くと(応力を0とすると)変形(ひずみ)が全然残らない。
第1.4図で説明すると、OからX点まで応力を加え、つぎに力をとりのぞくと、Xから同じ線を伝わってひずみが減じ、O点に帰る。これを弾性変形という。鋼船の各部分も航海中にこのような応力を受けている間は、外板の凹みも、肋骨の曲がりも起こらず安全である。
弾性限度を超えて応力をかけると、弾性変形に加えて塑性変形を起こすので、応力をとりのぞいても、ひずみは零にならず、塑性変形の部分が残る。
第1.4図で0からYまで変形させ、応力を零にすると、YからZにもどり、OZだけの塑性変形(永久変形)が残る。船舶の航海中にこのような応力がかかってはならないが、逆に造船所で鋼板にカーブを付けたり、折り曲げたりするときは、この塑性変形を利用している。このように常温状態で大きな力をかけて鋼材に塑性変形を起こさせることを冷間加工という。このときに、熱を加えてやれば、鋼材はあめのように軟らかくなり、あまり力を加えなくても塑性変形をする。これを熱間加工という。また鋼板を線状に加熱して任意の形状に曲げることができるのも、熱による膨張と、塑性変形を巧みに利用しているのである。
つぎに鋼材を低温(0℃〜−20℃以下)にし、試験片に切欠きを作って、引張試験または衝撃試験を行なうと、第1.5図に示す点線のように、低い応力でしかも伸びがほとんどなくてガラスのようにもろく破断する。これをぜい性といい、これに対して伸びを伴う粘い性質をじん性という。この低温ぜい性は、鋼材にリン、イオウなどの成分の多いとき、低温のとき、鋭い切欠き(溶接欠陥など)が存在するとき起こりやすい。船が突然真二つに折れて沈んだなどという事故は、このぜい性破壊が原因となっていることがある。大型船の厚板の部分にはぜい性破壊の起こりにくい溶接構造用鋼を使うべきである。また、LNG(液化石油ガス)タンカーのタンクなど極低温の場合にはニッケル鋼、ステンレス鋼またはアルミ合金など、ぜい性破壊を起こさない材料を使用する。
第1.4図 弾性と塑性
鋼材で作った構造物(船、橋など)は通常の使用条件では弾性限度内で使用しなければならない。もし何かのはずみで大きな力のかかった場合(衝突、座礁)にも、少なくとも塑性範囲内に止まって、凹んだり、曲ったりしただけで破断(破孔)しないことが望ましい。もしここでぜい性破壊を起こすと瞬時に全体が破壊して大惨事となる。
塑性をもっている(じん性がある)ということは、上に述べたような過大な力を受けたときに、その場所だけが伸びて力を逃がし、破断に至らせないという重要な性質である。また、さきに述べたように加工の際にも必要な性質である。高温となると第1.5図破線のように粘り軟らかくなり、さらに加工がし易くなる。
第1.5図 じん性とぜい性
鋼材の強さで、もう一つの大切なものがある。それは繰返し力をかけると、その力の大きさと回数によって鋼材が弱くなることである。これを疲れ強さという。たとえば針金を折り曲げると一回では折れないが、数回くりかえすことで折れるような例がある。この場合は塑性変形を起こすような高い応力を加えているので、数回のくりかえしで折れるのであるが、応力が低いと何万回、何十万回くり返して、やっと切れるようになり、さらに応力を小さくすれば百万回〜千万回(これを106回、107回という)も繰返しても折れなくなる。この限界の応力を疲れ限度といい、静かに連続的に引張った場合の破断応力(極限強さ)の1/2〜1/3にも下がる。したがって、機械台、船尾のプロペラ附近の振動をひどく受ける部分では、部材の寸法を増して応力を低くしておかねば、損傷を生ずるおそれがある。ましてこの部分は溶接がし難かったり、曲げ加工の程度の高いところで、鋼材も弱くなっていることが多いので注意が必要である。
どれだけの応力では、何回の繰返しに耐えるかの限界を示す曲線を疲れ限度曲線(S−N曲線)といい、第1.6図に一例を示す。図中の線の下方では破壊せず、上方では破壊することを示している。
船体の寿命を20年とすると、20年間に波浪による応力のくり返し数は1kgf/mm2(9.8N/mm2)の応力でで大よそ106〜107(百万回〜千万回)、10kgf/mm2(98N/mm2)の応力の程度で103〜104(千〜万回)と推定される。応力集中率(平均的な応力より、開口附近の部分の応力が高くなっている度合)を3倍、疲れ限度を20kgf/mm2(196N/mm2)とすると、船体の普通の部分は大体20年間に疲れ破壊はしないと考えられる。したがって、とくに応力の高い個所(30kgf/mm2(294N/mm2)附近)では低サイクル疲れを起こして割れが入るという以外にはあまり疲れについて心配する必要はない。これは部材の直交する箇所とか、肘板の付根とか、不連続な構造の場所であって、ここに割れが入るのは、就航後しばらくして激しい波にもまれた後などに起こり、これが低サイクル疲れ(高応力疲れ)と考えられている。この割れ目は、前に述べたぜい性破壊のスタート点となることもあり、注意が必要である。
| (拡大画面:10KB) |
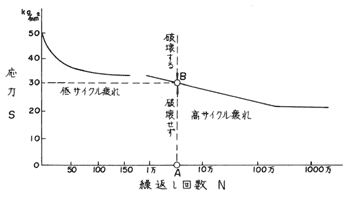 |
第1.6図 疲れ曲線(SN曲線)
1.3.3 鋼材の腐食と衰耗
鋼材の大きな欠点は空気中および海水中、とくに海水のしぶきのかかるところで腐食しやすいことである。最近は鋼材の下地処理(サンドブラスト、ショットブラスト、プライマーコーティング)と塗料が格段に進歩したが、タンク内、二重底内、単底下部などは腐食を完全に防止することはできない。塗料を塗らない状態で、軟鋼板は海水中で10年間に1〜0.6mm位腐食すると考えてよい。この量は大きな応力がかかった状態とか、電流が流れている状態では非常に多くなる。
船体の衰耗量は船齢20〜25年の場合、最大2.5mmに達した例があり、平均の年間衰耗量として、船底外板0.1mm、船側外板、上甲板0.13mm程度と考えてよい。したがって、船齢の終点において所要の強さを必要とするから、新船のときは、腐食余裕として2〜2.6mmを追加しておく必要がある。但し、鋼船の構造規則にはこの値を含んだ寸法が示しているから、設計に当っては、別に腐食余裕を加えてやる必要はない。
1.3.4許容応力と安全率
船体構造を設計する際にどの位の応力を受けるように部材寸法をきめるか、その許容応力が引張強さの何分の一になっているかはもっとも大切な問題である。
一般には鋼材の引張強さを許容応力で割った安全率は3〜4の程度であるから、許容応力はSM400Aで10〜14kgf/mm2(98〜137N/mm2)とする。
この安全率には、構造計算の誤差、工作の誤差、材料のバラツキ、外力推定の誤差などが含まれている。
一方、船体主要部材の寸法は鋼船の構造規則に示されているので、この寸法から標準状態について許容応力を逆算すると、船の長さが小さいときは許容応力が低く、船が大きくなると高くなり、たとえば60mの長さの船で8kgf/mm2(78N/mm2)200mの船で15kgf/mm2(147N/mm2)となり、安全率は小船で大、大船で小という結果となる。しかしこれは小船では標準状態がゆるやかにすぎること(つまり、もっときびしい状態であり得ること)を示しているにすぎない。
|