|
5.2.6.1.3.2 航空機(ヘリコプター)の試験結果
航空機レーダ画面によるSART信号の視認性の確認結果については、表5.2−18に示すとおりで、航空機用レーダによる胴衣装着用SARTの最大探知可能距離は、SART信号の強さCレベルで、高度1000フィート及び3000フィートでは約12マイル、また、500フィートの高度では約7マイルであった。
※ Cレベル:レーダ取扱い者が視認可能なレベル
| 表5.2−18
航空機用レーダによる視認性結果(高度500〜3000フィート) |
| |
SART信号の強さ
|
| C:SART信号がときどき見え始める。(離脱時は、見えにくくなる。) |
|
B:SART信号の強さが他のエコーより弱い。 |
|
A:SART信号の強さが他のエコーと同程度以上となる。 |
| |
M:SART信号が同心円状になる。(エコーの塊のようなリングとなった。) |
5.2.6.1.3.3 レーダ実験車による観測結果
1. 観測の概要
ダミー人形に取り付けた円偏波SARTを小型船に搭載あるいは曳航し、静岡市大谷付近の駐車場(海岸(波打ち際)から約90m)に駐車したレーダ車の舶用レーダを用いて観測を行なった。図5.2−36に黒い矢印で概略の位置を示す。白い矢印は、小型船の概略の動きを示しており、観測番号の内容は表5.2−19小型船舶の移動の概要に示す。
| (拡大画面:491KB) |
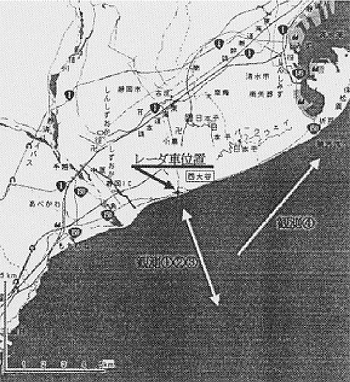
図5.2−36
観測地点とSARTを搭載した小型船の動き
|
円偏波SARTを載せた小型船舶の動きを表5.2−19にまとめる。動きの概略は図5.2−36中の白い矢印で示した。いずれの場合も円偏波SARTはダミー人形に取り付けられており、スイッチが入った状態である。
| |
小型船の移動 |
円偏波SARTの状況 |
| 観測(1) |
約300m離れた位置から4マイル沖まで直進。 |
船上においた状態。 アンテナ高さ1.3m。 |
| 観測(2) |
Uターンしてレーダ車目指して直進。 |
同上。ただし船橋の陰になっている。 |
| 観測(3) |
約600m離れた位置から約2マイル沖まで直進。 |
海中に投下。曳航。 アンテナ高さ0.1m。 |
| 観測(4) |
上記の位置より三保(清水港)を目指して東北東方向へ航行。レーダ車との距離が約1.4マイルまで縮まった後約5.7マイル離れるまで観測。 |
船べりにダミー人形ごと結んだ状態。 |
|
2. 計測システム
円偏波SARTの信号を舶用レーダの画面上およびディジタル・オシロスコープで確認・記録した。
(1)舶用レーダ
使用したレーダの主な仕様を次に示す。
| 周波数 |
9410MHz±30MHz |
| 尖頭出力 |
25kW |
| 空中線 |
9ft 水平ビーム幅 0.8° 垂直ビーム幅 0.6° |
| パルス幅 |
3マイルレンジ 0.2μs 6マイルレンジ 0.6μs |
| 偏波面 |
水平偏波 |
|
(2)ビデオ信号の記録
レーダのビデオ信号をディジタル・オシロスコープでA/D変換し、ハードディスクに記録し、ブロック図を次に示す。
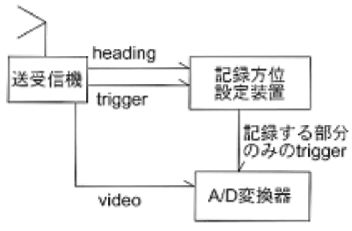
(レーダビデオ信号の記録システムのブロック図) |
レーダ送受信機からヘッディング信号とトリガ信号を取り出して、データを記録する方位(角度)設定装置へ入力する。この記録方位設定装置では、設定された部分のみトリガ信号を出力する。
レーダ送受信機からはビデオ信号も取り出し、ディジタル・オシロスコープに入力し、A/D変換を行う。そのとき、記録方位設定装置から出力されたトリガ信号を用いて、決められた方向のみのビデオ信号を記録する。A/D変換のサンプリング周期は1ns〜4nsである。
(3)映像の記録
レーダ画面の映像信号を、ダウンコンバータを通してビデオテープに記録した。ブロック図を次に示す。
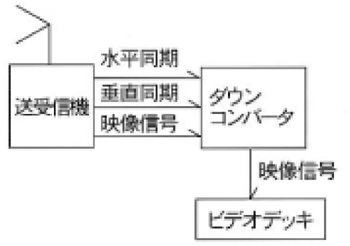
(映像記録システムのブロック図) |
3. 結果
ビデオ信号の記録結果の一例を次に示す。色が濃い程、信号が強いことを示している。
| (拡大画面:61KB) |
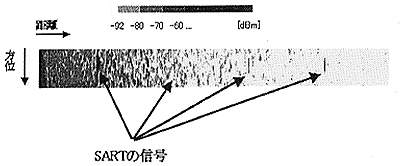
(ビデオ信号の記録例) |
このデータを用いて、円偏波SARTの1つ目の信号の最大値を求め、レーダのハイトパターンに重ねて表した。図5.2−36の観測(3)の場合を図5.2−37に示す。
ハイトパターンの一番上はレーダからSARTへのパターン、その下の2本はSARTからレーダへのパターンである。レーダからSARTへのパターンと同位相のものは水平偏波の場合、位相の異なるものは(5/4)πずらした場合のパターンである。ドットが実測したデータをプロットしたものである。
| (拡大画面:103KB) |
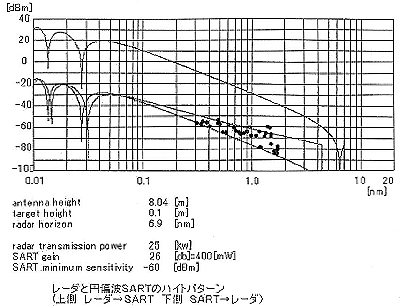
図5.2−37 SARTアンテナ高さ10cmの
場合のハイトパターンと実測データ |
|