植生・植物編
砂浜海岸環境調査票(植生・植物編)
(拡大画面: 89 KB)
調査した砂浜海岸の植物群落や植物の様子
(拡大画面: 30 KB)
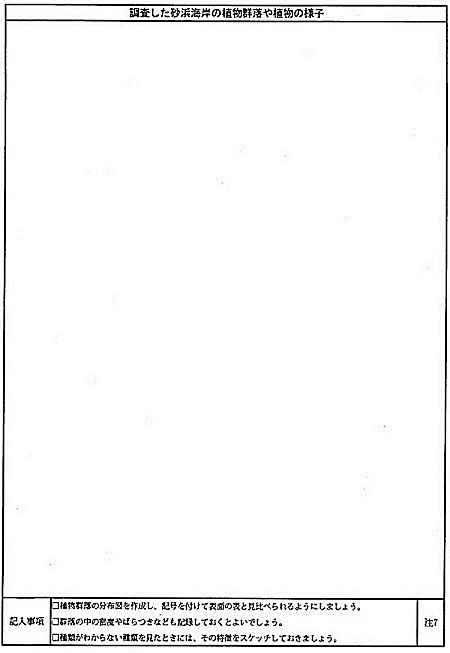
| 砂浜環境調査票(植生・植物編)の記入上の注意とヒント |
| 注1 |
【都道府県名】【市町村名】【地先名】【海岸の名前】【俗称】をそれぞれ記入します。
【海岸の名称】は調査する海岸の近くに○○○海岸とかかれた看板が立っていると思いますので、その名前を記入しましょう。
看板が見つからない場合には【俗称】としてなんと呼ばれているのか近所の人に聞いて書き記しましょう。 |
注2
注3 |
【調査年月日】【調査時間帯】は環境調査をするときには非常に大切な項目です。必ず記録しましょう。
また、時間帯は、海の潮位の状態が満潮なのか干潮なのかを知る上で重要です。開始時間終了時間を記録しましょう。 |
| 注4 |
【調査者】の欄には調査に当たった【団体名 学校名】と調査に参加した人の名前を記録します。大勢で調査した場合には班長や指導者の名前を書いておきましょう。 |
| 注5 |
植生・植物の調査・観察方法は観察する砂浜に分布する植物群落をスケッチ(概略の地図)を描いて記録しましょう。
イメージ図を次ページに示しましたので、参考にしてください。
【群落の記号】
スケッチした地図に示した植物群落に記号を付けて、表のこの欄に記入します。「ハマヒルガオ群落」「ヨモギ群落」など記号でなくても構いません。
チェック:「群落」とはある優占する植物種(たくさんみられる)を中心とした植物の集合体です。
例えば、川沿いの湿地には「ヨシ群落」がよく見られます。これはヨシが優占した植物の集合体ということです。
ヨシ群落の中を観察すると、ヨモギやセンダングサ、ヒルガオ、クサヨシなども見られます。
この調査票でも「優占している植物を群落名として名前を付ける」ことにします。
【主な種類】
群落内に生育している主だった植物の種名を記録します。わからない種類の植物を見つけた場合には、押し花などにして持ち帰り、図鑑で確認しましょう。
【被度】
群落の中の植物が地面を覆っている密度を「被度」として表現します。
群落を代表するような場所を見つけ、1m〜5m四方の中で植物が生えている面積がそのうちの何%を占めているかを観察します。
次ページの図を参考にしてください。 |
| 注6 |
【確認した種類】
群落を言うほどの面積もなく砂地に生えている植物もあると思います。それらの植物の種名を記録していきましょう。わからない種類があった場合には押し花などにして持ち帰り、図鑑で調べてみましょう。その場合、花や葉だけではなく、根から採取すると種類を調べるときに役に立ちます。 |
| 注7 |
植物群落の分布状況や群落の断面図などをスケッチしておきましょう。 |
植物分布図のスケッチ模式図
植物群落の分布の他に、周辺の状況(道路や住宅地、川の様子、断面図の位置など)をスケッチして記録しておきましょう。
また、概路の位置がわかるように距離もメモしておきましょう。
A−A’の断面の模式図
断面の模式図をスケッチしておくと、動物の生息環境を知る上で役に立ちます。
植物群落の被度のスケッチ
2m×2mの枠の中に、どれだけの密度で植物が生育しているかを記録します。
※クロマツ林など広い樹林で樹木の被度をみる時には10m×10m位の面積を観察します
<植物>
林 弥栄 「原色樹木大図鑑」北隆館
山渓ハンディー図鑑「野に咲く花」山と渓谷社
山渓ハンディー図鑑「樹に咲く花1・3」山と渓谷社
<昆虫>
「原色日本甲虫図鑑(II)、(III)、(IV)」保育社
<両生・は虫類>
自然観察シリーズ 日本の両生類 爬虫類 小学館
<烏類>
財団法人日本野鳥の会「フィールドガイド日本の野鳥」
山渓ハンディー図鑑「日本の野鳥」山と渓谷社
「野鳥ガイドブック」 永岡書店
<ほ乳類>
フィールドガイド足跡図鑑
<魚類及び海岸生物>
フィールド図鑑「海岸動物」 東海大学出版会
自然観察と生態シリーズ8 「海辺の生物」 小学館
山渓フィールドブックス8 「海辺の生きもの」 山と渓谷社
<漂着物>
「海流の贈り物漂着物の生態学」 平凡社
ガイドブック15「漂着物図鑑」 平塚市博物館
<生物全般>
「自然大博物館」小学館
<砂浜海岸の動植物について紹介しているホームページ>