 |
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年5月18日02時12分
都井岬東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船第八長久丸 貨物船フェニックスセブン
総トン数 19トン 3,853.00トン
全長
92.00メートル
登録長 14.95メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力
2,427キロワット
漁船法馬力数 160
3 事実の経過
第八長久丸(以下「長久丸」という。)は、まぐろはえ縄漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか4人が乗り組み、操業の目的で、船首1.30メートル船尾1.80メートルの喫水をもって、平成10年5月2日13時00分宮崎県油津漁港を発し、奄美大島東方沖合40海里ばかりの漁場に向かい、まぐろ7トンを獲て、同月17日02時00分同漁場を発進し、帰途に就いた。
A受審人は、種子島南東方沖合14海里ばかりを通過して北上し、翌18日00時00分都井岬灯台から176度(真方位、以下同じ。)18.7海里の地点において、針路を005度に定めて自動操舵とし、機関を8.5ノット(対地速力、以下同じ。)の全速力前進にかけ、法定灯火に加えて黄色回転灯を表示してレーダーを3.0海里レンジに設定し、これに連動した見張り警報装置(以下「警報装置」という。)を1.5海里で警報音を発するように設定して進行した。
ところで、A受審人は、操業中は専ら船橋内で操船を行い、操業中の甲板作業に従事せず休息をとることができることから、航海中の船橋当直については好天で一昼夜程度の航海であれば自ら単独で行い、悪天候のときは自ら単独で8時間行って残る時間を他の乗組員が全員で各2時間の輪番交替制で行うようにしていた。
発航後、A受審人は、いつものように他の乗組員を休息させ、単独で操舵操船にあたり、船橋内で1時間30分ほどの仮眠を2回とったのみで船橋当直を続け、長時間にわたる当直による疲れと睡眠不足で、針路を定めたころから著しい眠気を感じていたが、もう少しで入港できるからあとしばらくの我慢と思い、休息中の乗組員を昇橋させて2人当直とするなど居眠り運航の防止措置をとることなく、船橋の右舷側に設置したいすに座って見張りにあたりながら続航し、01時00分ごろ燃料の補給を終えて再びいすに座り、いつしか居眠りに陥った。
A受審人は、02時06分都井岬灯台から108度2.9海里の地点に達し、右舷船首30度2.0海里のところに前路を左方に横切るフェニックスセブン(以下「フ号」という。)の白、白、紅3灯を視認することができ、その後その方位がわずかに右方に変わっているものの、明確な変化がなく、衝突のおそれがある態勢で接近したが、居眠りに陥っていてこれに気付かず、同船の進路を避けないまま進行した。
A受審人は、02時08分警報装置の作動音で目が覚め、同所に座ったままレーダーを見て、その画面上で右舷船首31度1.4海里のところにフ号の映像を認めたものの、その灯火を確かめることもしないで、警報装置のスイッチを切り、再び居眠りに陥り、依然としてフ号の進路を避けないまま続航中、02時12分都井岬灯台から090度2.8海里の地点において、長久丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首がフ号の左舷側中央部に前方から55度の角度で衝突した。
当時、天候は雨で風力2の南南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、視界は良好であった。
また、フ号は、日本台湾及び香港の各港間を就航する船尾船橋型定期貨物船で、韓国人船長B、フィリピン人二等航海士Cほか韓国人2人及びフィリピン人11人が乗り組み、鋼材3,818トンを載せ、船首5.24メートル船尾6.54メートルの喫水をもって、同月16日18時00分兵庫県尼崎西宮芦屋港を発して香港に向かい、室戸岬、足摺岬南方沖合を通過して南下した。
C二等航海士は、翌々18日00時00分宮崎県戸崎鼻東方13海里ばかりの地点で前直の三等航海士から当直を引き継ぎ、操舵手に補佐させて当直に就き、01時35分都井岬灯台から055度10.2海里の地点において、針路を220度に定めて自動操舵とし、機関を13.0ノットの全速力前進にかけ、法定灯火が点灯されていることを確認して進行した。
C二等航海士は、01時55分左舷船首10度5.7海里ばかりのところに長久丸の点灯する黄色回転灯を初めて視認し、その後その方位に顕著な変化が認められなかったところから、02時05分都井岬灯台から078度4.2海里の地点に達したとき、針路を230度に転じ、操舵手に手動操舵に切り替えるように指示し、同船を監視しながら進行した。
C二等航海士は、02時06分都井岬灯台から080度4.0海里の地点に達したとき、長久丸が左舷船首15度2.0海里となって同船の白、緑2灯を視認し、その後同船が前路を右方に横切る態勢で、方位がわずかに右方に変わっているものの、明確な変化がないまま接近するのを認めた。
C二等航海士は、自船の船首までの長さから、衝突のおそれがあると認め、長久丸に向けて探照灯を数回点滅させ、長久丸の避航を期待して見守るうち、同船に一向に避航の気配が認められないまま接近し、02時10分同船が左舷船首11度1,180メートルとなって適切な避航動作をとっていないことが明らかとなり、自船の操縦性能を考慮して、衝突を避けるための協力動作をとることとしたが、機関を停止するなと協力動作を適切に行わないまま、右転によって替わすこととし、操舵手に針路を240度にするよう令し、同針路に転じて進行中、フ号は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
B船長は、C二等航海士から衝突の報告を受け、直ちに昇橋して事後の措置にあたった。
衝突の結果、長久丸は船首部を大破し、フ号は左舷側中央部外板に凹損を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、夜間、都井岬東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、長久丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、前路を左方に横切るフ号の進路を避けなかったことによって発生したが、フ号が、衝突を避けるための協力動作が適切でなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、都井岬東方沖合を漁場から油津漁港に向け北上中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、休息中の乗組員を昇橋させて2人当直とするなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかしながら、同人は、あとしばらくの我慢と思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、フ号の進路を避けないまま進行し、同船との衝突を招き、長久丸の船首部を大破し、フ号の左舷側中央部外板に凹損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
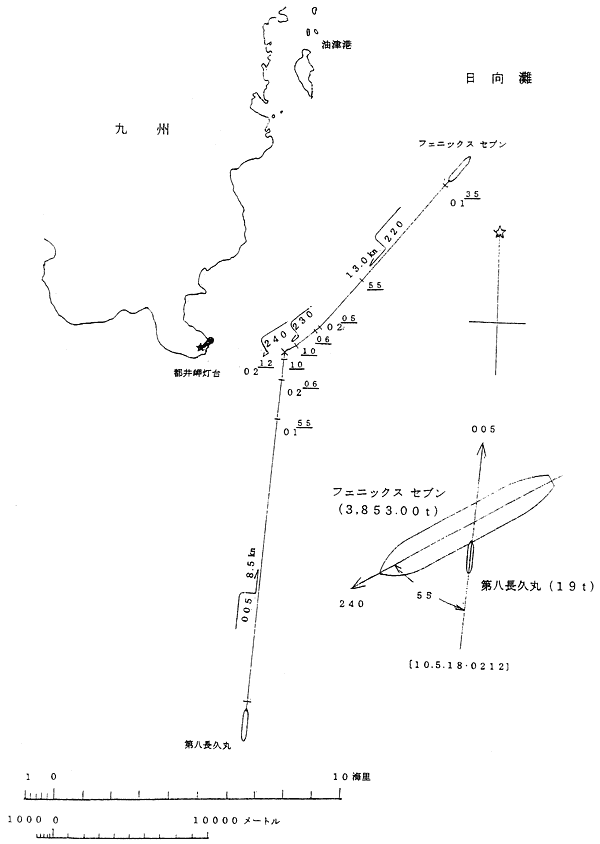 |