 |
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年11月17日16時03分
福山港
2 船舶の要目
船種船名
貨物船第三太賀丸 貨物船第三昭惠丸
総トン数 2,548.82トン 698トン
全長 97.22メートル
73.59メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 2,059キロワット
1,471キロワット
3 事実の経過
第三太賀丸(以下「太賀丸」という。)は、主に瀬戸内海周辺の諸港間で、セメントの運搬に従事する1基1軸固定ピッチプロペラを装備し、スラスタを有しない船尾船橋型セメント撤積運搬船で、A受審人ほか12人が乗り組み、セメント1,937トンを積載し、船首3.87メートル船尾5.09メートルの喫水をもって、尼崎西宮芦屋港へ向かう目的で、平成9年11月17日15時55分福山港内の日本鋼管福山港新涯導灯(前灯)(以下「導灯」という。)から126度(真方位、以下同じ。)1.4海里の中国製鋼岸壁に入船左舷付態勢から離岸を開始した。
ところで太賀丸着岸岸壁の前面水域は、港外と港奥とを結ぶ両側を製品岸壁等に挟まれた可航幅約300メートルの通称分岐航路と呼称される水路となっており、太賀丸は、ほぼ正横方向に錨鎖6節を延出して船首右舷錨を、右舷船尾部からもワイヤー約110メートルを同方向に延出してケッジアンカーを水深約15メートルのところにそれぞれ投入して係岸していた。
発航時A受審人は、船橋で操船指揮を執り、機関操作に機関長を、操舵に甲板手をそれぞれ就け、船首部に一等航海士ほか2名を、船尾部に二等航海士ほか1名をそれぞれ配置して、係留索を放すと共に前示錨鎖及びワイヤーを巻き始め、着岸岸壁とほぼ平行に離岸を開始した。
15時58分A受審人は、ケッジアンカーを揚収したのち、右舵一杯としたまま機関を適宜前進にかけて錨鎖の巻上げ作業中、同時59分残り錨鎖が約2節となったとき、西方950メートルばかりの港奥から出航してくる第三昭惠丸(以下「昭惠丸」という。)を視認でき、その後衝突のおそれのある態勢で接近する状況であったが、揚錨作業などの離岸操船に気を奪われ、見張りが不十分となり、同船に気付かず、揚錨作業を一時中断して同船を避けることなく、同作業を続行した。
A受審人は、16時01分船体が水路に直角となって揚錨したとき、左舷正横方向350メートルばかりのところに、自船に向首接近する昭惠丸を認めたが、同船は自船の船尾を替わして航過するものと思い、同時01分半機関を極微速力前進とし、続いて注意喚起のため発光信号を点滅すると共に操船信号短音1回を吹鳴して同時02分半微速力前進にかけているとき、太賀丸は、16時03分導灯から120度1.4海里の地点において、わずかな前進行きあしを持って035度を向首したその左舷中央部に昭惠丸の船首部が後方から70度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力2の西南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
また、昭惠丸は、専ら瀬戸内海で砂利採取及び運搬に従事し、フラップラダー、バウスラスタ及び固定ピッチプロペラを装備する船尾船橋型砂利採取運搬船で、B受審人ほか6人が乗り組み、空倉のまま、船首1.0メートル船尾3.0メートルの喫水をもって、同日15時55分導灯から134度1,040メートルの分岐航路に面した箕沖岸壁を発し、愛媛県越智郡大島に向かった。
B受審人は、発航時から操舵操船に当たり、15時59分導灯から120度1,650メートルの地点で、針路を水路に沿う120度に定め、機関を半速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
定針したときB受審人は、船首少し右950メートルばかりのところに離岸中の太賀丸を初認し、その後衝突のおそれのある態勢で接近していたが、同船は自船の通過を待つか又は水路中央に進出しないように操船するものと思い、警告信号を行わず、更に接近するに及んで減速するなどの衝突を避けるための措置をとることなく続航した。
B受審人は、16時01分船首方350メートルばかりのところに水路に直角となった太賀丸を認め、短音5回を吹鳴すると共に機関を中立として進行し、依然、機関を後進にかけるなどして衝突を避けるための措置をとることなく続航して同時02分ごろ同船の船首方を替わそうと左舵をとり惰力で進行中、近距離に迫った太賀丸を認め、ようやく衝突の危険を感じ、短音3回を吹鳴して機関を後進全速力にかけバウスラスタを始動するも及ばず、昭惠丸は、105度を向首して約1ノットの残存速力をもって、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、太賀丸は左舷中央部に凹損を生じ、昭惠丸は船首部に凹損を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、福山港分岐航路内において、離岸操船中の太賀丸が、見張り不十分で、揚錨作業を一時中止して、港奥から出航中の昭惠丸を避けなかったことによって発生したが、昭惠丸が、警告信号を行わず、更に接近するに及んで減速するなどの衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、福山港分岐航路内において離岸操船を行う場合、港奥から出航する昭惠丸を見落とさないよう周囲の見張りを十分行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、揚錨作業などの離岸操船に気を奪われ、見張りを十分行わなかった職務上の過失により、昭惠丸に気付かず、揚錨作業を一時停止して、同船を避けることなく離岸操船を続行して昭惠丸と衝突を招き、同船の船首部及び太賀丸の左舷中央部に凹損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、福山港分岐航路を出航中、船首少し右方に離岸操船中の太賀丸を視認し、その後衝突のおそれのある態勢で接近するのを認めた場合、警告信号を行い、更に接近するに及んで減速するなどの衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、太賀丸が自船の通過を待つか又は水路中央に進出しないように操船するものと思い、警告信号を行わず、更に接近するに及んで減速するなどの衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、太賀丸との衝突を招き、両船に前示のとおり損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
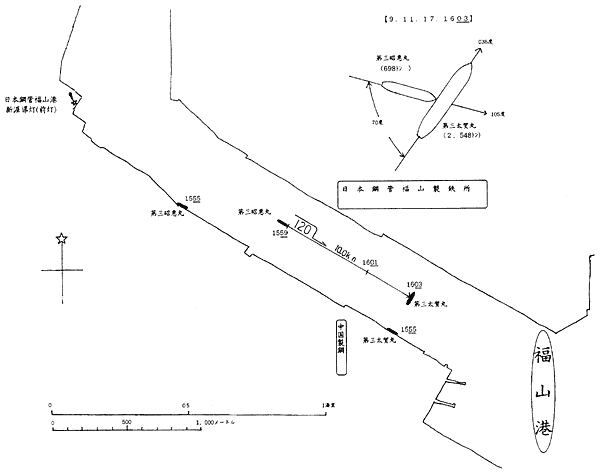 |