 |
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成8年11月11日05時30分
紀伊水道北西部
2 船舶の要目
船種船名
貨物船第六旭丸
総トン数 198トン
全長 57.25メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 661キロワット
船種船名 引船第六十二南海丸
総トン数 96.98トン
全長 24.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 976キロワット
船種船名 台船さかえ2号 台船さかえ5号
全長 26.00メートル
26.00メートル
3 事実の経過
第六旭丸(以下「旭丸」という。)は、専ら鋼材を輸送する船尾船橋型の貨物船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか1人が乗り組み、厚板鋼板628.9トンを載せ、船首2.55メートル船尾3.65メートルの喫水をもって、平成8年11月9日15時20分茨城県鹿島巷を発し、広島県広島港に向かった。
A受審人は、発航後、自身、一等航海士及び無資格のB指定海難関係人の順で、3人による単独4時間交替の船橋当直を行って本州南東岸を西行し、翌10日23時30分潮岬沖合を航過したところで、次直の一等航海士に船橋当直を引き継ぐことにした。
ところで、A受審人は、これまで紀伊水道通航の経験から、鳴門海峡付近においては船舶が輻輳することが考えられる状況で、B指定海難関係人の当直中に同海峡付近に差し掛かることが予想されたが、同人が船橋当直の経験が豊富なので改めて指示するまでもないと思い、双眼鏡やレーダーを活用するなど周囲の見張りを厳重に行うことを申し送るよう、一等航海士に対して指示することなく、漁船が多いときには注意するとともに、同海峡の通峡約40分前になったら船長に報告するようにと告げただけで、自室に退いて休息した。
翌々11日03時15分B指定海難関係人は、和歌山県日ノ御埼南方沖合で昇橋し、一等航海士から厳重な見張りについて特段の引継ぎがないまま単独で船橋当直に就き、03時30分紀伊日ノ御埼灯台から225度(真方位、以下同じ。)2.3海里の地点で、針路を320度に定め、引き続き機関を全速力前進にかけ、法定の灯火を表示し、11.4ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
05時10分B指定海難関係人は、大磯埼灯台から125度8.9海里の地点で、レーダーを3海里から12海里レンジに切り替えたとき、左舷船首10度4海里に十数隻の漁船を探知するとともに、肉眼により黄色の点滅灯などを認め、やがて2そう船引き網漁の漁船群がほぼ停留していることを知り、これらに注目しながら操舵用の椅子に腰を掛けて見張りを続けた。
05時22分B指定海難関係人は、大磯埼灯台から120度6.7海里の地点に達したとき、左舷船首29度1.4海里のところに、第六十二南海丸(以下「南海丸」という。)が引船列であることを表示する白、白、白、緑4灯を視認でき、その後同引船列が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めることができる状況であった。
しかし、B指定海難関係人は、そのころ漁船群が左舷船首23度1.8海里のところから東方に向けて一斉に航走を始めたため、その動きに気をとられ、双眼鏡やレーダーを活用するなど周囲の見張りを厳重に行わず、南海丸引船列の存在にも、その接近にも気付かないで、A受審人に報告できず、速やかに警告信号を行うことも、更に間近に接近したとき右転するなど衝突を避けるための協力動作をとることもできないまま続航した。
こうして、B指定海難関係人は、漁船群が前路を通過して右方に遠ざかっていく様子を見守っていたところ、05時29分右舷船首至近に南海丸の灯火を初めて視認し、漁船群の掲げる灯火模様と異なることに不審を覚え、双眼鏡で前方を確認したところ、南海丸が順に曳航したさかえ5号(以下「5号台船」という。)及びさかえ2号(以下「2号台船」という。)を認め、急ぎ機関を全速力後進としたが及ばず、05時30分大磯埼灯台から114度5.3海里の地点において、旭丸は、3.0ノットの行き脚をもって、原針路のまま、その船首が、2号台船の右舷船首部に後方から68度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、視界は良好であった。
A受審人は、自室で寝ていたところ、機関が後進に切り替わった音で目を覚まして間もなく軽い衝撃を感じ、直ちに昇橋して事後の措置に当たった。
また、南海丸は、専ら台船の曳航業務に従事する鋼製引船で、C受審人及びD指定海難関係人ほか2人が乗り組み、船首1.9メートル船尾2.6メートルの喫水をもって、幅6.4メートル深さ2.0メートルで、鋼材約60トンを載せ、船首尾とも1.0メートルの喫水となった無人の非自航式鋼製台船の5号台船及び2号台船を順に船尾に引いて引船列を構成し、同月11日04時05分徳島県徳島小松島港を発し、大阪港に向けて曳航を開始した。
南海丸引船列は、曳索として、南海丸と5号台船との間に80メートルの、5号台船と2号台船との間に20メートルのそれぞれ直径60ミリメートルのナイロンロープを使用し、南海丸の船尾から2号台船の後端までの長さを152メートルとしていた。
そして、C受審人は、曳航する台船に法定灯火として舷灯及び船尾灯を表示しなければならなかったものの、これらの灯火を表示しないで、5号台船の前部と2号台船の後部の甲板上高さ1.5メートルの箇所に、それぞれ4秒1閃光の白色点滅灯1個を点灯し、また、南海丸には、曳航物件の後端までの距離が200メートルを超えていなかったものの、法定灯火のほかにマスト灯1個を増掲してマスト灯3個を点灯させていた。
発航後、C受審人は、単独で船橋当直に就き、港界付近に至って機関を全速力前進にかけ、兵庫県沼島の北端に向かっていたところ、やがて自発的に昇橋してきた無資格のD指定海難関係人から、当直交替の申し出があったので、07時の朝食までの間を任せることにしたが、同人が船橋当直の経験が豊富なので心配はないものと思い、接近してくる他船を認めたときには速やかに報告するよう指示することなく、他船に注意するようにと告げただけで、自室に退いて休息した。
D指定海難関係人は、当直を引き継いだ直後の、04時40分大磯埼灯台から165度5.9海里の地点で、針路を淡路島と沼島の中間に向く048度に定め、引き続き6.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
05時00分D指定海難関係人は、大磯埼灯台から146度5.3海里の地点に達したとき、右舷船首63度に旭丸の白、紅2灯を初めて視認し、レーダーでその距離が6.0海里弱であることを認め、その動静を見ていたところ、同船の方位変化が少なかったので、同時14分その距離が3.0海里となったとき、同船から離れるつもりで針路を038度に転じた。
05時22分D指定海難関係人は、大磯埼灯台から122度5.3海里の地点に達したとき、旭丸を右舷船首73度1.4海里に見るようになり、このまま進行すると同船と著しく接近する状況であることを認めたが、速やかにC受審人にこのことを報告しなかった。
そして、このときD指定海難関係人は、更に針路を028度に転じたところ、ほぼ右舷正横に同船を見る態勢になったので、これで同船から十分に離れるはずで、著しく接近することを避けることができたものと思い、その後旭丸が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったものの、引き続き同船に対する動静監視を十分に行わず、このことに気付かないで、なおもC受審人に旭丸の接近状況を報告できず、速やかに行き脚を止めるなど同船の進路を避けることができないまま続航した。
05時30分少し前D指定海難関係人は、右舷後方至近に迫った旭丸に気付き、台船との衝突の危険を感じたがどうすることもできず、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
C受審人は、自室で椅子に腰を掛けて仮眠していたところ、船体の頃斜を感じて目を覚まし、続いてD指定海難関係人の「船長」という叫び声を聞き、直ちに昇橋して事後の措置に当たった。
衝突の結果、旭丸は、球場船首左舷側に破口及び船首材に凹損を生じ、2号台船は、右舷前部外板にV字形の破口を生じ、5号台船は、衝突の反動で南海丸球状船首が2号、5号両台船間の曳索の下に入り込んで同索を引っ張ったことにより転覆し、その積荷を流失したが、南海丸引船列は徳島小松島港に引き返し、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、夜間、紀伊水道北西部において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、東行中の南海丸引船列が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る旭丸の進路を避けなかったことによって発生したが、旭丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
南海丸引船列の運航が適切でなかったのは、船長が、無資格の船橋当直者に対し、接近してくる他船を認めたときには速やかに報告するよう指示しなかったことと、同当直者が、旭丸の接近状況を船長に報告しなかったこととによるものである。
旭丸の運航が適切でなかったのは、船長が、船橋当直者に対し、周囲の見張りを厳重に行うことを申し送るよう指示しなかったことと、無資格の船橋当直者が、周囲の見張りを厳重に行わなかったこととによるものである。
(受審人等の所為)
C受審人は、夜間、紀伊水道北西部を東行中、無資格の甲板員に単独の船橋当直を任せる場合、接近してくる他船を認めたときには速やかに報告するよう指示すべき注意義務があった。しかるに、同人は、同甲板員が船橋当直の経験が豊富なので心配はないものと思い、接近してくる他船を認めたときには速やかに報告するよう指示しなかった職務上の過失により、同甲板員から旭丸の接近状況についての報告を受けられずに同船との衝突を招き、旭丸の球状船首左舷側に破口及び船首材に凹損を、2号台船の右舷前部外板にV字形の破口をそれぞれ生じさせ、5号台船を転覆させるに至った。
以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、夜間、潮岬南方沖合において、一等航海士に船橋当直を引き継ぐ場合、無資格の機関長が船橋当直に当たる鳴門海峡付近においては船舶が輻輳することが考えられたから、他船を見落とすことのないよう、双眼鏡やレーダーを活用するなど周囲の見張りを厳重に行うことを申し送るよう指示すべき注意義務があった。しかるに、同人は、同機関長が船橋当直の経験が豊富なので改めて指示するまでもないと思い、一等航海士に対し、双眼鏡やレーダーを活用するなど周囲の見張りを厳重に行うことを申し送るよう指示しなかった職務上の過失により、同機関長が南海丸引船列の存在にも、その接近にも気付かないで進行して2号台船との衝突を招き、旭丸及び2号台船に前示の損傷を生じさせ、5号台船を転覆させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
D指定海難関係人が、夜間、単独の船橋当直に当たり、紀伊水道北西部を東行中、旭丸の接近状況を船長に報告しなかったことは、本件発生の原因となる。
D指定海難関係人に対しては、勧告しない。
B指定海難関係人が、夜間、単独の船橋当直に当たり、紀伊水道北西部を北上中、双眼鏡やレーダーを活用するなど周囲の見張りを厳重に行わなかったことは、本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
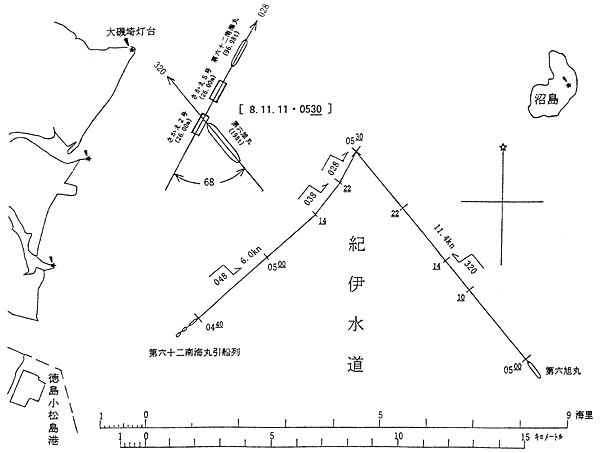 |