 |
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年9月26日05時05分
長崎県松島水道
2 船舶の要目
船種船名 漁船宝生丸 漁船満盛丸
総トン数 4.9トン 1.1トン
全長 14.80メートル
登録長 12.40メートル 7.02メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 200キロワット
漁船法馬力数 30
3 事実の経過
宝生丸は、船体中央からやや後方に操舵室を設けたFRP製漁船で、A受審人と同人の妻の2人が乗り組み、いか一本釣り漁の目的で、船首0.51メートル船尾1.40メートルの喫水をもって、平成10年9月23日15時00分長崎県相浦港浄土ヶ浦を発し、夕刻同県野母埼西方沖合の漁場に至り、夜間操業と同県三重式見港での早朝の水揚げとを繰り返し行ったのち、同月26日03時45分航行中の動力船の灯火のほか操舵室上部に黄色回転灯を点灯し、同漁場を発進して帰途についた。
発進後、A受審人は、機関を全速力前進にかけて17.0ノットの速力とし、操舵室右舷側のいすに腰掛けて手動操舵と肉眼による見張りに当たり、船首が浮上して船首方向に死角を生じた状態で進行した。
05時02分少し前A受審人は、頭島南灯台から250度(真方位、以下同じ。)830メートルの地点で、針路を松島水道のほぼ中央に向首する001度に定め、同一速力で続航し、同時02分同灯台から260度800メートルの地点に達したとき、右舷船首1度1,570メートルのところに、満盛丸の白灯を視認でき、その後、同船にほぼ向首して衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、定針したとき、いすから立ち上がって操舵室の天窓から顔を出し、前方をいちべつして他船が見当たらなかったうえ、レーダー画面にも他船が映っていなかったことから、前路に他船はいないものと思い、いすから立ち上がって操舵室の天窓から顔を出すなどの船首死角を補う見張りを十分に行うことなく、満盛丸に気付かないで、いすに腰掛けたまま進行した。
A受審人は、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、前路でほとんど停留状態の満盛丸に気付かず、同船を避けることができないまま同一針路、同一速力で続航中、05時05分瀬戸港福島外防波堤灯台(以下「外防波堤灯台」という。)から213度670メートルの地点において、宝生丸の船首が満盛丸の左舷船首部にほぼ直角に衝突した。
当時、天候は曇で風はほとんどなく、視界は良好であった。
また、満盛丸は、右舷船首部に揚網機を、後部甲板右舷側に舵輪と機関操縦レバーを備えた操縦台を設け、刺網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人と同人の妻の甲板員Cほか2人が乗り組み、いせえび漁の目的で、船首0.20メートル船尾0.40メートルの喫水をもって、同月26日04時15分同県瀬戸港福島を発し、松島水道南口付近の漁場に向かった。
ところで、操縦台上部に設けたステンレス製マストには、甲板上158センチメートル(以下「センチ」という。)のところにゼニライトL−2型と称する日光弁付きの単一乾電池を電源とする赤色点滅式簡易標識灯(以下「赤色点滅灯」という。)1個を、甲板上141センチのところに蓄電池を電源とする両色灯を、甲板上92センチのところに蓄電池を電源とする30ワットの白色全周灯1個をそれぞれ備え、右舷中央部舷側上に設けたステンレス製支柱には、甲板上93センチのところに蓄電池を電源とする10ワットの白色作業灯1個を取り付けていたが、トロール以外の漁法により漁ろうに従事している船舶が表示しなければならない法定灯火の設備を有していなかった。
04時25分B受審人は、前示漁場に至り、前日夕刻に設置しておいた、長さ約300メートルを1張りと称する刺網2張りを揚収することとし、両色灯以外の赤色前滅灯1個、白色全周灯1個及び白色作業灯1個をそれぞれ点打し、同点滅灯の灯火は間近に接近するまで見えなかったものの、他の灯火は遠方から視認できる状態で、網の設置方向に沿い、西方に向かって揚網を始め、約150メートル揚収したところで、反転して東方に向かって揚網を続けた。
04時55分ごろB受審人は、1張りを揚収ののち、05時00分外防波堤灯台から209度650メートルの地点に達したとき、2張り目の揚収にかかることとし、操縦台後方に腰掛けて手動操舵に当たり、再び反転して船首を西方に向け、機関をかけたままクラッチの嵌脱(かんだつ)を繰り返しながら0.3ノットの前進速力として270度に向首する態勢で進行し、C甲板員を揚網機の前方に配置し、揚がってくる網を懐中電灯で見守らせ、甲板員1人を揚網機の操作に、他の甲板員を網の整理などにそれぞれ当たらせていたところ、同時02分外防波堤灯台から211度650メートルの地点に達したとき、左舷船首88度1,570メートルのところに、松島水道を北上中の宝生丸の黄色回転灯の灯火を初認した。
その後、B受審人は、宝生丸がほぼ自船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、ほとんど停留状態で揚網中の自船を宝生丸が避けるものと思い、同船に対する動静監視を十分に行うことなく、同船から目を離して揚網を続けた。
B受審人は、動静監視を十分に行っていなかったので、避航する気配を見せないで間近に接近した宝生丸に気付かず、機関を使用するなどの同船との衝突を避けるための措置をとることができないまま揚網中、05時05分わずか前左舷船首至近に迫った同船を認め、急ぎ機関を後進にかけたが、効なく、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、宝生丸は、右舷側船首部外板の擦過傷、プロペラの曲損等を生じ、のち修理されたが、満盛丸は、船首部を大破し、宝生丸によって瀬戸港に曳航されたのち廃船とされた。また、C甲板員(昭和7年12月22日生)は、宝生丸力満盛丸を乗り切った際、衝撃で海中に転落し、宝生丸のプロペラに巻き込まれて死亡した。
(原因)
本件衝突は、夜間、長崎県松島水道南口付近において、漁場から帰航中の宝生丸が、見張り不十分で前路でほとんど停留していせえび刺網漁に従事中の満盛丸を避けなかったことによって発生したが、満盛丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、長崎県松島水道南口付近において、漁場から同県相浦港に向けて1人で操船に当たって航行する場合、船首方向に死角を生じて見通しが妨げられる状況であったから、前路の他船を見落とすことのないよう、いすから立ち上がって操舵室の天窓から顔を出すなどの船首死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、頭島南灯台西南西方沖合で針路をほぼ北に定めたとき、いすから立ち上がって操舵室の天窓から顔を出し、前方をいちべつして他船が見当たらなかったうえ、レーダー画面にも他船が映っていなかったことから、前路に他船はいないものと思い、船首死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路でほとんど停留していせえび刺網漁に従事中の満盛丸に気付かず、同船を避けることができないまま進行して衝突を招き、宝生丸の右舷側船首部外板の擦過傷、プロペラの曲損等を生じさせ、満盛丸の船首部を大破して廃船とさせ、同船の甲板員を死亡させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B受審人は、夜間、長崎県松島水道南口付近において、ほとんど停留していせえび刺網漁に従事中、左舷正横方に北上中の宝生丸の黄色回転灯の灯火を認めた場合、同船と衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、ほとんど停留状態で揚網中の自船を宝生丸が避けるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、避航する気配を見せないで間近に接近した宝生丸に気付かず、揚網を続けていて同船との衝突を避けるための措置をとることができないで衝突を招き、前示の損傷と同人の妻を死亡させるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
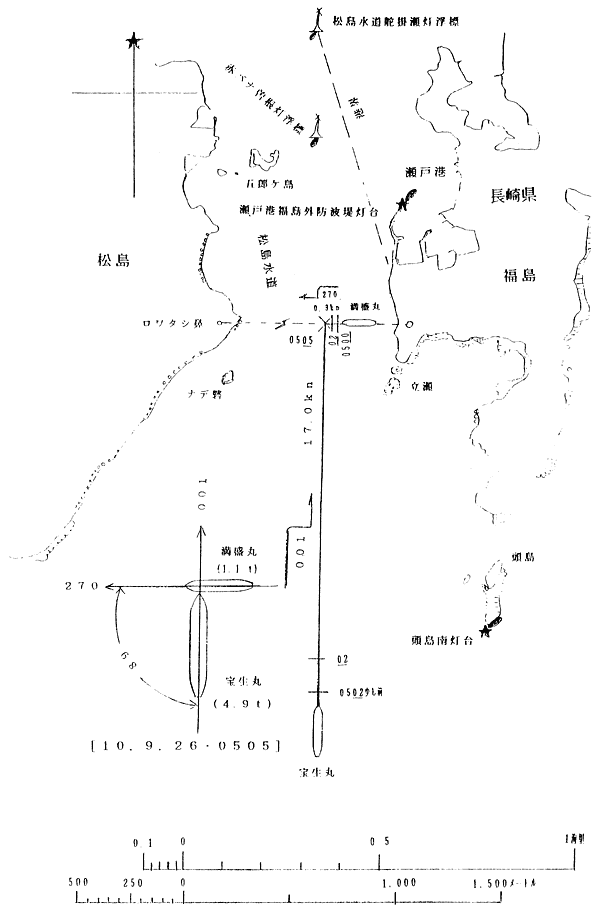 |