 |
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年8月21日00時30分
北海道釧路港南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船第八十一熊野丸
貨物船パックデューク
総トン数 184トン
15,822トン
全長 43.21メートル
登録長 162.43メートル
機関の種類
ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 1,470キロワット
11,550キロワット
3 事実の経過
第八十一熊野丸(以下「熊野丸」という。)は、さんま棒受網漁等に従事する中央船橋型の鋼製漁船で、A指定海難関係人及び船長B(四級海技士(航海)免状受有)ほか15人が乗り組み、さんま漁の解禁とともに操業の目的で、船首1.8メートル船尾4.8メートルの喫水をもって、平成9年8月20日12時00釧路港を発し、漁場に向かった。
14時50分熊野丸は、釧路港南西方沖合40海里ばかりの漁場に至り、操業の準備とともに付近海域の魚群探索を行ったものの、魚影がなかったので、漁場を変えることとし、16時ごろ厚岸湾沖合に向けて移動を開始した。そして、移動途中の20時ごろから霧模様となり、更に21時ごろ厚岸湾南方沖合30海里ばかりの漁場に達したころには霧となっていたが、視界制限状態の中で第1回目の操業を開始し、その後移動を繰り返して操業を続け、翌21日00時10分厚岸灯台から171度(真方位、以下同じ。)30.0海里の地点において、第4回目の操業を終え、4回の操業でさんま約12トンを獲て次の操業のため魚群探索を開始した。
ところで、そのころ釧路港から厚岸湾にかけての沖合には、大小多数のさんま漁船が出漁する漁場となっていて、特に厚岸灯台の南方沖合30海里ばかりのところを東端として西南西方向に伸びる潮目に沿った6海里ばかりの範囲は70隻を超えるさんま漁船が密集する海域(以下「漁船密集海域」という。)となっていた。
熊野丸では、航海甲板の操舵室のほか、その上方のコンパス甲板(以下「上部船橋」という。)でも操船ができるようになっており、天井部分にオーニングが施され、周囲を腰の高さまで囲いが設けられた上部船橋にはリモコン操舵装置、主機遠隔操縦装置、GPSプロッター、魚群探知機や操舵室に設置されたレーダーのモニターが置かれていて、さんま棒受網による操業時は主として同船橋を使用していた。そして、通常、魚群探索から投網するまでの間、A指定海難関係人が上部船橋のやや左舷寄りの主機遠隔操縦装置の後方で操業指揮を執り、両舷側にそれぞれ1名ずつ配置されたライト係が探照灯でさんまの探索と接近する他船への注意喚起を担当する一方、B船長ほか3人の乗組員が操舵、見張りとソナー、魚群探知機による魚群探索を担当し、視界制限状態においては、主にB船長が同船橋右舷寄りのレーダーのモニターでレーダー監視に当たることとしていた。
B船長は、第4回目の操業を終え、上甲板から上部船橋に戻ったとき、霧のため視界が著しく制限され視程200メートルとなっていたが、視界制限状態における音響信号(以下「霧中信号」という。)を行うことなく、昇橋して間もなく自らが運航の指揮をとらずに傾斜調整のため燃料油のタンク間移送の際に空気管から溢れ出た燃料油の拭き取りなどの後始末をするため再び上甲板に赴いた。
A指定海難関係人は、上部船橋を離れようとしていたB船長に対し、操業中の運航の安全確保のため同船橋にとどまって運航の指揮に当たることも霧中信号を行うよう要請することもなく、甲板員をレーダー監視に当たらせ、4.5ノットばかりの平均速力で針路を適宜にとって魚群探索を行い、00時20分漁船密集海域のほぼ東端の、厚岸灯台から172度30.0海里の地点に達したとき、魚群の反応があったので、機関を中立とし、航行中の動力船が表示する所定の灯火のほか、両舷のほぼ全ての集魚灯及び4個の探照灯を点灯して漂泊を開始した。
00時21分少し過ぎA指定海難関係人は、330度に向首させてさんまを集めていたとき、左舷正横前2度2海里のところにパックデューク(以下「パ号」という。)が存在し、その後同船と著しく接近することを避けることができない状況となった。
しかし、同指定海難関係人は、レーダー監視中の甲板員が漁船群の映像の中に紛れていたパ号の映像を識別することができず、同時28分半ようやく同甲板員が左舷正横0.3海里に同船の映像を認めたものの、同業船と思って同指定海難関係人へ報告がなされなかったことから、そのことに気付かず、依然霧中信号を行わずに漂泊中、同時30分わずか前左舷正横至近に同船の船首を認め、右舵を一杯にとって機関を全速力前進としたが、効なく、00時30分熊野丸は、前示の漂泊地点において、その左舷側中央部にパ号の船首が前方から88度の角度で衝突した。
当時、天候は霧で風はほとんどなく、視程は200メートルであった。
また、パ号は、R株式会社が運航する船尾船橋型の鋼製貨物船で、船長C及び二等航海士D(国籍ミャンマー連邦)ほか23人が乗り組み、空倉で船首3.35メートル船尾6.26メートルの喫水をもって、同8月18日07時54分(日本標準時、以下同じ。)大韓民国釜山港を発し、津軽海峡経由でアメリカ合衆国オークランド港に向かった。
翌々20日18時10分昇橋中のC船長は、襟裳岬灯台から180度10.3海里の地点で、針路を062度に定め、機関を全速力前進にかけて13.5ノットの対地速力とし、19時ごろ船橋当直を一等航海士に任せて降橋したあと、20時00分船内の時計を日本標準時より1時間進ませた。
23時00分D二等航海士は、操舵手1名とともに船橋当直に就き、翌21日00時00分厚岸灯台から183度329海里の地点に達したとき、霧となって視界が著しく制限される状態となり、そのころ前路近くから7海里ばかり前方にまで達する範囲に熊野丸を含む70隻以上の漁船が密集しているのをレーダー映像で認め得る状況にあったが、レーダーによる見張りを十分に行っていなかったので、それを認めず、速やかに右転するなどして漁船密集海域を避けて航行する措置をとることなく、霧中信号を行うことも減速して安全な速力とすることもせずに全速力のまま13.3ノットの対地速力で所定の灯火を掲げて進行した。
D二等航海士は、漁船密集海域に入ったのち、同時21分厚岸灯台から180度31.9海里の地点に達し、漂泊中のさんま漁船第三康正丸の北側すぐ近くを通過したころ正船首2海里のところに漂泊を開始した直後の熊野丸が存在し、その後同船と著しく接近することを避けることができない状況となったが、依然レーダーによる見張りを不十分としていてこのことに気付かず、その速力を針路を保つことのできる最小限度の速力に減じず、また、必要に応じて行きあしを止めないまま、霧中信号を行わずに全速方で続航中、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
パ号は、衝突後そのまま目的地に向け航行を続けていたところ、同日06時05分根室半島南東方沖合において釧路海上保安部の要請により停船し、球状船首部に損傷があるのを確認したのち、同保安部の指示により釧路港に向かった。
衝突の結果、熊野丸は左舷側中央部外板に楔形の大破口を生じ、船内に浸水してのち沈没し、パ号は球状船首左舷側に破口を生じ、釧路港で仮修理したのち本修理された。また、熊野丸の乗組員のうち、衝突の際の大傾斜で海中に投げ出された機関員E(昭和18年2月18日生)が溺死したほか、B船長(昭和16年4月19日生)及び甲板員F(昭和20年1月1日生)が行方不明となり、のち死亡と認定され、残された乗組員全員が膨張式救命筏に乗り移って間もなく、衝突音を聞いて近寄ってきた同業船に救助されたが一等機関士Gが全治1ケ月の入院加療を要する右第12肋骨骨折、腰部及び右大腿挫傷などを負ったほか、13人が胸部、背部、臀部、下肢、膝部などに挫傷を負った。
(原因に対する考察)
本件衝突は、夜間、多数の漁船が操業する釧路港南東方沖合において霧のため視界が著しく制限された状態のもとで発生したものであるが、その原因について考察する。
パ号が00時00分視界が制限される状態になったころ、前路近くから7海里ばかり前方にかけての海域は漁船が密集し、その東端付近に操業中の熊野丸が存在していたことはすでに認定したとおりである。
パ号が漁船密集海域に入り込んだことにより、熊野丸を含む複数の漁船と衝突するおそれが生じ、若しくは著しく接近することとなることは必然であり、更に同海域の中では衝突回避のための動作に著しく制約や困難が伴うことを併せ考えれば、船員の常務として同海域に極力入り込まないようにすべきであり、当時パ号が同海域に入らなければならなかった特段の事情も認められないことから、同船が同海域を避けて航行する措置をとらなかったことは本件発生の原因をなすものである。
パ号は、漁船密集海域に入ったのち、00時21分正船首方で漂泊中の熊野丸が2海里となり、その後同船と著しく接近することを避けることができない状況にあったが、その際海上衝突予防法第19条第6項に規定する措置としてその速力を針路を保つことのできる最小限度の速力に減じ、必要に応じて停止すべきであったところ、それらの措置をとらなかったことは本件発生の原因をなすものである。
パ号においてこれらの措置がいずれもとられなかったのは、レーダーによる見張りが十分に行われなかったことによるものと認められ同船がレーダーによる見張りを不十分としていたことは本件発生の原因をなすものである。
一方、熊野丸においても、パ号の映像が漁船群の映像の中に紛れ、やや識別しにくく、レーダーの性能面から映像上同業船との区別が付かない事情にあったとはいえ、レーダーによる見張りを十分に行っていれば、自船の正横より前方にあるパ号と著しく接近することを避けることができない状況となったことを早期に認識できたものと認められる。熊野丸はパ号の接近に0.3海里になるまで気付いていないことから、レーダーによる見張りが必ずしも十分でなかったものと認められるが、熊野丸は漂泊中であり、その状況を早い段階で知ったとしても、前示の規定に基づいて新たな動作をとる余地はないことから、そのことは本件発生の原因とはならない。
また、パ号は、視程200メートルの視界制限状態下を全速力の13.3ノットの対地速力で航行し、同速力のまま熊野丸と衝突していることはすでに認定したとおりであり、熊野丸の外板に大破口を生じさせ、同船を沈没にまで至らしめる重大な結果を招いたことはパ号の過大な速力での航行によるものと認められることから、同船が安全な速力としなかったことは本件発生の原因をなすものである。
更に、熊野丸及びパ号の両船共霧中信号を行っていなかったが、熊野丸の汽笛は、音響言号設備の技術基準により可聴距離1海里以上であり、同船が霧中信号を行っていれば、パ号側の当時の当直模様については定かではないものの、衝突回避のために有効な措置をとり得る時期にパ号側が聴取できた可能性は十分に考えられるところであり、熊野丸が霧中信号を行っていなかったことは本件発生の原因をなすものである。
また、パ号が霧中信号を行っていれば、熊野丸側ではその音色などの違いから同業船とは異なる大型船の接近を早期に知り、船の向きを変えて船横方向から衝突されるのを回避するなど被害を最小限に止める措置をとることができたものと認められることから、パ号が霧中信号を行っていなかったことは本件発生の原因をなすものである。
視界制限状態に伴う運航保安上の責務は、漁船においても操業中を含め船長が負うものであって漁労長は船長を補佐する立場であり、船長が霧中信号を行わなかったこと及び漁労長が船長に対して霧中信号を行うなどの運航の安全確保のための措置をとるよう要請しなかったことは、熊野丸の運航が適切でなかったことの船内要因をなすものである。
(原因)
本件衝突は、夜間、霧のため視界が著しく制限され、多数の漁船が操業する釧路港南東方沖合において、パ号が、レーダーによる見張りが不十分で、密集して操業中の漁船群を避けて航行する措置をとらなかったばかりか、霧中信号を行わなかったうえ、安全な速力とせず、熊野丸と著しく接近することを避けることができない状況となった際、その速力を針路を保っことのできる最小限度の速力に減じず、必要に応じて停止しなかったことによって発生したが、熊野丸が、漂泊中、霧中信号を行わなかったことも一因をなすものである。
熊野丸の運航が適切でなかったのは、船長が、霧中信号を行わなかったことと、漁労長が、船長に対して運航の安全確保のための措置をとるよう要請しなかったこととによるものである。
(指定海難関係人の所為)
A指定海難関係人が、霧のため視界が著しく制限された釧路港南東方沖合において操業する際、船長に対して霧中信号を行うなどの運航の安全確保のための措置をとるよう要請しなかったことは本件発生の原因となる。
A指定海難関係人に対しては、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
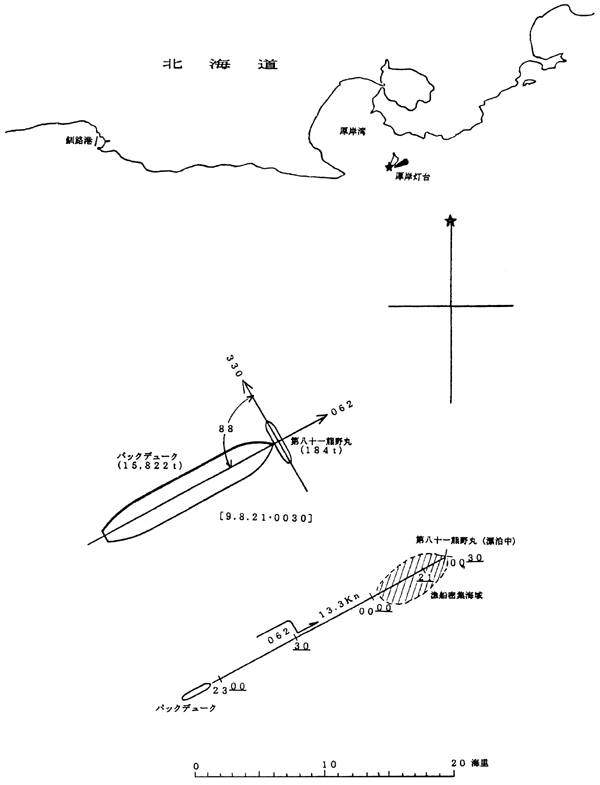 |