 |
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年11月4日03時40分
大分県保戸島化東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 引船若潮
はしけ旭栄3号
総トン数 492.41トン
全長 51.90メートル 87.90メートル
幅
23.80メートル
深さ 5.50メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力
3,383キロワット
船種船名 漁船第六十八新栄丸
総トン数 17トン
全長
22.90メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 160
3 事実の経過
若潮は、2基2軸の可変ピッチプロペラを装備した鋼製引船で、A受審人ほか5人が乗り組み、グリーンサンド7,000トンを積載して船首3.7メートル船尾5.2メートルの喫水となった無人のはしけ旭栄3号(以下「旭栄」という。)船尾に曳航し、船首3.1メートル船尾4.7メートルの喫水をもって、平成9年11月3日16時20分宮崎県細島港を発し、山口県徳山下松港に向かった。
ところで、A受審人は、旭栄の船首部右舷側の甲板上には長さ約13.9メートル幅約4.3メートルのランプウェイが設置されていることから、後方の見通しの妨げとならないよう、ランプウェイを約12度の仰角で船体中心線から右舷方約40度方向に突き出して固定し、旭栄を曳航していた。
A受審人は、港外に出たところで、曳航索の長さを420メートルに調整し、旭栄の長さ50メートルの引船列と併せ、若潮の船尾から旭栄の船尾までの距離が約560メートルの引船列として日向灘を北上し、日没となったころ、若潮に法定の灯火を表示し、旭栄には舷灯及び船尾灯を掲げたほか、甲板上の四隅に取り付けた乾電池式の簡易標識灯を点灯し、18時ごろ二等航海士に当直を引き継ぎ降橋した。
翌4日00時00分A受審人は、前直者と交替して単独で船橋当直に就き、同時11分鶴御灯台から066度(真方位、以下同じ。)3.2海里の地点に達したとき、針路を338度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、折からの南東流に抗して3.2ノットの対地速力で進行した。
03時00分A受審人は、高甲岩灯台から118度2.6海里の地点に差し掛かったころ、逆潮流が弱まり、4.4ノットの対地速力となって続航し、同時20分同灯台から095度1.8海里の地点に達したとき、右舷船首37度1.6海里のところに第六十八新栄丸(以下「新栄丸」という。)の白、紅2灯を初めて視認したが、その方位が右方に少しずう変わっていたことから、同船が旭栄の船尾を替わるものと思い、新栄丸の動静監視を十分に行わなかったので、その後、同船が前路を左方に横切り旭栄と衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、自船が引船列であることを考慮して、早期に新栄丸の進路を避けることなく進行した。
A受審人は、03時35分新栄丸を右舷正横450メートルに見て航過したとき、同船が自船と旭栄との間に向首してくるのを認め、手動操舵に切り替え、曳航索の上を通過させようと、翼角を0度として中立回転とし、同索を弛ませたが効なく、03時40分高甲岩灯台から049度1.7海里の地点において、旭栄は、原針路のまま、2.0ノットの対地速力となったとき、そのランプウェイの中央部に、新栄丸の操舵室左舷側が前方から83度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の南風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、付近海域に約0.8ノットの南東流があった。
また、新栄丸は、大中型まき網漁業船団の灯船に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.2メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、同月3日16時30分大分県松浦漁港を発し、芹埼南方3海里の漁場に向かった。
B受審人は、日没になったころ、法定の灯火のほか、操舵室全面の両耐側に作業灯各1個及び後部マストに赤色の標識灯2個を点灯し、18時ごろ同漁場に至って船団の網船とともに操業を開始したが、漁獲量が少なかったので漁場を移動することにし、23時30分同漁場を離れ、魚群の探索をしながら北上して保戸島北東方沖合5海里に至り、1時間ばかりその付近の探索を行った。
翌4日03時00分B受審人は、高甲岩灯台から051度3.9海里の地点で、針路を241度に定めて自動操舵とし、機関を微速力前進にかけ、折からの南東流によって9度左方に圧流されながら3.1ノットの対地速力で進行し、魚群の探索に当たっていたところ、魚影の反応がなくて気力緩み、眠気を催すようになったが、付近は船舶が輻輳(ふくそう)する海域で頻繁に操舵を行うことになるから、まさか居眠りすることはないと思い、いすから立ち上がって身体を動かすなり、外気に当たるなどして居眠り運航の防止措置をとることなく、いすに腰を掛けたまま魚群探知器を見ているうち、いつしか居眠りに陥った。
こうして、B受審人は、03時20分高甲岩灯台から052度2.8海里の地点に達したとき、左舷船首46度1.6海里に旭栄を引いた若潮の白、白、白、白、緑5灯及び旭栄の灯火を視認することができ、その後、若潮引船列がその方位が明確に変わらず前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近したが、居眠りに陥っていてこのことに気付かないまま、警告信号を行わず、やがて間近に接近しても衝突を避けるための協力動作をとることができないまま続航中、新栄丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、若潮及び旭栄は損傷がなく、新栄丸は操舵室屋根及び同室左舷側壁等に損傷を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件衝突は、夜間、大分県保戸島北東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、若潮引舵列が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る新栄丸の進路を避けなかったことによって発生したが、新栄丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、はしけを曳航して大分県保戸島北東方沖合を北上中、前路を左方に横切る新栄丸の灯火を視認した場合、衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、新栄丸が旭栄の船尾を替わるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、新栄丸が旭栄と衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、新栄丸の進路を避けることなく進行して同船との衝突を招き、新栄丸の操舵室屋根及び同室左舷側壁等に損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項3号を適用して同人をを戒告する。
B受審人は、夜間、単独で操舵と見張りに当たり、魚群の探索を行って大分県保戸島北凍方沖を西行中、眠気を催した場合、いすから立ち上がって身体を動かすなり、外気に当たるなどして居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、付近は船舶が輻輳する海域で頻繁に操舵を行うことになるから、まさ居眠りすることはないと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠り運航となり、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもできないまま進行して旭栄との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
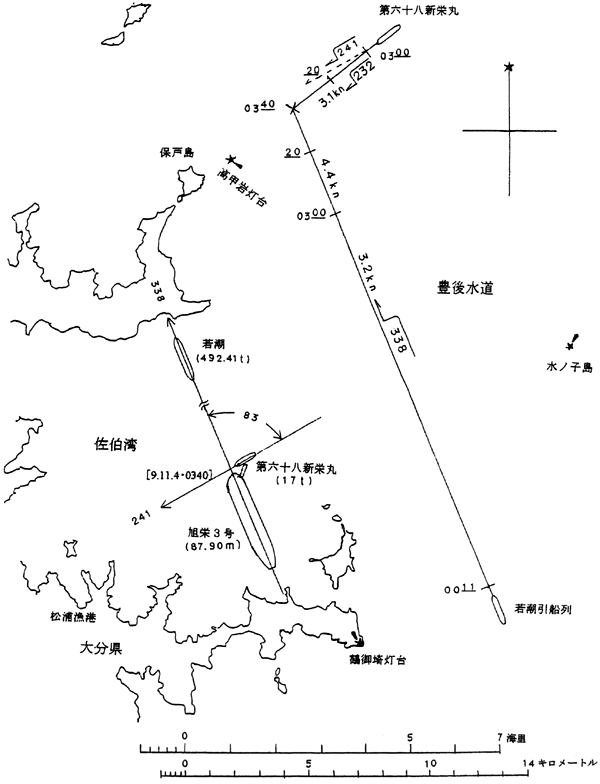 |