 |
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年12月10日08時50分
北海道函館港
2 船舶の要目
船種船名 引船第五新徳丸
漁船昭栄丸
総トン数 168.21トン 9.7トン
全長 25.00メートル
登録長
14.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関
出力 1,206キロワット
漁船法馬力数 120
船種船名
漁船第16漁宝丸
総トン数 6.6トン
登録長 11.98メートル
機関の種類
ディーゼル機関
漁船法馬力数 90
3 事実の経過
第五新徳丸(以下「新徳丸」という。)は、北海道函館港から台船、起重機船などを周辺の港湾に向け曳航している2機2軸の鋼製引船で、推進器として可変ピッチプロペラ2個を有し、A受審人がほか2人と乗り組み、平成9年12月6日朝から曳航作業に従事したのち独航で帰航し、同日17時ごろ船首2.20メートル船尾3.80メートルの喫水をもって、函館港西ふ頭G岸壁に、その基部から160メートルのところに接岸し、船首尾索各2本と船首スプリング1本をとって入り船左舷付けに係留し、翌7日から北西の季節風が強まったので、そのまま停泊していた。
ところで西ふ頭は、函館港第1区北西部の陸岸から北東方に突出する埋立地で、その北西側は基部から037度(真方位、以下同じ。)の方向に延びる長さ約230メートルのG岸壁と、その北東端から095度の方向に屈曲する長さ約150メートルのF岸壁が設けられ、両岸壁の西方及び北方沖合は函館ドック岸壁に囲まれて東方に開く幅約230メートルの水路となっていた。
A受審人は、同月9日夕刻、風波がおさまってきたので、翌朝港内に停泊中の起重機船を白神岬北方の木古内漁港向け曳航する予定として帰宅し、翌10日08時00分帰船したところ、自船の右舷側に第16漁宝丸(以下漁宝丸という。)が、その僚船1隻を外側に並列に係留し、G岸壁には、新徳丸の船首方に約3メートル離れて4隻のいか釣り漁船が並列に入り船付けで係留し、船尾方にば約6メートル離れて昭栄丸が出船右舷付けに係留しているのを認め、漁宝丸とその僚船を移動させたのち船首を岸壁に付け回して後進で離岸することとし、僚船の船長を探したが、帰宅していたので、08時40分漁宝丸の船長に対し、僚船を横抱きしたまま自船を離れて昭栄丸の船首方のG岸壁に着岸するよう依頼したのち同時45分昇橋し、離岸配置に就いた。
A受審人は、配置に就いたとき、両舷機をプロペラの翼角0度のまま起動して機関回転数毎分380とし、08時47分船首スプリング1本を残して他の係留索を解き放し、漁宝丸が移動するのを待っていたところ、北西の風により自船が沖合から横風を受ける状況であることを知ったが、自船の船尾が風に立つまで船首を岸壁に付け回して離岸するなどの適切な操船について考慮しなかった。
A受審人は、08時48分半昭栄丸の船首方の岸壁に漁宝丸が僚船を内側にして出船並列に接岸したのを確認し、右舷機プロペラの翼角を前進5度とし、左舵30度をとって船首を岸壁に付け回し、08時49分半自船の船尾方向が岸壁と35度の角度になったとき、船尾を風に立てることなく、船首スプリングを解き放し、次いで舵中央、左舷機プロペラの翼角を後進10度として002度の方向に約2ノットの対地速力で後進したところ、船尾が急速に風下に落とされて左舷側船尾が後方の昭栄丸の船尾部左舷側に接近するのを認め、急ぎ両舷機プロペラの翼魚を0度としたが間に合わず、08時50分函館港西ふ頭G岸壁基部から036度185メートルの地点において、新徳丸の左舷側後部が約2ノットの後進惰力で昭栄丸の左舷側後部に並行に衝突してこれを擦過し、続いて新徳丸の左舷船尾が、昭栄丸の船首方の岸壁に並列係留していた漁宝丸の左舷船尾に衝突した。
当時、天候は曇で風力4の北西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、視界は良好であった。
また、昭栄丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、Bが船長として甲板員1人と乗り組み、同月9日早朝、函館港沖合漁場から帰港し、船首0.50メートル船尾2.50メートルの喫水をもって、新徳丸の船尾と自船の船尾とを約6メートル離してG岸壁に出船右舷付けとし、船首及び船尾から各2本の係留索をG岸壁のビットにとって出漁待機した。
B船長は、翌10日朝、操舵室後部のベッドに横になって休息中、08時45分離岸配置に就いた新徳丸の機関音に気付いて操舵室左舷側通路に出て同船の離岸操船模様を見ていたところ、同時50分少し前、同船の船尾部左舷が自船の左舷側後部に接近するのを認めたが、何をする暇もなく前示のとおり衝突した。
一方、漁宝丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、Cが船長として1人で乗り組み、同月9日早朝、函館港沖合漁場から帰港し、船首0.30メートル船尾1.50メートルの喫水をもって、新徳丸の右舷側に左舷付けに係留して荒天待機していたところ、間もなく自船の右舷側に僚船1隻がその左舷側を接舷し、その船首及び船尾索各1本を漁宝丸の船首及び船尾たつに取って並列に係留した。
翌10日08時40分C船長は、A受審人から自船と右舷側の僚船とを移動してほしい旨の依頼を受け、同時45分僚船を横抱きしたまま新徳丸の右舷側を離れ同時48分半昭栄丸の船首と僚船の船尾とを約5メートル離してG岸壁に出船並列に着岸し、同時49分僚船の船首及び船尾索各1本を岸壁のビットに取って係留作業を終えた。
その後C船長は、自船の船尾甲板上で新徳丸の離岸操船模様を見ていたところ08時50分新徳丸が昭栄丸に衝突し、続いて新徳丸の左舷船尾が自船の左舷船尾に迫ったが何をする暇もなく前示のとおり衝突した。
衝突の結果、新徳丸に損傷はなかったが、昭栄丸は、左舷側外板に擦過傷を生じ、左舷側後部いか釣り機1台とその付属機器を破損し、漁宝丸は、左舷船尾いか釣り機1台とその付属機器を破損したが、のち損傷部は修理された。
(原因)
本件衝突は、新徳丸が、北海道函館港西ふ頭G岸壁において、沖合から横風を受ける状況で船首を岸壁に付け回して後進で離摩する際、操船が不適切で、船尾方に係留中の昭栄丸及び漁宝丸に向けて後進したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、北梅道函館港西ふ頭G岸壁において、沖合から横風を受ける状況で船首を岸壁に付け回して後進で離岸する場合、自船の船尾が風に立つまで付け回して離岸するなどの適切な操船を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、離岸後に両舷機プロペラを使用すれば船尾が風下に落されることはあるまいと思い、船尾が風に立つまで付け回して離岸するなどの適切な操船を行わなかった職務上の過失により、船尾方に係留中の昭栄丸及び漁宝丸に向け後進して衝突を招き、昭栄丸の左舷側外板に擦過傷を生じさせ、左舷側後部いか釣り機1台とその付属機器を破損させ、漁宝丸の左舷船尾いか釣り機1台とその付属機器を破損させるに至った。
参考図
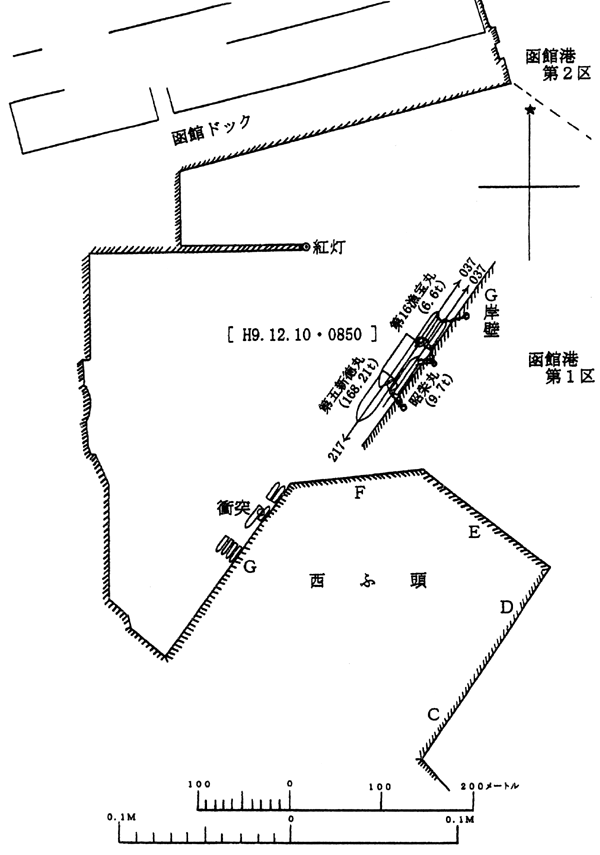 |