 |
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年10月24日10時30分
九州北岸倉良瀬戸
2 船舶の要目
船種船名 油送船白運丸
貨物船明安丸
総トン数 198トン 191トン
全長 39.99メートル 55.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力
588キロワット 514キロワット
3 事実の経過
白運丸は、船尾船橋型の鋼製油送船で、A受審人ほか2人が乗り組み、軽油500キロリットルを載せ、船首2.6メートル船尾3.8メートルの喫水をもって、平成9年10月23日13時00分香川県坂出港を発し、長崎県長崎港に向かった。
A受審人は、船橋当直を自らと甲板長の2人による単独4時間の2直制とし、翌24日06時30分関門航路西山ふ頭沖で昇橋して船橋当直に就き、九州北岸沿いに西行し、08時ごろ地ノ島北方に差し掛かったとき、それまで2.5海里ばかりあった視界が霧により急に悪化し、視程が100メートルになったことから、倉良瀬灯台の東方0.5海里の地点で、機関を中立回転として漂泊した。
09時30分A受審人は、視程が900メートルまで回復したので目的地に向け航行を再開し、同時36分倉良瀬灯台から146度(真方位、以下同じ。)560メートルの地点において、針路を212度に定め、機関を微速力前進にかけ、3.8ノットの対地速力で、航行中の動力船であることを示す灯火を掲げ、手動操舵により進行した。
A受審人は、定針後、視界が再び悪化して視程が70メートルに狭められるようになったが、霧中信号を行わず、在橋していた機関長をレーダーの見張りにあて、オノマ瀬灯浮標を右舷方に600メートル離して航過したのち、10時03分倉良瀬灯台から203度1.9海里の地点で、針路を228度に転じて続航した。
10時22分半A受審人は、右舷船首28度1.5海里のところに東行中の明安丸のレーダー映像を初めて認め、同時24分半同映像がほぼ同方位のまま1.0海里となり、同船と著しく接近することを避けることができない状況となったことを知ったがこのままの針路でも接近したときに左転すれば替わせるものと思い、行きあしを止めることなく、操舵にあたりながらときどきレーダーの画面を見て進行した。
A受審人は、10時29分少し過ぎ明安丸の映像が消えて映らなくなったことから、左舵20度を取って左転を始め、同船を見付けようとして前方を見張るうち、同時30分少し前右舷前方至近に明安丸を視認し、機関を全速力後進にかけたが効なく、10時30分倉良瀬灯台から215度3.5海里の地点において、白運丸は、船首が201度を向いて原速力のまま、その右舷中央部に明安丸の船首が前方から70度の角度で衝突した。
当時、天候は霧で風はほとんどなく、潮候は低潮時で、視程は約70メートルであった。
また、明安丸は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、B受審人ほか2人が乗り組み、空倉のまま、船首1.4メートル船尾2.9メートルの喫水をもって、同月24日07時05分長崎県久喜漁港を発し、関門港若松区に向かった。
B受審人は、発航時から引き続き船橋当直に就き、09時30分ごろ栗ノ上礁北北西方沖合3海里ばかりの地点で、機関長Cに当直を引き継ぎ、船橋内後部の畳に座って休息した。
C機関長は、09時50分栗ノ上礁灯標から029度4.3海里の地点において、針路を倉良瀬戸西口に向く086度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で進行したところ、10時10分ごろ霧により視界が急に悪化して視程が900メートルになったのを認め、B受審人に視界制限状態になったことを報告した。
報告を受けたB受審人は、操船の指揮を執り、C機関長を手動操舵にあて、航行中の動力船であることを示す灯火を掲げ、レーダーの監視にあたっていたところ、10時15分左舷船首10度3.1海里のところに南下中の白運丸のレーダー映像を初めて認め、そのころ視界が更に悪化して視程が70メートルに狭められたが、霧中信号を行うことも、安全な速力にすることもなく続航し、同時24分半倉良瀬灯台から224度4.0海里の地点に達したとき、白運丸の映像がほぼ同方位のまま1.0海里となり、同船と著しく接近することを避けることができない状況となったことを知ったが、少し右転すれば左舷を対し航過できるものと思い、針路を保つことができる最小限度の速力に減じ、必要に応じて行きあしを止めることなく、針路を091度に転じて進行した。
10時26分半B受審人は、白運丸の映像が左舷船首14度1,100メートルに接近し、不安を感じたものの、機関を半速力前進の7.0ノットに減じたのみで続航し、同時30分少し前船首至近に同船を視認し、機関を全速力後進にかけたが効なく、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、白運丸は、右舷側中央部外板に破口を生じて積荷の軽油の一部が流出し、明安丸は、球状船首部に破口及び亀裂を伴う曲損を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、白運丸及び明安丸の両船が、霧による視界制限状態の倉良瀬戸を航行中、南下する白運丸が、霧中信号を行わず、レーダーにより前路に探知した明安丸と著しく接近することを避けることができない状況となった際、行きあしを止めなかったことと、東行する明安丸が、霧中信号を行うことも安全な速力とすることもせず、レーダーにより前路に探知した白運丸と著しく接近することを避けることができない状況となった際、針路を保つことができる最少限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めなかったこととによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、霧による視界制限状態の倉良瀬戸を南下中、レーダーで前路に探知した明安丸と著しく接近することを避けることができない状況となったことを知った場合、行きあしを止めるべき注意義務があった。しかるに、同人は、このままの針路でも接近したときに左転すれば替わせるものと思い、行きあしを止めなかった職務上の過失により、明安丸との衝突を招き、白運丸の右舷側中央部外板に破口を生じさるとともに積荷の軽油を流出させ、明安丸の球状船首部に破口等を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、霧による視界制限状態の倉良瀬戸を東行中、レーダーで前路に探知した明安丸と著しく接近することを避けることができない状況となったことを知った場合、針路を保つことができる最小限度の速力に減じ、必要に応じて行きあしを止めるべき注意義務があった。しかるに、同人は、少し右転すれば左舷を対し航過できるものと思い、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めなかった職務上の過失により、白運丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
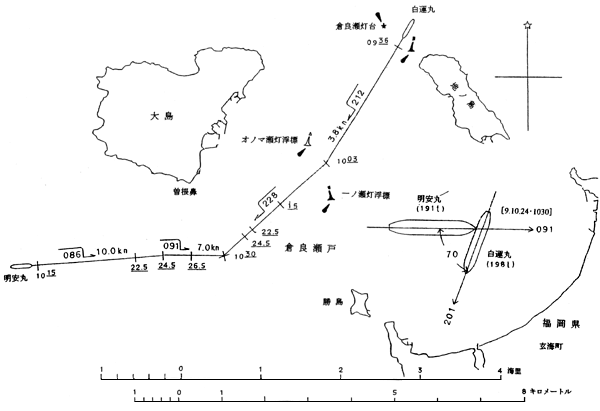 |