 |
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年4月23日12時18分
下関南東水道
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第八勇進丸
貨物船シリウス
総トン数 491トン 1,301トン
登録長 64.88メートル 65.80メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力
1,323キロワット 1,471キロワット
3 事実の経過
第八勇進丸(以下「勇進丸」という。)は、専ら広島県を中心に瀬戸内海西部で海砂の運搬に従事する船尾船橋型砂利採取運搬船で、バウ・スラスターを装備し、A受審人ほか4人が乗り組み、海砂沖積みのため空倉のまま、船首1.4メートル船尾3.1メートルの喫水をもって、平成10年4月23日11時40分幅岡県苅田港沖の埋立地を発し、関門港西口六連島沖合の錨地に向かった。
A受審人は、抜錨後も1人で操舵操船にあたり、昼食のため一時一等機関士と交代して降橋し、食事後再度昇橋して航海当直を継続し、一等機関士も関門航路通航に備えて引き続き在橋させて補佐にあて、12時06分部埼灯台から144度(真方位、以下同じ。)3.5海里の地点に達し、関門港新門司区北東3.5海里沖合の2個の特殊浮標の間を抜けたとき、針路を341度に定めて自動操舵とし、レーダーで部埼南東沖合に錨泊していた10隻ばかりを左舷側に確認してその周辺部を、機関を全速力前進にかけて10.0ノットの対地速力で進行した。
12時15分A受審人は、部埼灯台から133度3,930メートルの地点において、左舷船首16度ほぼ1海里に下関南東水道推薦航路線に沿って南東進しているシリウスを初めて視認し、動静監視を続けているうち、同時15分半同船との方位が殆(ほとん)どを変わらずに0.8海里に接近し、衝突のおそれが生じていることを認め、同時16分半僅(わず)か前互いに0.5海里に接近する状況となったが、相手船がそのうち避航動作をとるものと思い、警告信号を吹鳴することなく、針路と速力を保持したまま航行した。
A受審人は、12時17分シリウスが590メートルの間近に接近し、シリウスの避航動作のみでは衝突を避けることができないと認められる状況になったが、直ちに機関を全速力後進にかけるなど衝突を避けるための最善の協力動作をとらずに続航した。
12時17分半少し前A受審人は、400メートルにまで接近したシリウスにやっと衝突の危険を感じ、自動操舵のまま、機関操縦装置のハンドルを停止に引き、同装置のパイロットランプを確かめてから直ちに微速力後進に引き、プロペラ軸は4秒後に後進回転に入ったものの、依然としてシリウスに避航動作の気配が見られないので、同時17分半主機を全速力後進にかけたところ、右舵がとられていたためか、舵付近で後進の推進器流が勢いを増すにつれ、左回頭を強めながら前進し始めた。
A受審人は、機関を全速力後進にかけたころ、今まで直進していたシリウスが右転し始めたのに気づいたが、すでに互いに280メートルにまで接近し、何ら有効な手を打つ余裕がなく、機関後進の効果を待っているうち、12時18分部埼灯台から126度3,130メートルの地点において、勇進丸は、290度に向いて6.0ノットの前進惰力を残したまま、その船首がシリウスの左舷中央部に前方から70度の角度で衝突して嵌(は)まり込んだ。
当時、天候は雨で風は殆どなく、潮候はほぼ低潮時で、視程は1海里であった。
また、シリウスは、二層甲板を有する船尾船橋型貨物船で、専ら中華人民共和国の泉州から宇野港又は名古屋港への航海に従事し、B指定海難関係人及び二等航海士Cほか韓国人1人及びフィリピン人5人が乗り組み、御影石及び白陶土1,542トンを積載し、船首尾5.0メートルの等喫水をもって、同月19日15時00分(現地時間)泉州を発し、宇野港に向かった。
ところで、シリウスは、昭和51年10月広島県豊田郡木江町R株式会社で建造され、S株式会社で所有されていた第十五清丸と称する総トン数697.74トンの貨物船で、垂線間長65.00メートル幅11.40メートル深さ6.80メートルで、平成9年5月にシリウスに船名が変更されてからも、船体は建造時と同じ状態で使用されていた。
なお、C二等航海士は、甲板長の資格で5年間の乗船の経歴を積み、1997年3月にフィリピン共和国の三等航海士の免状を取得し、同年5月24日シリウスに乗船したとき、初めて二等航海士の職に就き、船舶往来の少ない海域では1人で船橋当直に立直していたものの、瀬戸内海の船舶交通の輻輳(ふくそう)する海域においては、B指定海難関係人が昇橋して見張りと操船の指揮にあたっていた。
こうして、B指定海難関係人は、越えて同月23日09時10分関門港西口六連島沖合の錨地に投錨して検疫を済ませ、10時40分抜錨したのち、甲板手を手動操舵に配置して操船を指揮し、途中11時50分ごろ昇橋してきたC二等航海士に手動操舵を引き継がせて関門港を通り抜け、12時05分ごろ部埼灯台の沖合に至り、部埼南東沖合の錨地に10隻ばかりの船舶が錨泊していることをレーダー画面で確認したが、下関南東水道第1号灯浮標(以下「第1号灯浮標」という。)を視認でき、視程が約1.5海里あったことに気を許し、錨泊船群の中から急に船舶が飛び出してくるおそれのある状況であったものの、しばらく船橋に留まって錨泊船群周辺の他船の動静を確認することなく、出航部署を解いて平常の航海当直体制に切り換えることとし、12時10分部埼灯台から101度770メートルの地点に達したとき、針路を135度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で進行し、C二等航海士は船舶交通の輻輳海域での船橋当直の経験が十分でなく、1人で即座に、かつ、的確に状況を判断をして適切な操船にあたることを期待できなかったが、引き続き在橋して操船の指揮をとることなく、第1号灯浮標から針路を125度に転ずること、同灯浮標の付近は漁船を含む通航船舶が多いので気をつけることの2点を指示しただけで降橋し、昼食のため食堂に向かった。
C二等航海士は、12時15分部埼灯台から124度1.2海里の、第1号灯浮標を左舷正横に見て0.1海里隔てた地点で、針路を125度に転じて自動操舵として航行するうち、12時15分半レーダーの画面で右舷船首20度0.8海里に勇進丸の映像を初認し、操舵室の外に出て同船が前路を左方に横切る態勢で接近しているのを確認し、同時16分半僅か前、勇進丸との相対方位に変化がなく、衝突のおそれがある態勢で互いに0.5海里に接近したが、コンパス方位を計測するなど、動静監視を十分に行わなかったので、自船の方が先に勇進丸の前路を横切って替わることができるものと思い、速やかに右舵一杯をとって勇進の進路を避けることなく、避航の時期を逸したまま続航中、同時17分半少し前互いに400メートルにまで接近したとき、初めて衝突の危険を感じ、手動操舵に切り換え、右舵一杯をとって右回頭していたところ、勇進丸が左転していることに気づき、同時18分僅か前左舵をとったが効なく、シリウスは、その船首が180度に向いて9.0ノットに減速したとき、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、勇進丸は船首両舷側の水線上に亀裂とともに、球状船首部に破口を伴う凹損を生じたが、のち修理され、シリウスは左舷中央部に大破口を生じ、勇進丸から離れて左舷側に傾いたまま左回頭し、12時26分ごろ部埼灯台から127度3,400メートルの地点で沈没し、シリウスの乗組員は、沈没前に離船して海上に浮かんでいるところを勇進丸乗組員に全員救助された。
なお、同日12時50分航行中の第二十一日之出丸がシリウスの船体に乗り揚げて航過し、シリウスの周辺には標識が施されて航行船舶に警報が出されたものの、越えて6月13日にはパナマ国籍貨物船ベイボナンザがシリウスに乗り揚げる事件が発生した。シリウスの船体は8月22日サルベージ業者により引き揚げられて大韓民国に運ばれ、のち解体された。
(原因)
本件衝突は、下関南東水道部埼沖合において、シリウスが、船橋部署体制が適切でなかったうえ、動静監視不十分で、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する勇進丸を避けなかったことによって発生したが、勇進丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための最善の協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人等の所為)
A審人は、下関南東水道部埼沖合において、左舷前方に前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するシリウスを認めたのち、針路と速力を保持しながら進行中、同船が間近に接近しても避航の気配を示さなかっ場合、衝突を避けるための最善の協力動作をとるべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、シリウスが避航動作をとるものとばかり思い、機関を一挙に全速力後進にかけるなど、最善の協力動作をとらなかった職務上の過失により、機関の動作を小幅にとってシリウスに接近し続け、同船との衝突を招き、勇審丸の船首両舷側に水線上に亀裂と球状船首部に破口を伴う凹損を、シリウスの左舷中央部に大破口をそれぞれ生じさせ、シリウスを沈没させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
B指定海難関係人が、関門港を東航したのち、視界の見通しが良くない部埼沖合で多数の船舶が錨泊しているのを認めた際、錨泊船群の周辺において航行中の船舶に出会うおそれがあったのに、経験の浅い航海士1人だけを船橋に配置し、自ら操船の指揮にあたらなかったことは、本件発生の原因となる。
よって主文のとおり裁決する。
参考図(2) 参考図(1)
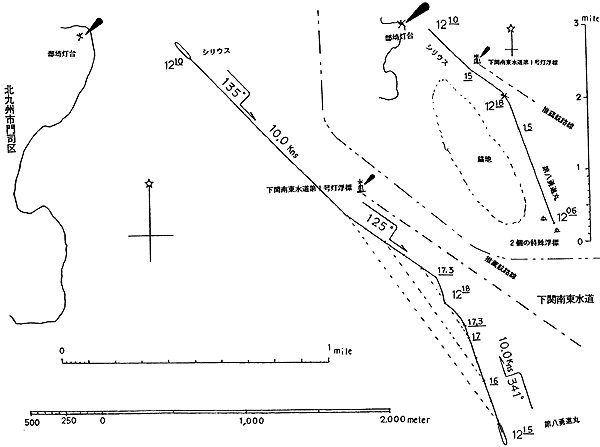
参考図(3)
.gif) |