 |
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年12月22日18時46分
那覇港
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第十二有明丸
貨物船サニーキング
総トン数 2,367トン
1,107トン
全長 102.00メートル
登録長 60.00メートル
機関の種類
ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 2,942キロワット
1,323キロワット
3 事実の経過
第十二有明丸(以下「有明丸」という。)は、航行区域を限定近海区域とし、専ら京浜港川崎区と四日市港から那覇港への自動車輸送に従事する船首船橋型自動車運搬船で、A受審人ほか10人が乗り組み、自動車355台を積載し、船首3.90メートル船尾5.40メートルの喫水をもって、平成9年12月20日15時00分四日市港を発し、那覇港新港ふ頭7号岸壁に向かった。
翌々22日17時50分ごろA受審人は、残波岬西方約1海里の地点で昇橋し、代理店に船舶電話で郡覇港の唐口(とうくち)から出航する他船の有無を問い合わせ、18時30分ごろに1隻の出航船があるとの情報を得たのち、航行中の動力船の灯火を表示して自ら操船の指揮を執り、唐口に向けて進行した。
ところで、唐口は、航路を設定していなかったものの、那覇港新港第1防波堤南灯台(以下「南灯台」という。)から302度(真方位、以下同じ。)2,080メートルのところに設けた那覇港中央灯浮標(以下「中央灯浮標」という。)のほか数個の右舷標識と左舷標識とを備え、新港第1防波堤(以下「防波堤」という。)の入口付近の最少可航幅が約350メートルであり、新港ふ頭に向かうには、那覇港導灯(以下「導灯」という。)が、示す127.4度の方位線に沿って航行し、那覇港第4号灯浮標の手前で北東方に向けて大角度に変針する必要があった。
18時30分ごろA受審人は、唐口の北北西方約2.3海里の地点に達したとき、入船配置を令し、二等航海士を船長補左と見張りに、甲板手を手動操舵に、機関長を船橋での機関操作にそれぞれ当たらせ、中央灯浮標を船首目標として防波堤を左舷側に見て南下していたところ、同時33分ごろ唐口を出航する他船を認め、同船が代理店から知らされた出航船で、ほかには出航する船舶はいないものと考え、同時36分少し過ぎ南灯台から317度2,500メートルの地点に達したとき、針路を155度に定め、速力を港内全速力前進の12.5ノットとして唐口に向けて続航した。
18時39分少し前A受審人は、南灯台から306度1,560メートルの地点に達したとき、左舷船首45度2,400メートルのところに、防波堤の入口に向けて出航する態勢のサニーキング(以下「サ号」という。)の白、白、緑3灯を初認し、そのまま進行すれば同船と防波堤の入口付近で出会うおそれがあることを知ったが、300ないし400トンの小型船だろうから、導灯を左舷船首方に見て航行すれば、防波堤の入口付近で互いに左舷を対して十分に航過できるものと思い、速やかに機関を後進にかけて行きあしを止めるなどの防波堤の外で同船の進路を避けることなく、同時39分少し過ぎ機関の回転数を下げ、6.9ノットの微速力で続航した。
18時40分半わずか過ぎA受審人は、南灯台から296度1,200メートルの地点に至り、針路を防波堤の入口に向く130度に転じたところ、サ号を左舷船首24度1,840メートルに見るようになったが、依然防波堤の外で同船の進路を避けずに進行し、同時43分少し前サ号と南灯台とを一線に見るようになったころ、同船に注意を喚起するつもりでいったん探照灯を照射して続航した。
有明丸は、防波堤の入口に向けて進行中、18時45分ごろA受審人が、右転しながら左舷船首至近に迫ってきたサ号を認め、衝突の危険を感じて右舵一杯とし、再び同船に向けて探照灯を照射したが、効なく、18時46分南灯台から242度340メートルの地点において、船首が200度を向いたとき、原速力のまま、その左舷船尾部にサ号の船首が前方から74度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力2の北西風が吹き、潮候は下げ潮の末期で、視界は良好であり、日没は17時44分であった。
また、サ号は、専ら那覇港と中華人民共国福州港間のコンテナ輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、ミャンマー入船長B及び台湾人機関長Cほかミャンマー人11人が乗り組み、雑貨入りコンテナ21個を積載し、船首2.60メートル船尾3.40メートルの喫水をもって、同日18時20分新港ふ頭1号岸壁を発し、航行中の動力船の灯火を表示して福州港に向かった。
ところで、C機関長は、乗組員に機関長の海技免状受有者がいなかったので、機関長として雇入れされていたものの、船長の海技免状も受有し、実質上の船長として自ら操船の指揮に当たっていた。
発航後、C機関長は、B船長を船首に配置し、操舵手を手動操舵に就かせ、機関を微速力前進にかけて6,0ノットの速力で進行し、18時39分少し前南灯台から085度1,000メートルの地点に達したとき、針路を256度に定めて続航した。
定針したとき、C機関長は、右舷船首34度2,400メートルのところに、防波堤の入口に向けて入航する態勢の有明丸の白、白、紅3灯を視認でき、その後同船が針路を転じ、そのまま進行すれば、同船と防波堤の入口付近で出会うおそれのある状況となったが、右舷前方の南灯台の灯火に気をとられ、周囲の見張りを十分に行っていなかったので同船の存在に気付かないまま続航した。
18時43分少し前C機関長は、有明丸が右舷船首30度1,090メートルに接近し、自船に向けて探照灯を照射したものの、依然周囲の見張りを十分に行っていなかったので、これに気付かず、速やかに警告信号を行うことも間近に接近したとき機関を後進にかけて行きあしを止めるなどの衝突を避けるための措置をとることもできないまま進行した。
18時45分ごろサ号は、南灯台から207度220メートルばかりの地点に達したとき、右舵10度をとって防波堤の入口に向けて右回頭中、C機関長が、左舷船首至近に有明丸の白、白、緑、紅4灯を初認し、驚いて機関を停止したが、効なく、船首が306度を向いたとき、約5.0ノットの残速力で、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、有明丸は、左舷側船尾部外板に亀裂を伴う凹損を生じ、サ号は、船首部を圧壊したが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、夜間,那覇港唐口の防波堤の入口付近において、入航する有明丸と出航するサ号とが出会うおそれがあった際、有明丸が、防波堤の外でサ号の進路を避けなかったことによって発生したが、サ号が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、那覇港唐口の防波堤の入口に向けて入航中、防波堤の入口に向けて出航中のサ号を認め、同船と防波堤の入口付近で出会うおそれがあることを知った場合、防波堤の外で同船の進路避けるべき注意義務があった。しかるに、同人は、導灯を左舷船首方に見て航行すれば、同船と互いに左舷を対して十分に航過できるものと思い、防波堤の外で同船の進路を避けなかった職務上の過失により、そのまま進行して衝突を招き、有明丸の左舷船尾部外板に亀裂を伴う凹損を、サ号の船首部に圧壊を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
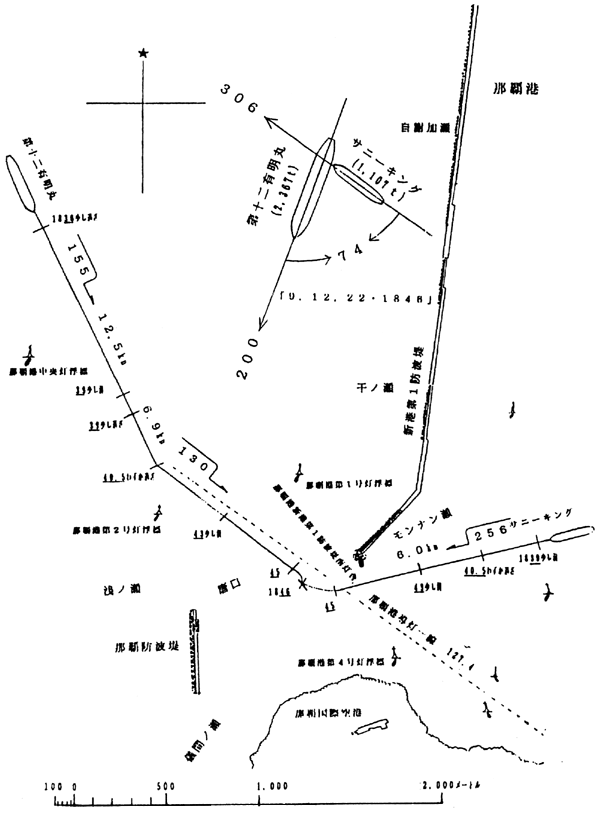 |