 |
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年4月6日13時30分
佐賀県呼子港北方海域
2 船舶の要目
船種船名 漁船新漁丸
漁船洋丸
総トン数 13トン 4.34トン
登録長 14.86メートル 9.65メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
漁船法馬力数 160 50
3 事実の経過
新漁丸は、専ら一本釣り漁業に従事し、船体中央からやや後方に操舵室を設けたFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、いか漁の目的で、船首0.70メートル船尾1.50メートルの喫水をもって、平成10年4月6日13時10分佐賀県小川島漁港を発し、僚船10隻ばかりとともに長崎県五島列島西方沖合の漁場に向かった。
発航後、A受審人は、沖合に出たところでいったん停止し、トリムタブを調整したのち、機関の回転数を徐々に上げながら進行し、13時20分少し前小川島港西防波堤灯台から228度(真方位、以下同じ。)600メートルの地点に達したとき、GPSプロッターに表示させた度島を船首目標として針路を242度に定め、機関の回転数を常用の毎分1,600とし、折からの海潮流に抗して14.0ノットの対地速力で、操舵室右舷側操縦席に腰掛けて手動操舵に当たり、トリムタブによって船首の浮上を押さえても、船首前方6度ばかりの範囲に死角を生じるうえ、煙突やマストの前部甲板上の構造物により前方の見通しが悪いことから、時折天窓から顔を出して周囲を確認し、遠方の島々が霞んで見にくい状況下、GPSプロッターを見ながら進行した。
13時29分少し前A受審人は、波戸岬灯台から024度2,170メートルの地点に達したとき、先行する僚船から無線電話がかかり、自船の前方に小型船がいるとの注意を受けて天窓から顔を出し、前路540メートルのところに、船首を北方に向けて船尾にスパンカを張った漂泊中の洋丸を認めたが、一べつしたのみで、たまたま同船が左舷船首わずか左に見えたことから、同一の針路のまま同船を左舷側に30メートルばかり隔てて航過できるものと思い、引き続き天窓から顔を出して操船に当たるなど、同船に対する動静監視を十分に行うことなく、再び操縦席に腰掛け、衝突のおそれがある態勢で同船に向首接近していることに気付かないまま続航した。
こうしてA受審人は、腰掛けたまま0.5海里レンジとしたレーダーで同船の映像をとらえようとしたものの、洋丸が木船であったためか同船の映像をとらえることができず、漂泊中の洋丸を避けないで進行中、13時30分わずか前船首死角の右舷側に洋丸の船首部を、左舷側に洋丸のスパンカをそれぞれ認め、とっさにクラッチを中立として左舵一杯としたが、及ばず、13時30分波戸岬灯台から015度1,800メートルの地点において、202度に向首したとき、ほぼ原速力のまま、新漁丸の船首部が洋丸の右舷後部外板に前方から45度の角度をもって衝突した。
当時、天候は曇で風力2の北北西風が吹き、潮候は上げ潮の初期で約1ノットの東北東方に向かう海潮流があり、視程は3海里ばかりであった。
また、洋丸は、専ら一本釣り漁業に従事し、船体後部に操舵室を設けた木製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、汽笛やその代用となる設備を持たず、いか漁の目的で、船首0.25メートル船尾2.00メートルの喫水をもって、同日06時30分佐賀県加唐島漁港を発し、加唐島北西方沖合の漁場に向かい、同時40分ごろから同漁場において操業を行ったものの、漁獲が少なかったので漁場を移動することとし、12時00分佐賀県呼子港北方の海域に向けて発進した。
ところで、呼子港北方の海域は、その周囲に、いずれも漁港を有する加唐島、小川島、松島、馬渡島などの島々があって、漁場を往来する漁船や、島々を行き交うフェリーなど、多数の船舶が通航するところであり、十分な信号設備をもたない小型漁船は、気象、海象条件などによって他船から視認しにくい状況となることがあるから、同海域で漂泊したり操業したりする際、危険が迫れば速やかにこれを回避するための適切な措置をとることが必要であった。
12時15分B受審人は、波戸岬灯台から351度1,600メートルの地点に至って再び操業を始め、船尾にスパンカを張って折からの風で北北西に向首し、風下に落とされないよう機関を適宜使用しながら操舵室前方の甲板上に出て漂泊中、海潮流によって1海里ばかり東北東方に圧流されたので、13時10分操業再開地点まで潮上りし、その後同じ態勢で操業を行ったものの、漁獲がないので操業をあきらめ、同時20分ごろ漁具の収納に取り掛かり、同時29分少し前波戸岬灯台から014度1,790メートルの地点まで圧流され、337度に向首した態勢で漁具の収納を続けていたとき、右舷船首85度540メートルのところに新漁丸が自船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近する状況となった。
13時29分半わずか過ぎB受審人は、新漁丸を同方向200メートルのところに認め、その操舵室が見えない状態で船首部に白波を立てながら自船に急速に向首接近することに気付いたが、新漁丸が船首を右舷に少し振ったように見えたことから、自船を避ける動作をとったものと思い、クラッチを入れて速やかに移動するなど、親漁丸との衝突を避けるための措置をとることなく、その動静を見ていたところ、同船との距離が100メートルを切るようになって再び自船に向首するのを認め、初めて衝突の危険を感じ、操舵室に赴き機関のクラッチを入れようとしたが、及ばず、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、新漁丸には損傷がなかったが、洋丸は、右舷後部板大破、操舵室圧壊、船尾張出し甲板脱落などの損傷を生じ、のち廃船とされた。また、B受審人が、右腕骨折及び右手挫傷などを負った。
(原因)
本件衝突は、佐賀県呼子港北方の船舶が多数通航する海域において、漁場に向けて航行中の新漁丸が、動静監視不十分で、漂泊中の洋丸を避けなかったことによって発生したが、洋丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、佐賀県呼子港北方の船舶が多数通航する海域を漁場に向けて航行中、前路に漂泊中の洋丸を認めた場合、同船を無難に替わせるかどうか判断できるよう、引き続き天窓から顔を出して操船するなどの同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、洋丸を一べつしたのみで、そのままの針路で同船を左舷側に隔てて航過できるものと思い、その後操縦席に腰掛けたままで同船に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、洋丸を避けずに進行して同船との衝突を招き、同船に左舷後部外板大破、操舵室圧壊、船尾張出し甲板脱落などの損傷を、B受審人に右腕骨折などを負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、佐賀県呼子港北方の船舶が多数通航する海域において操業のために漂泊中、自船に急速に向首接近する新漁丸を認めた場合、十分に有効な信号設備がなかったから、クラッチを入れて速やかに移動するなどの衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、親漁丸の船首が右に振れたように見えたことから、同船が自船を避ける動作をとったものと思い衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、新漁丸との衝突を招き、前示損傷等を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
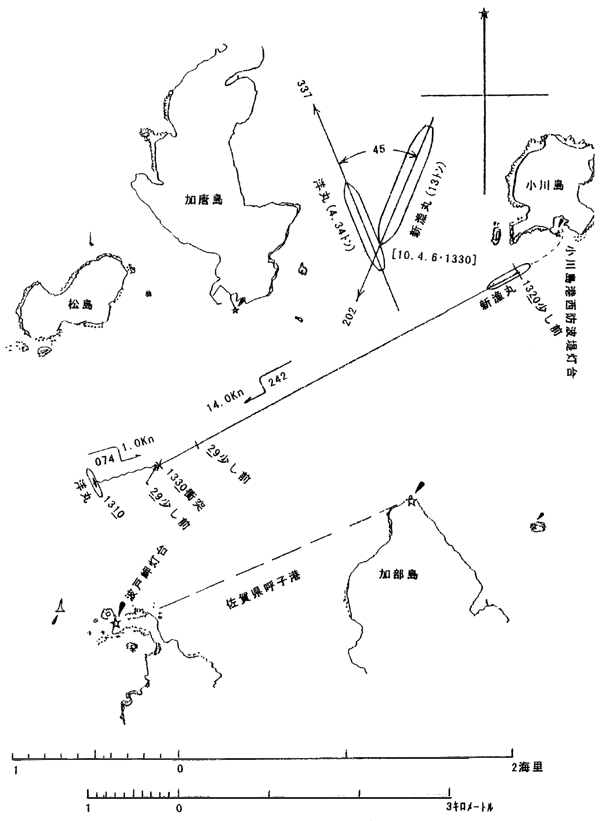 |