 |
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年12月23日12時05分
和歌山県日ノ御埼沖合
2 船舶の要目
船種船名 貨物船住久丸
遊漁船福丸
総トン数 199トン 7.02トン
全長 58.80メートル
登録長
11.95メートル
機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関
出力 735キロワット
235キロワット
3 事実の経過
住久丸は、鋼材などの輸送に従事する船尾船橋型の貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、鋼材680トンを積載し、船首2.8メートル船尾36メートルの喫水をもって、平成9年12月23日05時40分兵庫県姫路港を発し、京浜港東京区に向かった。
A受審人は、10時30分ごろ和歌山県ツブネ鼻西方において、前直の機関長と交替して単独の船橋当直に当たり、その後昇橋した甲板員である妻を見張りの補助につけ、11時28分紀伊海鹿島灯標から265度(真方位、以下同じ。)0.8海里の地点で、針路を175度に定め、引き続き機関を全速力前進にかけ、10.5ノットの対地速力で、次の転針予定地点である日ノ御埼沖合に向けて手動操舵により進行した。
12時02分A受審人は紀伊日ノ御埼灯台から239度760メートルの地点を通過したとき、針略を市江埼沖合に向かう137度に転じ、このとき左舷船首26度1.1海里に、前路を右方に横切る、態勢の福丸の白い船体を初めて視認した。
その後、A受審人は、福丸の動静を監視していたところ、同船が避航の気配を見せないまま衝突のおそれのある態勢で接近することを知ったが、警告信号を行わず、また間近に接近したのを認めても、同船が小型船なので避航すれば間に合うものと思い、機関を後進にかけるなど衝突を避けるための協力動作をとることなく、同じ針路、速力のまま続航した。
12時05分少し前、A受審人は、福丸が同方位200メートルに近づいたので、衝突の危険を感じ、機関を停止としたが及ばず、12時05分紀伊日ノ御埼灯台から180度1,100メートルの地点において、住久丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首部に、福丸の船首が前方から47度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力5の北北東風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、海上はやや波が高かった。
また、福丸は、船体中央部やや後方に操舵室を備えたFRP製小型遊漁廉用船で、B受審人が1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日11時30分和歌山県御坊港西川右岸の係留地を発し、日ノ御埼南方の釣り場に向かった。
11時45分半B受審人は、日高川河口沖の、紀伊日ノ御埼灯台から098度4.3海里の地点で、針路をGPSプロッターに入力しておいた釣り場に向かう270度に定め、機関を半速力前進にかけ、13.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
ところで、福丸は、高速力で航行すると船首部が大きく浮上することに加え、船首端から約2.5メートル後方の右舷船首甲板上に設置された長さ幅とも約60センチメートルで、甲板上の高さ約1.5メートルの仮設便所と、操舵室前方の機関室囲壁上の船体中心線より少し右舷寄りに設置された直径約40センチメートルの煙突とにより、舵輪後方の左舷寄りで操船に当たったとき、船首から右舷方にかけて大きな死角を生じ、前方の見通しが妨げられる状態となっていた。
B受審人は、平素、操舵室天井の開口部から顔を出して見張りに当たるようにしていたが、当時海上の波がやや高く、風浪を右舷方から受けてたえず波しぶきが操舵室にかかる状況であったことから、同開口部から顔を出すことをやめ、操舵室内の舵輪後方の左舷寄りでいすに腰を掛け、旋回窓を作動させて操船と見張りに当たった。
12時02分B受審人は、紀伊日ノ御奇灯台から133度1,650メートルの地点に達したとき、右舷船首21度1.1海里に、前路を左方に横切る態勢の住久丸を視認することができ、その後その方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近したが、航行の妨げとなる他船はいないものと思い、釣り場のポイントを確かめることに気をとられ、船首を大きく振るなど死角を補う賑りを十分に行うことなく、作動中の旋回窓に顔を近づけて前を見ていたので、住久丸の接近に気付かず、早期に右転してその進路を避けることなく進行中、12時05分突然衝撃を受け、福丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、住久丸は左舷船首外板に擦過傷を生じたのみであったが、福丸は船首部を圧壊し、のち修理された。
(原因)
本件衝突は、和歌山県日ノ御崎沖合において、両船が互いに進銘を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、福丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る住久丸の進路を避けなかったことによって発生したが、住久丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、操舵室の舵輪後方の左舷寄りで操船と見張りに当たり、御坊港から日ノ御埼沖合の釣り場に向けて西行する場合、同位置からは船首から右舷方にかけて大きな死角を生じて見通しが妨げられる状態であったから、前路を左方に横切る態勢で接近する住久丸を見落とすことのないよう、船首を振るなどして死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが同人は、航行の妨げとなる他船はいないものと思い、釣り場のポイントを確かめることに気をとられ、死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、右舷船首方から接近する住久丸に気付かず、同船の進路を避けずに進行して住久丸との衝突を招き、同船の左舷船首外板に擦過傷を生じさせ、福丸の船首部を圧壊させるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、紀伊水道を日ノ御埼に接航して南下中、市江埼沖合に向かう針路に転じたとき、左舷船首方に前路を右方に横切る福丸を視認し、その後衝突のおそれがある態勢で避航の気配のないまま間近に接近するのを知った場合、機関を後進にかけるなど衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。ところが、同人は、福丸が小型船なので避航すれば間に合うものと思い、機関を後進にかけるなど衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、そのまま進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
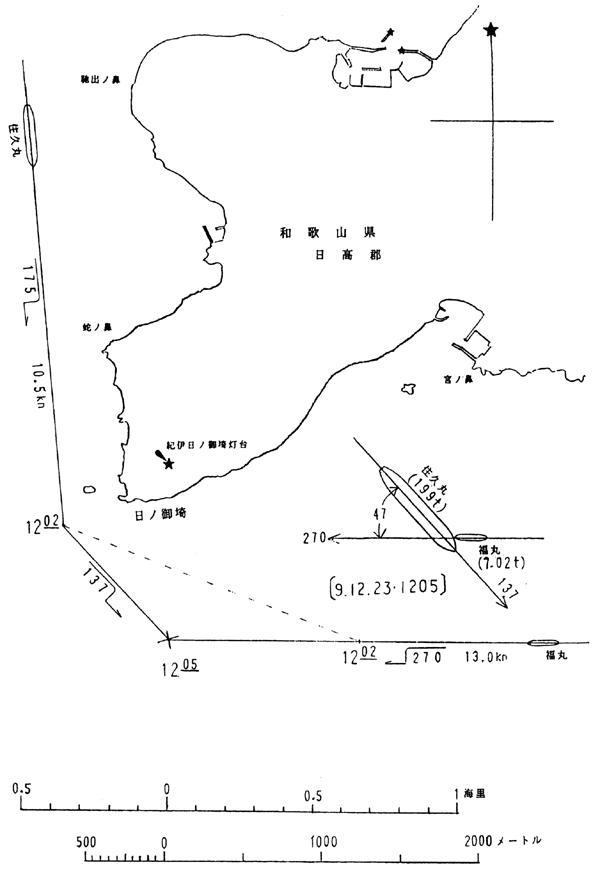 |