 |
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成7年9月19日12時46分
広島県土生港長崎瀬戸
2 船舶の要目
船種船名 旅客船第拾青丸
プレジャーボート伊東
総トン数 151.51トン
全長 30.20メートル 7.68メートル
幅
7.00メートル 1.85メートル
機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関
出力 220キロワット
33キロワット
3 事実の径過
第拾青丸(以下「青丸」という。)は、船首にランプゲート及び船体中央やや船尾寄りに船橋を備えた旅客船兼自動車渡船で、愛媛県弓削島明神と広島県因島長崎地区との間を1時間に2往復する短距離の定期航路に従事していたところ、A受審人ほか2人が乗り組み、乗用車2台及び旅客6人を乗せ、船首0.8メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、平成7年9月19日12時35分明神のフェリー発着場を発し、長崎地区の土生桟橋に向かった。
発航後A受審人は、船橋中央の操舵スタンドの後方に立ち、同スタンドの右舷側に取り付けられた操舵レバーを右手で操作しながら、単独で操船と見張りに当たり、12時43分少し前因島天狗山(208メートル)山頂三角点(以下「三角点」という。)から170度(真方位、以下同じ。)1,370メートルの地点に達したとき、針路を302度に定め、機関を8.0ノットの全速力前進にかけ、長崎瀬戸の右側寄りをこれに沿って進行した。
ところで、長崎瀬戸は、港則法が適用される土生港内に位置し、因島と生名島の間の幅員約300メートル、長さ約1海里の南東から北西方向に延びる狭い水道で、各方面からのフェリー等が通航し、時期によっては釣り船が多数集まる海域であったが、本件発生当日の午前中は同瀬戸に釣り船が50隻ほど出ていたものの、正午ごろには10隻ほどに減少し、これらは、因島の造船所沖合で、岸線に沿って約400メートルの間に散在し、また、青丸が通航するころには他の航行船舶はいなかった。
A受審人は、これらの釣り船の間を定めた針路のまま続航し、12時44分半三角点から187度1,130メートルの地点に達したとき、正船首わずか左350メートルの、散在していた釣り船の北西端に位置して船尾マストに白色の三角帆を掲げた伊東を初めて視認し、間もなく同船が漂泊しているとともに、同船の右舷側で人が背中を見せて手釣りをしているのを認めた。
A受審人は、そのまま進行すれば自船の左舷船首部が伊東に接触し、衝突のおそれのある態勢となっていたものの、一瞥(いちべつ)して同船は自船の船幅程度離して左舷側に替わるものと思い、右舷方の着岸予定の桟橋が近くなったことから、同方向に目を向け、引き続き同船に対する動静監視を十分に行わなかったので、衝突のおそれのあることに気付かず、同船を避けないまま進行した。
12時46分わずか前A受審人は、再び、前方に目を向けたとき、左舷船首至近に迫った伊東を認め、急ぎ機関を中立としたが、効なく、12時46分三角点から205度1,030メートルの地点において、原針路、原速力のまま、青丸の左舷船首が伊東の左舷中央部に前方から13度の角度で衝突し、同船を転覆させてその船体を乗り切った。
当時、天候は晴で風力2の南東風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、潮流はほとんどなかった。
また、伊東は、船体中央よりやや船尾寄りに機関室を有し、同室後部に操舵装置と主機遠隔操縦装置を有するFRP製のプレジャーボートで、船長Bが1人で乗り組み、遊漁の目的で、同日09時45分港小用地区の係留地を発し、長崎瀬戸の釣り場に向かった。
やがて、B船長は、生名島寄りの釣り場に達したところで手釣りを開始し、正午少し過ぎになって潮が変わったことから、因島の造船所寄りの釣り場に移動し、機関のクラッチを切って中立回転としたうえ、船尾マストに白色の三角帆を掲げて折からの南東風に船首を立て、漂泊して再び手釣りを始めた。
12時44分半B船長は、衝突地点付近で、135度に向首した自船の機関室後部の右舷側に腰を下ろし、右舷方を向いて手釣りをしていたとき、左舷船首13度350メートルのところに青丸を視認することができ、その後同船が衝突のおそれのある態勢のまま自船を避けずに接近していたが、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、衝突を避けるための措置をとらなかった。
12時46分わずか前B船長は、移動を開始しようとして機関を低速にかけ、左舵一杯をとったとき、船首至近に迫った青丸に初めて気が付き、大声を出したが、何をする間もなく、行きあし及び舵効が生じる前に135度を向首して前示のとおり衝突した。
衝突の結果、青丸は、左舷船首部に擦過傷を生じ、伊東は、左舷側外板に亀裂を伴う損傷を生じ、船底を上にして転覆しているところを青丸によって最寄りの立石港の浅瀬に運ばれ、また、B船長(大正8年5月14日生、四級小型操縦士免状受有)は、伊東の機関室内に閉じ込められて溺死した。
(主張に対する判断)
本件は、土生港長崎瀬戸において、航行中の青丸と遊漁中の伊東とが衝突した事件である。
青丸側補佐人は、「本件は、伊東が青丸の左舷前方で漂泊していて、青丸とは無難に替わる態勢にあったところ、伊東が衝突直前に移動を始め、青丸の前路を航過しようとしたことによって発生したものである。」旨主張する。
以下この点について、検討する。
衝突前の両船の相対位置関係について、A受審人は、同人に対する質問調書において、「針路302度、速力8ノットで航行しているとき左舷船首方に伊東を初認した。間もなく同船が漂泊しているのを認めた。」旨の供述をしており、また、初認時の伊東までの距離は、青丸の運航模様に関する実況見分調書写中の記載により、350メートルであったことが確認されている。
一方、C船長は、同人に対する質問調書において、「三角帆を上げ、南東方を向いて漂泊し、手釣りをしていたとき、伊東は本船の右舷後方30ないし40メートルのところにいて、同じく南東方を向いて漂泊していた。青丸は本船と伊東の間の伊東寄りを進行し、青丸が本船の右舷側を航過した直後にB船長の大声を聞いた。直ちに伊東の方を見ると、同船の三角帆が青丸のランプの上に見えたが、すぐに見えなくなり、それと同時に何かを押しつぶすような大きな音がした。」旨を供述している。
これらを総合すると、A受審人は、衝突の1分半前に135度を向首して漂泊していた伊東を青丸の正船首わずか左、距離350メートルのところに初めて視認したものと認められる。
次に、青丸、伊東両船の衝突舷を考察すると、青丸については、A受審人に対する質問調書中、「針路302度のまま、青丸の左舷船首部が伊東に衝突した。」旨の供述記載により、青丸の衝突時の船首方向は302度で、同船の左舷船首部が衝突したことは明らかである。
一方、伊東については、青丸側補佐人は伊東の左舷側が衝突したとは認定できない旨主張するが、同船の船体と損傷模様に関する実況見分調書写中の記載によれば、ステムに損傷はなく、左舷側の方が右舷側よりも損傷模様が大きいことが認められる。加えて、これらの損傷のうち、左舷ブルワーク上縁に設置されていたオーニング用支柱2本のうち1本は、右舷船尾方向に向けて、また、もう1本の支柱は、右舷正横方向に向けてそれぞれ曲損しているのが認められ、更に、船尾中央部にあった帆柱は、折損しているが、両片の折損面を合わせると右舷船尾方に傾斜する形となっていることが認められる。
これらのことから、伊東については、左舷が衝突したと認めるのが相当である。
ところで、伊東の船体と損傷模様に関する実況見分調書写中の記載によれば、伊東は、衝突時、機関を低速前進にかけ、舵を左舵一杯にとっていたことが認められることから、同船は、何らかの理由で移動しようとしていたことは十分考えられることである。
しかしながら、仮に、伊東が移動中に衝突したとしても、その衝突舷が左舷側と認められることから、同船の衝突時の船首方向は、漂泊中の船首方向である135度から青丸の針路の反方位である122度までの間にあったことになり、全長7.68メートルの伊東程度の大きさのプレジャーボートが最大13度回頭したとしても、同型船の運動性能から見ると、その回頭に要する時間は数秒程度の極めて短時間で、移動距離はほとんどなく、漂泊状態にあったものと考えられる。
一方、B船長のとった低速前進、左舵一杯の措置が、仮に差し迫った危険から逃れるためのものであれば、当時の両船の態勢から見て、全速前進、右舵一杯の措置をとるのが通例であることから、同人は、衝突の直前まで青丸との関係について危機意識を持っていなかったことが考えられる。しかしながら、このことは、前示のC船長の供述から明らかなように、単にB船長が衝突の直前まで青丸の接近に気付かなかったことによるものと認められる。
他方、伊東の近くで遊漁中のC船長も、伊東と自船の右舷側を航過して行った青丸との間の関係について、危機意識を持っていた様子が感じとれない。しかしながら、C船長は、同船長の原審審判調書添付の別紙Cすなわち青丸、伊東及び幸丸との関係図において、青丸が幸丸を無難に航過して行く態勢であったことを作図していることから、C船長は、青丸が自船を無難に航過する態勢にあり、伊東と青丸の第三船同士の相対位置関係について、特に関心を持って気に止めていたとは思われず、両船間の正確な把握ができていなかったことによるものと考えられる。
したがって、これらのことは、A受審人が伊東を初認した時点で、同船と青丸の両船間に衝突のおそれがあったことを否定するものではない。
以上を総合すると、伊東は、漂泊して釣りをしているとき、来航する青丸と衝突のおそれがあったところ、何らかの理由で移動を開始しようとして機関を低速前進にかけ、左舵一杯をとったものの、行きあしや舵効が生じる前に同船を認めたが、何をする間もなく、漂泊状態で本件が発生したと見るのが相当であり、青丸側補佐人の主張は、これを採用することはできない。
次に、青丸側補佐人は、「本件は、伊東が港則法第35条に違反し、港内においてみだりに漁ろうに従事していたことによって発生したものである。」とも主張する。
ところで、港内は、一般に船舶が輻輳(ふくそう)する海域であることから、そのような海域において、無制限に漁ろうを認めることは、船舶交通の安全上の問題ばかりでなく、港の機能が損(そこ)なわれる事態にもなりかねない。
そこで、港則法は、港内における船舶交通の安全を確保し、港内の整頓を図るために、特に「船舶交通の妨げとなる虞(おそれ)のある港内の場所においてみだりに漁ろうしてはならない」との規定を設け、港内の特に船舶が輻輳する場所において、船舶交通の支障となるような漁ろうをみだりに行うことを禁じており、この漁ろうには手釣りによる漁ろう等も含まれると解されている。
しかしながら、港内において、みだりに漁ろうを禁じている場所というのは、単に航路筋、泊地等といった場所的な要素だけでなく、当該場所の当該時刻における船舶の通航、停泊船の状況等時間的な要素も考慮に入れて具体的、かつ、個別的に判断して決まるものである。
したがって、当該漁ろう行為が、船舶交通の妨げとなるおそれがあるかどうかということは、そのときの個々の状況に即して判断されるべきものである。
ところで、長崎瀬戸は、港則法が適用される海域であるが、事実認定の根拠において述べたとおり、本件発生当時は潮が変わって午前中には50隻ほどいた釣り船が10隻ほどになっており、これら釣り船は因島の造船所沖合で、岸線沿いに長さ約400メートルの間に散在し、伊東はこれらの北西端に位置していたことが認められる。
また、C船長が、同人に対する質問調書において、「青丸の前方に釣り船以外の他船はいなかった。」旨を述べていることから、航行船舶は青丸以外にはいなかったことが認められる。
一方、A受審人は当廷において、「長崎瀬戸に入って定針してから直進した。」旨を供述し、また同受審人の原審審判調書において、「伊東だけを避ければ後は安全に行くことが出来た。」旨を供述していることから、青丸は、伊東とほぼ同じ海域で釣りをしていた釣り船の間を無難に航過してきたこと、更に、これら釣り船とほぼ同じ海域で、かつ、これらの北西端に位置していた伊東を替わし、目的地まで向うのに何の支障もなかったことが認められる。
したがって、伊東が、青丸の通航を妨げるような漁ろうをみだりに行っていたとは認められず、よって、本件に港則法第35条を適用する余地はない。
(原因)
本件衝突は、土生港長崎瀬戸において、西航中の青丸が、動静監視不十分で、漂泊中の伊東を避けなかったことによって発生したが、伊東が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、土生港長崎瀬戸において、単独で操船と見張りに当たり、釣り船が散在する同瀬戸を西航中、前路に三角帆を掲げて漂泊している伊東を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、引き続き同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、伊東は自船の船幅程度離して左舷側に替わるものと思い、伊東に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船を避けずに進行して衝突を招き、自船の船首部に擦過傷を生じさせたほか、伊東を転覆させ、B船長を溺死させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
(参考)原審裁決主文平成9年9月30日広審言渡(原文縦書き)
本件衝突は、第拾青丸が、動静監視不十分で、漂泊中の伊東を避けなかったことに因って発生したが、伊東が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったこともその一因をなすものである。
受審人Aの六級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
参考図
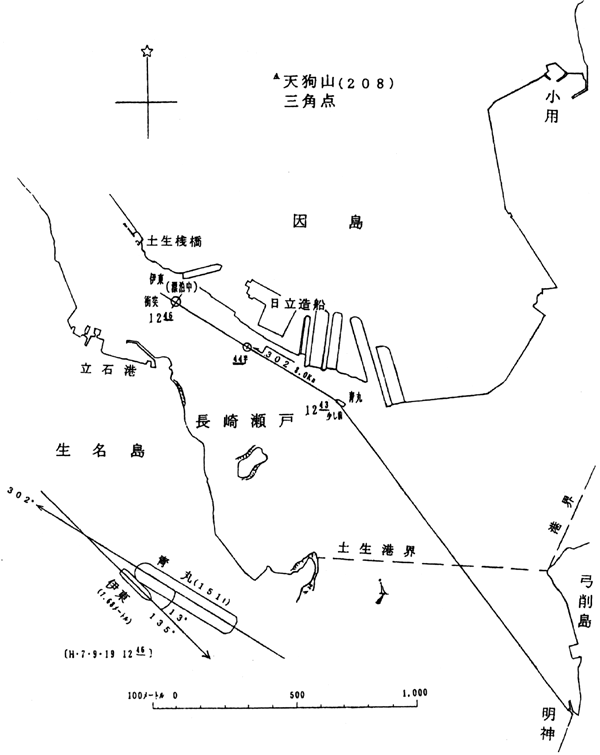 |