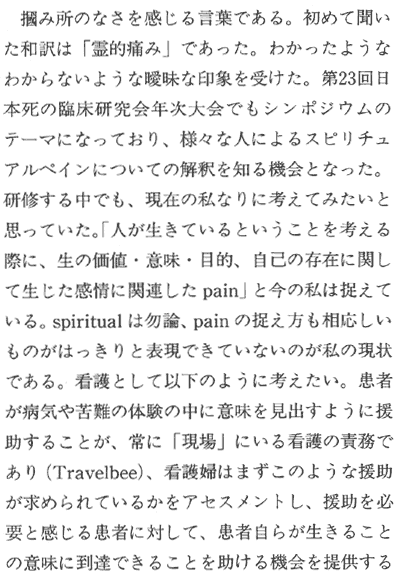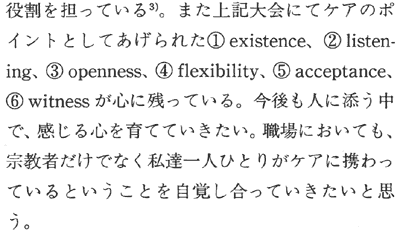2) 症状マネジメントについて
日々行っていることの再確認ができた。系統立てた考え方の補足、世界や日本全体の動向、使用したことのない薬剤や使用法、症状マネジメントのための統合的アプローチ、終末期におけるリハビリテーションなどの新しい知識を得ることもできた。症状とはその人が感じる主観的なものであり、訴えをありのままに受け入れる姿勢、共感する態度、訴えた言葉の背景を考えることが必要である。看護婦が症状のアセスメントをする際には、症状・ケアに関する豊富な知識、症状のために制限されている日常生活動作は何か、それに伴う患者さんと家族の思いはどうかと考える視点が重要である。今後の自分にとって、不足している知識の修得と同時に、看護婦の視点で看るという訓練の必要性を感じる。また、他施設ではどのようにしているのか一番聞きたかったセデーションについても、時間はなかったが、参考図書と「答えはない。その都度悩んでいこう」という言葉を恒藤先生からいただいた。鎮静は目的、継続性、レベル、時期により分類できる2)が、緩和ケアにおいては時期についての見極めがやはり難しいと思う。実習先でも、いつ開始するか、間欠から持続的に切り替えていくか等、話し合われていた。必要な時に、相応しい方法で鎮静を行えることが目標と言える。それが、遺る家族・我々にも記憶として残るのだ。人により鎮静の解釈・思いが異なる。今後もその都度皆─患者さん・家族・スタッフ─で話し合っていけたらと思う。
3) 家族・遺族ケアについて
家族・遺族ケアの重要性は、自分達のケアの配慮の足りなかったことから、遺族に死別後の苦しみや悲しみ、後悔の念を抱かせてしまった経験から身に染みて感じている。患者さんだけが満足しても、それだけでは片手落ちの場合もある。家族も全人的にケアしていく対象であり、遺族ケアは家族ケアの一端であるということを、講義を聴き強く認識した。家族をシステム、ライフサイクル等の面から捉える概念やストレスや危機下にある家族に添うために活用できる様々な理論について学んだ。必要時、自分の引き出しの一つとしてそれらを使えるようにしたいと思う。また、各家族により関わりが短期間に深まりやすかったり、なかなか情報を得られなかったりする。それはなぜか。家族のシステム自体に問題があるのか、家族全体へのもしくは家族員個々へのアプローチに問題があるのか、看護婦自身に逆転移や価値観の押し付けなどの問題があるのか、客観的に検討する必要がある。そのために、看護婦は、患者・家族の心理状態に関する知識と、自分自身を知り(自己認識)、受け入れ、コントロールして患者・家族と関わる力を持つ必要がある。人と人との関わりに変わりがないのだから、力み過ぎず必要な時に添える関係をチームとして築きたいと思う。
4) スピリチュアルペインについて