PROGRAMME NOTES
白石美雪
チン:オーシャン・フィーヴァー
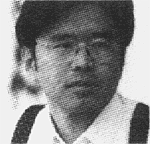
1957年、台湾生まれのゴードン・シーウェン・チンは中学時代を日本で過ごし、アメリカで作曲の学位を取得。現在、台湾の大学で教える傍ら、ピアニスト、指揮者としても活躍している。1997年に作られたこの曲の原題は「海的随想」。チンは水辺で思索に耽るのが好きで、横浜や南カリフォルニアの海岸、オンタリオ湖の岸辺へよく出かけた。波は彼に時の経過を思わせるという。最初にオーボエが曲全体を貫く主題を呈示する。はるか昔をなつかしむようなこの旋律がくり返される間に、過ぎ去った快活な日々を象徴するアレグロの部分が挟まれていく。
ヴィルムス:サンサラ
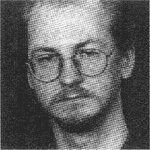
1974年にラトヴィアのリガで生まれたマルティンス・ヴィルムスは、アコーディオンを学んだのち作曲をはじめ、現在はリトアニア音楽アカデミーで研鑽を積んでいる。ラトヴィア作曲家協会が1996年の最優秀室内楽に選んだ《サンサラ》は弦楽四重奏に大太鼓が入る特殊な編成。タイトルは生と死の連鎖を意味していて、「生れ落ちた瞬間から、死と密接な関わりをもつ生命の価値を意識しながら、真実を語ろうとつとめた」という。曲は静と動の相互作用によって構成されている。
トルグレン:アステリア
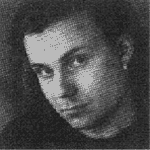
ヨハン・トルグレンは1971年ヘルシンキ生まれのフィンランドの作曲家で、シベリウス・アカデミーでハイニネンに学び、パリでサーリアホやマヌリ、ダルバヴィに師事した。現在はサンディエゴのカリフォルニア大学で、ファーニホウやチナリー・ウン、レイノルズについている。1995年作曲の《アステリア》は星の煌く夏の夜を描いた三重奏曲。木管の高音域を使った技巧的ですばやい動きが、星の瞬きを思わせる。ひとつの音程で作られた和音を拡大したり、転回しながら、一連の変奏が紡ぎ出されていく。
チョイ:ユンのための弦楽四重奏曲
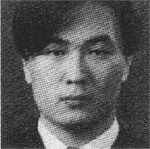
1974年、韓国生まれのミュンフン・チョイは高校、大学と作曲を専攻し、今年の2月に韓国国立音楽大学の大学院を修了した。1996年に書かれたこの曲は、音楽と郷土の韓国にたゆまぬ愛情を注いだイサン・ユンに捧げられている。ABCDA′という5セクションから構成され、Aの主題は作曲家ユンの思い出、Bは祖国を離れたのちの彼の音楽的行為を表現し、Cは彼の精神を崩壊させた恥辱と苦悩をユンの生没年(1917-95)を音名で象徴的に表現し、そのモチーフを使って描いた。Dは人間性の再発見を促した彼の1980年以降の音楽語法で、そしてA′は死後も残るユンの音楽とその思想を表している。
エルコレカ:カンタク
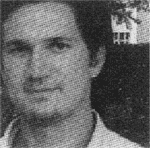
ガブリエル・エルコレカは1969年ビルバオ生まれのスペインの作曲家で、地元でピアノと作曲を学んだ後、奨学金を得て、現在、ロンドンに留学中。ロイヤル音楽アカデミーでフィニッシーに師事している。《カンタク》は1996年スペイン文芸協会のコンクールで第1位となった作品。器楽アンサンブルを背景にピッコロが活躍する曲で、バスク地方の民謡の構成が複雑なテクスチュアの奥に隠されている。ピッコロはバスクのポピュラー音楽に典型的なtxistu(チストゥ)という笛の代わりとして用いられ、全曲を通じてこの楽器の響きが主な素材となっている。
ヒンドソン:死の匂い
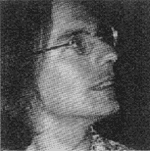
マシュー・ヒンドソンは1968年生まれのオーストラリアの作曲家で、シドニー大学とメルボルン大学で学んだ。国外のコンクールへもたびたびオーストラリアを代表して出品している。フルートとクラリネットとピアノを増輻するこの三重奏曲は、死をめぐる3つのアイディアと結びついている。一つは肉体の死とそれに抵抗する本能について、二つ目は死にいたる以前の生命体験に関する黙想、三つ目は「死のメタル」と呼ばれる音楽のジャンルで、作品全体にみられる暗い楽想はヴィルトゥオージティを駆使して演劇的に奏でられる。
前ページ 目次へ 次ページ