素の割合が下がっており、年功重視から能力重視の昇進制度への変更がさらに行われ又は行われようとしていることがうかがえる。(なお、他の理由は20〜30%程度となっていた。)
2. 昭和50年(1975年)大学卒サラリーマンの昇進実態
(1) 昇進の早いグループ〔第17図参照〕
オイルショック直後の昭和50年に大学を卒業し、民間企業に採用された者が20有余年在職し、現在、当該企業で昇進の最も早い(トップ)グループとして取り扱われているのは、同期採用者の24.6%(全体平均)で、前回調査(昭和61年調査「昭和40年大学卒採用者」のトップグループは35%)に比べ、幹部要員は大幅に絞りこまれ、3人に1人から4人に1人となった。
このトップグループの付いている役職(ポスト)を見てみると、最高は僅かではあるが「役員」が3%(前回調査3%)、「部長級」が39.8%(同24%)、「部次長級」が31.6%(同31%)、「課長級」が24.5%(同40%)となっており、半数に近い企業が「部長級」以上の役職を出していた。前回調査に比べ今回調査の方がスピード出世となっているが、前述のとおり、選別が大変厳しくなったこと、また、第1次オイルショック直後で各企業が新規採用者を手控えたことからかとも考えられる、
第17図 昇進が最も早いグループの昇進ポストの実態
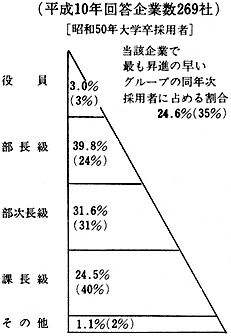
(注) ( )内の数字は、前回(昭和61年)調査で「昭和40年大学卒採用者」の昇進実態を調べた結果である。
(2) 昇進が遅れているグループ〔第18図参照〕
一方、当該企業で昇進が最も遅れているグループについて、現在、どのような役職(ポスト)に付いているかを見てみると、「課長代理級以下」とする企業が83.3%で、僅かに「部次長級」が0.8%、「課長級」15.9%となっており、課長代理級以下とする企業がほとんどであった。なお、同グループの同期採用者に対する割合は、22.3%(前回23%)となっていた。したがって、早いグループと遅いグループの割合を差し引いた半数程度(53.1%)が、「普通グループ」といえるのではないかと思われる。
第18図 昇進が最も遅れているグループの昇進ポストの実態
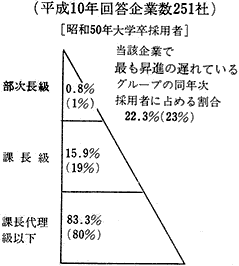
(注) ( )内の数字は、前回(昭和61年)調査で「昭和40年大学卒採用者」の昇進実態を調べた結果である。
V 人材評価と人事考課等
1. 人事評定の実施状況等〔第19図参照〕
人事評定を、
人材評価……職務能力のレベルやその発揮度を評価し、その結果、将来発揮できる可能性の高い能力や、開発される可能性の高い能力とそのレベルを予測できる評価システム
業績評価……一定の期間内に挙げた成績(結果)をきめられた評価基準に従って診断・評価するシステム
人事考課……人材評価と業績評価の両評価を行う評価システム
前ページ 目次へ 次ページ