
(B)海運事情と保有船主の実態
ペルーの海運業は、国内外の貨物運搬にとって重要な輸送手段である。
ペルーは環太平洋国であり、南米の東に通ずるアマゾン川の上流国でもあり、アンデス山脈が国土の中央を縦走しているため、海運水運は不可欠となっている。
また、対外貿易量の90%は海運輸送によっていることから、国の経済は大きく海運業に依存している。
ペルー政府は、第2次世界大戦後、自国海運業の育成に努め、海運政策としては自国船優先主義が導入され、1980年代初期には80万G/Tの船腹量を保有し、南米諸国では4番目に大きい商船隊を誇るに至った。
しかし、海運の実情に即さない過保護政策を取り続けたため、海運支援のための政府予算も枯渇し、徐々に海運業も不況に陥った。
さらに、1980年代にペルーを襲った経済危機および不安定な社会情勢などにより、ますます自国海運業の競争力が失われてきている。
1990年にフジモリ政権発足後、戦後実施された数々の保護政策は撤廃され続け、現在では一部の海運会社を除き、保護政策は残っていない。
1991年に自国海運業への優先制度がなくなったのを機に、ペルー商船隊の貨物運搬量は138万8,000トンから半減し、ペルーの海運不況を招き、多くの中小関連企業が姿を消していった。現在では、国内海運市場も外資系企業に徐々に開放されてきている。
今後、ペルー政府が再び自国海運業に対する保護政策を採ることは予想されないが、一方、アルゼンチンのように全面的に海運市場を外国海運会社に開放することについて、政府は明確にしていない。
このため、今後のペルー海運業界の行方は判然と.していない。
このような状況下、現在、ペルーの海運会社は、外国企業とのジョイント・ベンチャーによる外国資本・技術投資の促進や外国籍船によるメリット享受などを狙い、外国企業との合併および代表契約などを積極的に進める等、生き残りのための努力を行っている。
ペルー最大の貿易港は、首都リマのカヤオ港である。この他にサラベリ港、パカスマヨ港、パイタ港、サン・ファン港、サン・ニコラス港など、河川港等を含めて主要港が17存在する。
カヤオ港は、リマ首都圏および全国の輸出入運搬量の52%がこの港を通っており、穀物、・鉱物、一般貨物、液体貨物、石油、コンテナ貨物等を扱っている。
近年の著しい経済復興と貿易の自由化に伴い、カヤオ港を始めとした主要港の総荷動き量は急増している。
1996年にカヤオ港に出入港した船舶数は約3,490隻であり、運搬された一般貨物コンテナ数は201,552TEU(輸出用77,618TEU、輸入用123,934TEU)であった。
輸出貨物の多くは石油製品、鉄鉱および魚粉、輸入貨物の大半は石油・石油製品である。
1996年の実績によると、ペルーの港湾を利用する船舶のうち、ペルー船籍の割合は僅か6%に低下している。
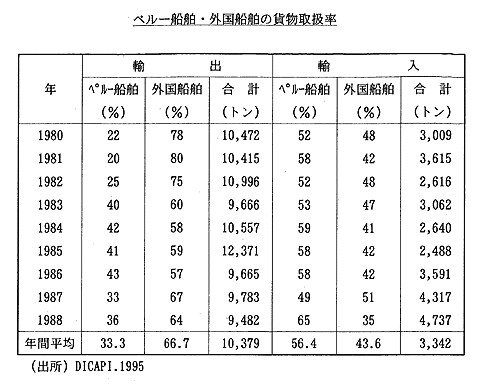
前ページ 目次へ 次ページ
|

|