これらの水抵抗器の電極面の電流密度は、0.15A/cm2以下にとるのがよい。清水の固有抵抗は20℃で2000〜5000Ω・cmであるが食塩含有量が5%をこえると10〜5Ω・cmと急激に減少する。
図2.1は450V回路で1000KW程度まで負荷がかけられる水抵抗器の一例であるが、普通のドラムカン(0.6φ×0.9m)を使っても流水なしで3〜5KW,5l/minの水を流して約20KWの負荷がとれる。この場合の電極は面積0.06m2、厚さ5mm程度3枚でよい。
(c) 電動機の負荷試験で、相手機械と連結されているときは、相手機械に負荷をとってもらうのが普通である。
電動機単独のときは、他の発電機をベルト掛け又は直結してそれに負荷をとってもらうのが普通である。
(e) 負荷力率を1.0以外の任意の力率(一般に遅れ90〜80%)で運転するときは、水抵抗とともに可変リアクトル又は同期電動機を使う。同期電動機(交流発電機でよい)を使うときは、2・2・8の図2・12のように接続し、界磁電流を調整して力率を変化させる。最大遅れ容量Qは、励磁電流を零にしたときで次の値となる。
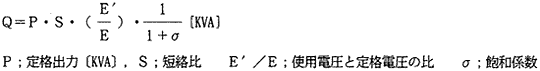
なお、さらに励磁電流の極性を変えて励磁すると10〜20%くらい容量を増すことができる。
2・1・7 復習問題(2)
(1) 試験・検査に適用される規則、規格などはどんなものがあるか述べよ。
(2) 試験を行った際の感電に対する安全対策を5つ挙げよ。
(3) 指示電気計器の校正はどの位の間隔で行う必要があるか述べよ。