従って、電圧の位相が零又はπ(180゜)の時短絡が発生した相に最大の交流分短絡電流が流れることになる。
IECでは遮断器が装備されていて、その点の短絡電流が問題になる系統において短絡電流を考える場合には最初の数サイクルが特に問題になるという理由から(式1)の同期リアクタンス分を無視して次のように近似している。
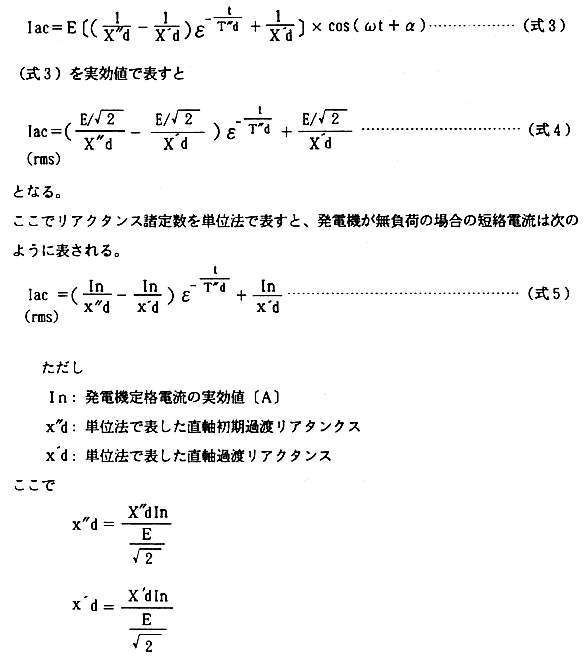
発電機が定格負荷を背負って運転している場合には、発電機の誘起電圧〔E〕は無負荷時の値よりも負荷電流による発電機の内部電圧降下分だけ高くなっているので、この場合の発電機の短絡電流計算においてはその時の誘起電圧の値を(式4)に代入して求めるべきであるが、IECではこの誘起電圧の値が不明の場合には(式5)で求めた無負荷時の短絡電流の値を1.1倍したものとしてよいとしている。
すなわち
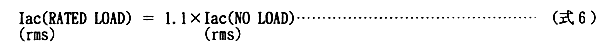
従って、IEC方式によって、実際に発電機の短絡電流の交流分実効値を計算する場合
には(式6)にもとずいて定格負荷時の値を求めこの値を使用すべきである。