
(c)交流発電機の構造
(2)(a)(ii)で述べた交流発電機では回転体に電機子コイルがあって,固定子が界磁磁極であった。しかし多くの交流発電機はその逆である。
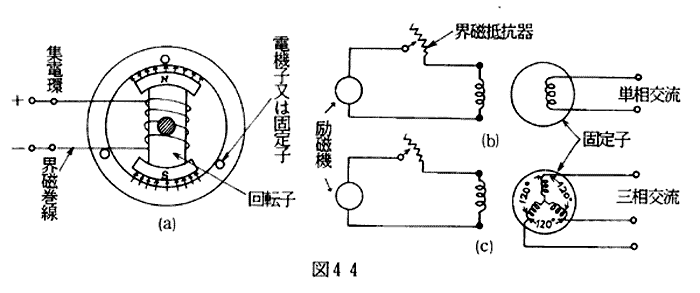
図44(a)のように固定子に電機子巻線があって,回転子は界磁巻線が施してある。そして励磁機から集電環を通じて界磁電流を磁極NSに送っている。この状態でこれを回転させれば固定子の電機子巻線に起電力が発生し,交流発電機となる。図44(b)のように固定子に1組の巻線を鉄心間に配置した場合には下図(a)のような単相交流が流れる。また,図44(c)のように固定子に120°づつへだてた3組の巻線を配置した場合には下図(b)のような三相交流が流れる。
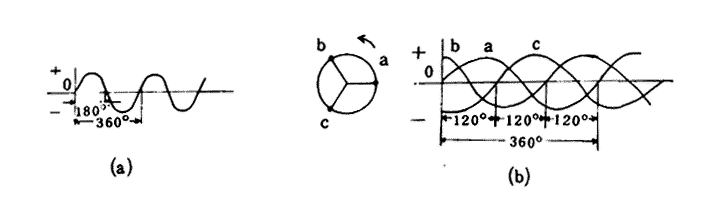
前者を単相交流発電機,後者を三相交流発電機という。
また,界磁が上記のように回転しているので,回転界磁形交流発電機と称し図44(a)はN,S極の2極であるが,これより多い極数のものがある。交流機の場合には定格周波数f〔Hz〕,極数P,回転速度Ns〔rpm〕との間に次の関係がある。
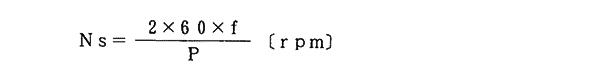
例えば,f=60〔Hz〕,P=2とする三相交流発電機の駆動機の回転速度は Ns=60×60=3600〔rpm〕でなければならない。
また,f=50〔Hz〕,P=4とする三相交流発電機の駆動機の回転速度は上式から
Ns=1500〔rpm〕となる。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|