
|
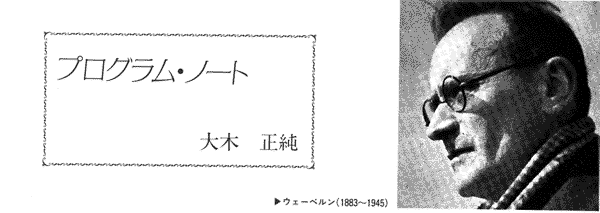
ウェーベルン:管弦楽のためのパッサカリアop.1 1908年、ウェーベルン(1883〜1945)が25歳になる年の作。彼は、その3年あまり前から、シェーンベルクに師事して研鑚を積んでいた。この曲は、その修行時代の成果を問う言わば集大成的な作品として書かれ、記念すべきop.1という、作品番号が与えられたのである。バロック時代の1種の変奏曲形式であるバッサカリア(シャコンヌと同義)が選ばれたのは、新ウィーン楽派の学究的側面を物語るもののように思われる。曲は弦のピッツイカートの弱音で、休止符を挟んで奏される8つの音による、ごく簡潔な主題を軸にウェーベルンらしい緻密なタッチで組み立てられている。変奏は全部で23,第10変奏まではニ短調が基調だが、第11〜第14変奏では、ニ長調に転じ、次いでもう一度短調に戻ったあと、比較的長いコーダで締めくくられる。ほんの数年前まで、たとえば1905年作の「弦楽四重奏のための緩除楽章」のような、後期ロマン派風の情緒纏綿たる音楽を書いていたウェーベルンも、いよいよこうして、彼自身の厳しい創作の道を歩み始めるのである。 リスト:ピアノ協奏曲第1番変ホ長調 ビアノはもとより、オーケストラの扱いにも習熟していたリスト(1811〜1886)が、ピアノ協奏曲を2曲しか書かなかったのは不思議思えなくもない。前衛作曲家リストにとって、バロック以来、長い伝統を受け継いできた協奏曲という器は、いかにも古臭く感じられるのだろうか。事実、リストのビアノ協奏曲は、2曲ともきわめてユニークなスタイルで書かれている。楽章間(ないしは各部分間の切れ目がなく、全曲が通して演奏されるようになっていることもそうだし、また通常のいわゆる協奏風ソナタ形式にも彼はほとんどこだわらない。さらに、各楽章楽(部分)の主題に密接な関連をもたせて、全曲に強い統一感を与えているのも、協奏曲としてはきわめて異例の手法である。形の上では、2曲はむしろ幻想曲か交響詩に近いリストには協奏曲という曲種に、ピアノとオーケストラとの競演という以上の制約を課す気持ちが、ほとんどなかったとさえ思われる。協奏曲第1番は、遡って青春時代の1830年ごろに構想が芽生えていた模様だが、作品に本腰を入れたのはリスト38歳の1849年のことで、その年の夏にひとまず完成をみた。彼がピアニストとしてヨーロッパ各地を駆けめぐるヴィルトゥオーゾ稼業から足を洗い、キエフで知り合ったザインヴィットゲンシュタイン公爵夫人カロリーネとともにワイマルで新しい生活を始めたのはちょうどその前の年である。つまりこのピアノ協奏曲は、ワイマルにおけるリストの名作時代の慕を切って落とした形となった。なお、リストはその後も1曲に改訂を加え、1852年2月17日、ワイマルで初演した、ソロはもちろんリスト自身、指揮の労をとったのはベルリオーズである。曲は続いて演奏される4つの楽章から成り、アレグロ・マエストーソの第1楽章でさっそうとスタートする。ソナタ形式に準じてはいるがきわめて自由なスタイルである。続いてクワジ・アグージョの緩徐楽章に棚当する部分があり、ひととき叙情的なムードが広がる。次のアレグレット・ヴィヴァーチェではトライアングルの活躍がめざましい。リストの音楽が大嫌いだったハンスリックが、これを皮肉って「トライアングル協奏曲」と称したのは周知の通り。終曲アレグロ・マルチアーレ・アニマートでは、欧州の素材も加えて、絢欄たるクライマックスが築かれる。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|