海流調査では、浮氷の動きから海流の流速を測定している研究があった(文献1.2.11,12)。この研究では、目視判読を行って浮氷の動きを追っていたが、観測時の状況や浮氷自身の変化によって後方散乱が変わるため、観測間隔があくと浮氷の動きを追うのが難しいとしていた。なお、浮氷の動きは海流と風に影響を受けるが、風の影響は除いていた(文献1.2.11)。SAR画像には、うねりが異なる海流や中規模の渦などが現れることがわかっており、現在行われているNOAA衛星などによる海流調査と併用できると思われる。
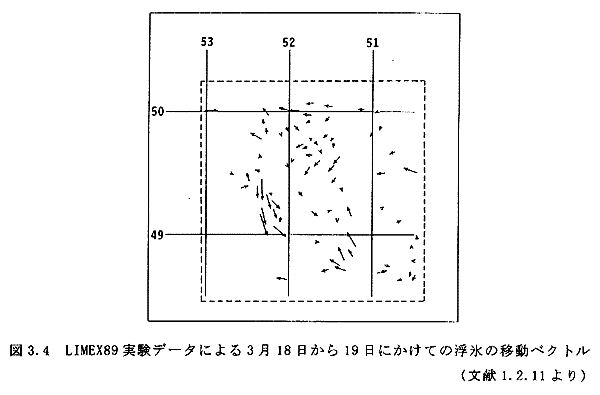
海氷調査では、氷縁部における海氷の動きを測定する研究(MIZEXなど)が行われていた(文献1.4.2〜6)。この研究では、2時期の観測データを用いているが、各データの位置合わせが困難であるとの問題点が指摘されていた(文献1.4.3)。その他、氷種を後方散乱の違いから分けており、海氷の表面が雪で覆われていても分類が可能であるとの報告も見られた(文献1.4.18)。
ヒアリングの結果から、海氷調査にはJERS−1(Lバンド)がERS−1(Cバンド)より有効であるとの知見を得た(本報告書P.13)。
実利用されているSARとしては、北海における砕氷船の効率的運用のための海氷監視システムがある(文献1.4.15,16)。また、SARなどによる流氷解析画像を、通信衛星を利用して配信するシステムが実用化に向けて研究されている(本報告書P.16)。
海氷調査を行う上での問題点は、シートゥルーステータの不足、観測範囲が狭い、SARデータの撮影頻度の増加などがあげられていた。