
|
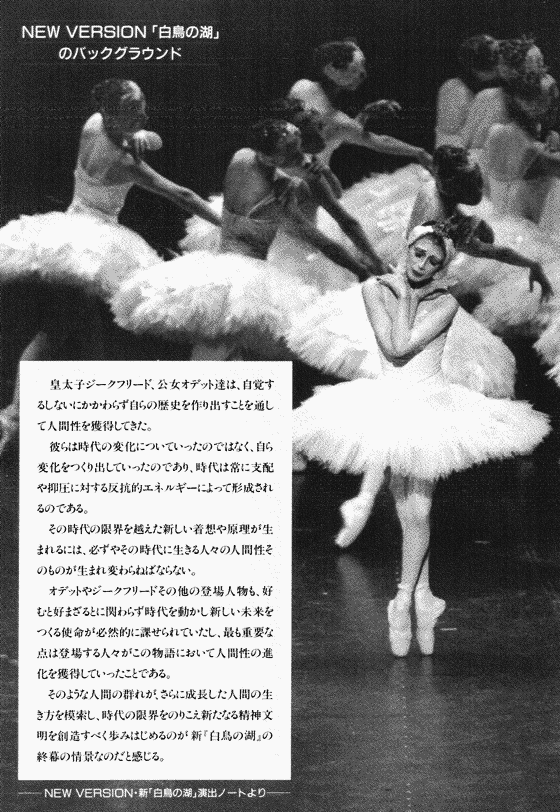
この物語の舞台は16世紀後半、群雄割拠たる未統一のドイツの中の、とある王国。女王マリアの夫でありジークフリードの父である先の国王フリードリッヒは、その自らの王国ばかりではなくドイツ全土を統べる王、神聖ローマ帝国の皇帝であった。
未統一ながら当時のドイツにも選挙王制といって「ドイツ王」という存在があった。ボヘミア公、ザクセン公、ブランデンプルク辺境伯、ライン帝領伯、この四大世俗諸侯にマインツとケルンとトリエルの大司教を加えた7人が、各地の諸侯(王、公、伯など)の中から全ドイツの王を選び出し、これに神聖ローマ皇帝の称号を与えるしきたりであった。
フリードリッヒはこの選帝侯達に高い信任を得て栄えある皇帝位について大きな業績を残したのであるが、その治世半ばにして惜しまれつつも世を去ってしまった。その愛患ジークフリードの利発さは選帝侯のみならす全ドイツの諸侯の知るところであったが、幼少ゆえに皇帝位につくには時期尚早とみなされ、その成長を待って改めて皇帝として選出するまでは皇太子としておく旨の取り決めが選帝侯達の間で成された。(因みに今回の演出では王国のモデルはプロイセンであるが、実際には16世紀後半の時期にプロイセンは皇帝を輩出するほどの大国ではなかった。)
さてフリードリッヒの死後、才媛の誉れの高かった妻マリアは王位を継いで女王を称した。これを快く思わず、ジークフリードを即座に王位につかせる事を強く主張する者もあったが、その様な輩に限って実は己が摂政の座に就いて国政を左右せんとするものであった。マリアは勇気をもって彼ら奸臣を退け、ヴォルフガング公爵をはじめとする忠実な家臣団に支えられて窮地を脱した。因みにこのヴォルフガングという人物は、その夫人と共に常に皇太子ジークフリードの側にあって教育係の役目も果した。
国政の安定した後の王国はさながら先王フリードリッヒの生前を彷彿させんばかりの幸せと豊かさとに満ち溢れるようになった。皇太子ジークフリードが成人すると、彼に皇帝たる人物に求められるすべての資資があるか否かを判ずべく、選帝侯達か宮廷に招かれた。彼らは皇太子の成長ぶりに満足し、彼が一国の領主の身分にさえなれば今直ぐにでも皇帝として選ばれるだけの資格かあることを認めた。そこでマリアは皇太后となって退き、この王国の王位を譲ることとなった(Act1:退位式)。
ジークフリードが一国の王として、同時に神聖ローマ皇帝として認められる口冠式(Act3:)が退位式とわずか
前ページ 目次へ 次ページ
|

|