
|
(二)活動しながら自分の感情を表現できるパートナーを作り相互に声をかける。
(三)被災者のいない所では同僚と努めてユーモアのある会話を心掛ける。
(四)自分で自分自身の活動を褒める。
(五)チームワークを大切にし、チームの一員としての任務に気持を集中する。
別表4 デブリーフィングの進め方(ミッチェル博士の方法)
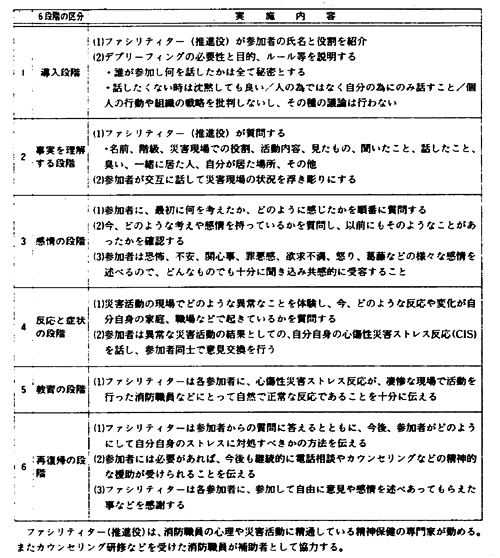
八、ストレス緩和の心理的応意手当法(デフュージング)
デフュージング(Defusing)は、CISを体験した消防職員が通常の生活パターンに戻る前の心のケアとして行われる心理的応急手当法である。
職員が現場を離れる前や災害活動終了後、八時間以内の問に行うもので、カウンセリング等の専門知識を有する者がリーダーとなり、最も深刻にCISを体験したと思われる職員を対象に、その職員のストレス反応に応じた情報や助言を与える。デフュージングでは、ある程度は仲間や上司への抵抗や批判を許容するとともに具体的なストレス軽減法等を指導し、更に強度のストレス障害を示す者をチェックし必要があれば個別のカウンセリング等を指導する。
時間は三〇分から一時間以内で、参加者が十分に発言する機会は少ないが効果的に実施されれば、以後のストレス反応を緩和し時にはデブリーフィングが不要になることがある。
九、デブリーフィング(災害体験を整理し受容するグループ・ミーティング)
デブリーフイング(CIS-debriefing)はCISからPYSDへの進行を予防するために行われる「心のケア」を目的とした報告会であり、またその一連の過程をも指す包括的な言葉である。通常、公式的なデブリーフイングは災害後二四時間から七二時間以内に、災害心理に精通した専門家の指導で行われる。
「心のケア」に軍隊等の帰還報告を意味する「デブリーフィング」の言葉が使用されているのは、精神科や心理学的なラベル(呼称)を意識的に避けて、参加者が患者等では無く正常な人々であることを強調するためである。
(一)専門家が、ファジリティター(推進役)を勤め、消防職員でカウンセリング研修を受けた者がピア・デブリーファー(仲間内
前ページ 目次へ 次ページ
|

|