
|
高関健という指揮者 渡辺和彦
カタチにこだわり、スタイルを貫く
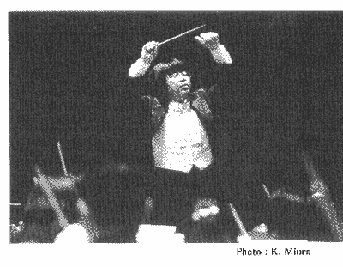
現在の日本の指揮者は、「若手」から「中堅」といわれる世代の人に才能がそろっている。ただし指揮者界というのは、80歳を越えた長老がまだまだ元気に活躍し、60歳前後のひとが長年の実績と知名度を武器に楽壇に広く睨みをきかせているというなかなか大変な世界なので、30歳代半ばから40代前半くらいまでのひとは、「中堅」ではなくてまだ「若手」と呼ばれてしまう。そうした「若手指揮者」の中には、前後の世代の指揮者よりも音楽面で明らかに一歩リードしている人が複数いる。高関健は間違いなくそうしたひとりに数えられる。
高関健は現在、新日本フィルの「指揮者」の地位にあり、1993年1月からは高崎市にある群馬交響楽団の音楽監督も兼任している。彼はかつての「カラヤン指揮者コンクール・ジャパン」(77年)の優勝者で、79年から85年まではカラヤンの助手をつとめていた。日本へ帰国後は広島交響楽団音楽監督だったこともある。
最初に書いたように、現在の日本の「若手」指揮者の中には非常に優秀な人が多い。今年秋からカールスルーエ歌劇場(ドイツ)の音楽総監督に就任し、東京フィルの常任指揮者も兼ねる大野和士、東京シティ・フィルと広島交響楽団の常任指揮者・音楽監督の十束尚宏、ついこの間までスウェーデンのノールショピング交響楽団の首席指揮者の地位にあり、現在はヨーロッパの数多くのオーケストラに客演、日本フィルの正指揮者でもある広上淳一、同じくスウェーデン・ヘルシンボリ交響楽団の首席客演指揮者で九州交響楽団常任指揮者の山下一史など。彼らは皆、1996年末の時点で、30歳代半ばから40代前半。指揮界ではまだ「若手」でも、一般社会ではもう立派な「中堅幹部」の世代である。
高関健は、いま名前をあげた若い指揮者の中でいちばん年上で(1955年生まれ)、山下一史とともに生前のカラヤンから音楽的にも人間的にも強い影響を受けた人である。文章の上では簡単に「影響を受けた」と片づけてしまいがちだが、それはほとんど全人格的な影響かもしれない。
たとえばついこの間、新日本フィルの定期公演で演奏されたR.シュトラウスの有名な交響詩〈ツァラトゥストラはかく語りき〉の演奏と指揮。その冒頭の金管のある音符ひとつを、高関健は現在の楽譜とは少し違って短く吹かせた(煩雑になるので具体例はここでは省略します)。なんでも作曲者の自作自演録音はそのようになっているとかで、晩年のR.シュトラウスと同じ時代を生きたことのあるカラヤンは、作曲者の流儀に従って金管を短く吹かせていた。
細かい話である。ひとつの音が短くなっていようが楽譜に印刷してある通り普通に長めになっていようが、そのことが全体の解釈にどう影響するというほどのことはないかもしれない。しかし高関健はそういう音楽家なのである。本人はどう思っているのかぜんぜん知らないが、指揮者=高関健はカタチをとても大切にする。細部にこだわることは、それらの必然的な積み重ねである全体のカタチの在り様(よう)にも影響する。高関健が指揮するオーケストラ作品は、始めの部分から最後の和音に至るまで、作品全体の骨格(というより基本となる背骨の部分)がとてもシッカリときこえる。決して「情に流され」たりはしない。そうすることを良しとしない。
本日清奏されるべートーヴェンは、年末の〈第9〉ということもあって、聴き手それぞれの胸に様々な思いや感想が交錯する曲だろう。しかしこの曲の楽譜には、演奏者にそのつど解釈や決断を迫る難所や論議百出箇所がゴマンとある。その部分のひとつひとつで高関健は何日も悩んだかもしれない。しかしそうした部分は一瞬のうちに通りすきてしまう。聴き手はぜんぜん気づかなかったということもある。しかしそれでもいいのである。
私から見た高関健は、それが報われるか報われないか、そういうことはこの際あまりどうでもよくて、そうすることが音楽家としての自分のスタイルと信じている、そういう頑固な芸術家に思える。 (わたなべ・かずひこ 音楽評論家)
前ページ 目次へ 次ページ
|

|