
|
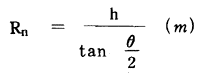
(2・4)
しかし、垂直ビームの死角といっても、その中に電波が全く行かないということではなく、ある程度弱くなるというだけのことであり、逆に死角内の物標は近いので反射電波も強くなり、その到来電波が弱くなったことと相殺されるため、一般の航海用レーダーでは、よほど空中線が高い場合以外はあまり問題とはならない。したがって一般に最小探知距離はパルス幅とTR管の回復時間とで決まり、150(m)×τ(μS)より少し長くなるのが普通である。
2・3距離分解能
自船のレーダー側から見て、同一方向の一直線上にある二つの物標が、互にどれだけ離れていれば二つの物標として分離できるかを示す限界の最小の距離を距離分解能という。図2・2において、自船のレーダー空中船から見て、同じ方向に物標A及びBがあり、空中線から電波を発射したとすれば、まず物標Aに当たり次に物標Bに当たる。このときの物標Aからの反射波と物標Bからの反射波との時間的関係は、最小探知距離における送信波と反射波との時間的関係と同じで、AとBの物標が、Aからの反射が終らないうちにBの反射がAに届くほどの近い距離にあれば、それらの反射映像はつながってしまい、二つの物
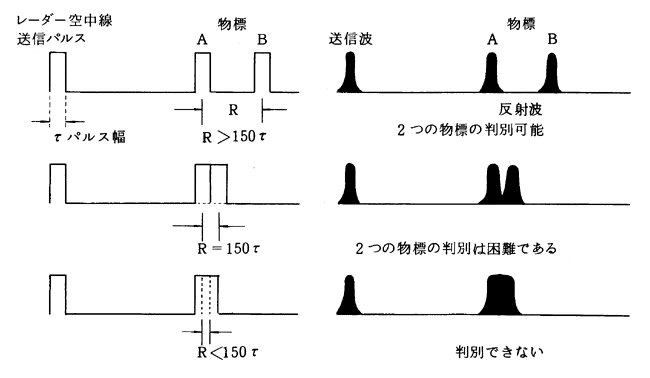
図2・2 距離分解能
前ページ 目次へ 次ページ
|

|