
|
江戸写し絵とは
江戸時代・享和3年(1803)、映像を和紙に映し、からくりで人形を動かす劇が、江戸は神楽坂の小屋にかけられた。
闇の中に色鮮やかに描かれた人形が浮かび上がり、形がぐんと大きくも小さくも自在に変化し、瞬時に消えてはまた現れるという、これまでに見たことのない新しい劇に、新し好きの江戸っ子は、キリシタン・バテレンの魔術かと熱狂した。
ルーツはオランダ渡来のエキマン鏡
エキマン鏡と呼ばれた幻灯器は、18世紀中頃には長崎へ渡来し、異国の珍しい景色を映して評判を呼んでいた。ほどなくそれは、難波、江戸へ伝えられる。
その後は日本人の得意技。ただ映すだけでは芸がないと、ガラス絵にからくり仕掛けで絵を動かし、語りと音曲をつけて劇を演じたのが、改良のミソ。
映画やアニメ誕生に先立つ、百年も前に始めたのだから立派なもの。
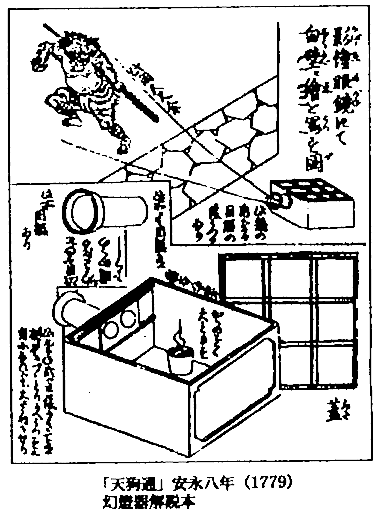
特徴
映画やアニメは、映像がフイルムに固定され、機械で動く。写し絵は、演技者が種板を動かし、糸を引いて映像を動かす。
手動によって映像を変化させる芸能は、他にはない。
映像のアップ、縮小、フェイドイン、フェイドアウトなど、現在、映画で使われる技法の多くが、「写し絵」誕生の当初から使われていた。
作品は「忠臣蔵」「番町皿屋敷」「勧進帳」「怪談 乳房榎」など、百をこす外題が分かっている。他に、枯れ木に花を咲かせ、花火を打ち上げる両国の景色など、からくりの面白さを見せる花物。民謡に振り付けた踊り、土地の伝説などを合わせて、一晩の興業を行っていた。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|