
|
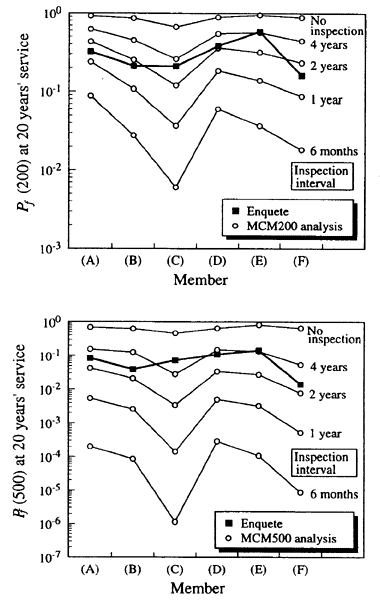
図2.3.5 20年使用後の各部位の累積破壊確率
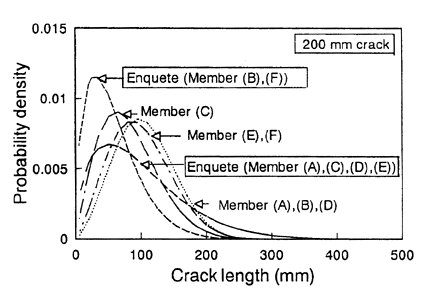
図2.3.6 検査で発見される亀裂長さの分布
のオーダであった。そこで検査間隔を調節することにより累積破壊確率の目標値を達成するには、どの程度の検査間隔 が必要かを計算した。その結果Pf(200)に対しでは検査間隔を約半年に、Pf(500)に対しては約1.5年の検査間隔にする必要があることがわかった。
検査の有効性は亀裂成長パターンにも影響を受ける。本研究では図2.3.3のパターン?を想定して解析を行ってきたが、その他についても解析を行い亀裂成長パターンの影響を調べた。その結果図2.3.3の5つの亀裂成長パターンで破壊確率は2から3倍変化し、初期に亀裂成長が緩やかなパターン?が、累積破壊確率が大きいことがわかった。
2.3.4 感度解析
アンケート結果では、6つの構造部位の疲労特性は部位(c)を除き大きな差異は見られなかった。そこで部材(c)を除く5つの部位の平均的な疲労特性を基準として感度解析を行った。また検査は間隔2年の近接目視を基準とした。感度解析は基準の疲労特性と検査能力の周辺で、部材の疲労寿命(25%、50%、75%、100%(基準)、150%、200%、400%の8通り)、検査間隔(3ケ月、6ケ月、1年、2年(基準)、4年および検査無しの6通り)、亀裂成長曲線(図2.3.3)の3つをパラメトリックに変化させて解析した。解析結果は、部材信頼度向上や部材の軽量化、検査の簡素化などの設計要求に対する解を得るという立場から検討した。表2.3.1には要求に対する対応策をまとめている。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|