
|
亀裂伝播経路や伝播速度の情報が未だ不足しているためと考えられる。このため後述の解析てば?の直線的亀裂成長を仮定して解析を行った。
また亀裂検出率に関する質問から、現状の検査によって発生した亀裂の約60%が発見され残り40%は兄落とされていること、また発生した亀裂の約3割が200mmを越え、約1割が500mmを越えて成長するという回答が得られた。
検査による亀裂検出能力:6つの部位を近接目視検査したときのPOD曲線を、腐食や塗装の影響が無い比較的良好在条件下で質問した。また図2.3.4中に示す6つの亀裂形態についても同様の質問を行った。これは同一長さの亀裂であっても、溶接止端に沿う亀裂と横断する亀裂、亀裂開口幅、亀裂検出のヒントの有無、亀裂検出を困難にする周辺部材の有無など亀裂形態によってPODが異なると考えたためである。結果を整理すると、POD曲線は図中の3グループ(Easy,Moderate,Difficult)に分類できた。検出能力が良好なのは部位(E),(C),(E),(F)や形態(1)、(2)のように、亀裂発生点となる応力集中部が一点に特定できる場合である。一方、(5)の溶接ビードに沿う亀裂や、(6)の部材裏面で発生した亀裂が反対側表面に貫通したものは検出能力が低いことがわかる。
目標信頼度:部材の目標信頼度は安全性と経済性の両面から決定される。アンケートではPf(200)やPf(500)のレベルを、どの程度にするのが望ましいかを質問した。構造部位により多少の差異は見られるが、全般的に200mmを越える亀裂個数については現状の1/8程度に、500mmを越える亀裂については現状の1/16程度にするのが望ましいという結果が得られた。
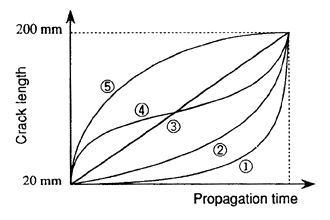
図2.3.3 準備した亀裂成長パターン
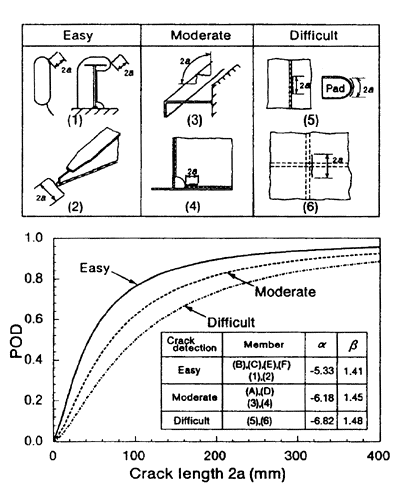
図2.3.4 近接目視検査のPOD曲線
2・3・3信頼性解析の結果
信頼性解析には取扱いが容易なマルコフ連鎖モデルを使用した。補修は完全補修モデルを仮定した。図2.3.5は20年後の破壊確率を6つの部位について一括して示す。また図中には比較のために、了ンケート調査で得られた破壊確率も黒四角印で示している。調査結果はPf(200)でみると検査間隔2年の解析結果に近く、Pf(500)では検査間隔4年の解析結果に近い。これはほぼ船体の定期検査や中間検査の間隔に対応している。また検査を全く行わなければ、発生した亀裂の約90%が200腕を越えて成長し、また60%程度が500ππを越えるが、現状行われている検査では、それらをPf(200)で約1/3、。またPf(500)で約1/5に減少させる効果があることがわかる。
図2.3.6は検査で検出される亀裂長さの分布を、アンケート調査と解析(検査間隔2年の解析)で比較している。アンケートでは部位(B)、(F)で50mm、部位(A)、(C)、(D)、(F)で100mmの亀裂が多く見つかっているが、解析結果でも80mmから100mm程度の亀裂が多く発見されるという結果が得られた。
目標信頼度の回答は粗く考えると、Pf(200)を0.01(百分の1)のオーダに、またPf(500)を0.001(千分の1)
前ページ 目次へ 次ページ
|

|