
|
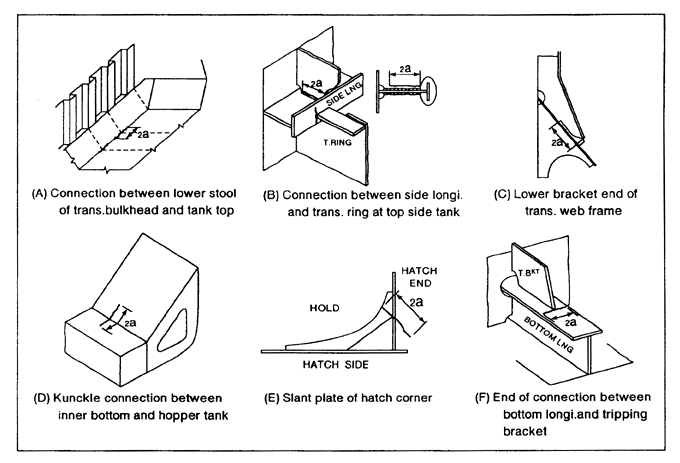
図2.3.1アンケート対象に選んだ6つの構造部位
亀裂発生時期の分布、(3)20mmから200mmまでの亀裂伝播年数と亀裂成長パターン、(4)200mmから500mまでの伝播年数と亀裂成長パターン、(5)検査で見つかる亀裂長さの平均値、最小値および最大値、(6)目視検査における亀裂検出確率、(7)200mmあるいは500?を越える亀裂個数の現状と望ましいレベル、(8)長大亀裂からの事故シナリオ、(9)亀裂形態別の亀裂検出確率、(10)検査における構造部位への接近度、の10項目である。
今回のアンケートの特徴は、(a)損傷統計の収集でなく、回答者が過去に経験した損傷事例に基づいて主観的に回答してもらった点、(b)20年間に亀裂発生を生じる部材に限定して疲労特性を調査している点、(c)日常比較的多く経験する200mmおよび500mmを限界亀裂長さに設定してこれを越える亀裂を破壊事象とし定点、(d)評価の難しい亀裂成長の様子をパターン化して準備しそれから選択してもらった点である。
上記の(b)、(c)から累積破壊確率Pf(200)、Pf(500)はそれぞれ、20年間に亀裂発生を生じる部材(亀裂発生時期は分布する)があったとして、それが使用期間中に200mmあるいは500mmを越えて成長する確率(1部材当たりの確率)、というように定義した。
2.3.2 アンケート調査結果
部材の疲労特性:アンケート結果によると、疲労亀裂は6つの部位とも部材使用開始後4,5年で多く発生していた。図2.3.2 は部材(A)について亀裂発生時期、亀裂が200mmに達する年数および500mmに達する年数の分布を一例として示す(20年間に亀裂発生を生じる部材に限定)。亀裂成長パターンについては、図2.3.3の5種類を準備しその中から選択してもらったが、回答からは亀裂進展の特徴は読み取れなかった。これは
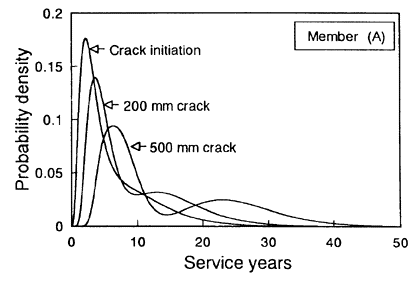
図2.3.2 構造部位(A)の疲労寿命分布の確立密度関数
前ページ 目次へ 次ページ
|

|