
|
(1) 主寸法比は、時代、船形の大小を問わずほとんど変わらない。
(2) 船体横断面の断面係数に関する規則要求値に対する実際の値は、甲板側では要求値ぎりぎりが多いが、船底側では20〜30%増しになっており、船底側は、縦強度以外の要因(二重底強度や局部強度)で構造が決定されている。
(3) 上甲板はほとんど、船底側は2/3の船で高張力鋼が使用されている。大型船(Panamax,Cape size)では10年以上前からHT化率が60%を越えている。又、4万D/W以下の小型船では30%程度であるが増加の傾向にある。
(4) 貨物倉の長さは船長に伴って長くならないので、大型船ほど船底の縦横比が小さく(幅広に)なる(図2.2.1参照)。
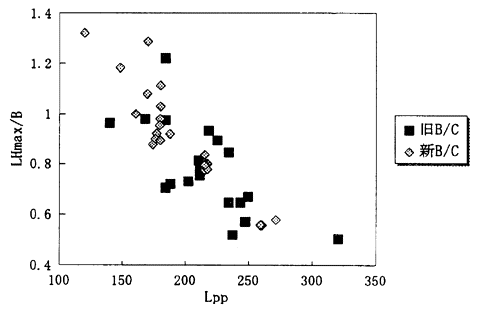
図2.2.1船の大きさと船底の縦横比との関係
(LHmax:船倉長さ B:船幅)
(5) 船形が大きくなると相対的にビルジホッパーが大きくなり、ビルジホッパーで強度を保持しようとする傾向がある。
(6) ホールドフレームブラケットの底辺の長さは、ホールドフレームの断面係数と密接な相関がある。
(7) トップサイドタンクの形状は、ハッチカバーの形式に影響され、大型船ではサイドローリング型が多いのでトップサイドタンクの幅は、船幅と相関がある。
(8) 船形が大きくなると相対的にスツールが大きくなり、スツールで強度を保持しようとする傾向がある(図2.2.2参照)。
(9) 同じ船でも水密隔壁に比べて荷重の大きい深水隔壁では、相対的にコルゲートを大きくして強度を確保する傾向にある。
(10) クロスデッキの形状は、ハッチカバーの形式にも影響されるが、大型船ではサイドローリング型が多いので倉口幅とクロスデッキ長さの比は、2程度が多い(図2.2.3参照)。
2.2.4 構造データの設計における活用法
個々のパラメータについては、前記2.2.3で調査した図表により傾向がつかめるため設計する際の指針として有効に利用できる。
これとは別に主要部構造データの一覧表を小冊子にまとめ、データの絶対値の資料としても設計する際に有効に使えるようにした。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|