
S:主桁の心距(m)
l:主桁のスパン(m)
5.3.5 船尾構造
(1)プロペラ直上外板
1955年頃、1軸当たり2000馬力級の大馬力高速機関を搭載したアルミニウム合金製高速艇が建造されるようになり、プロペラ直上外板の損傷が大きな問題となった。
それよりさき1935年頃、1軸当たり40,000馬力級の高速艦の艦尾構造に溶接が採用されたところ、リベット構造時代には問題がなかったプロペラ直上外板に損傷が発生するようになった。これは1日海軍の松本喜太郎氏の研究日によって解決したのであるが、この旧海軍の基準に材料の相違による修正を行って設計した艇に損傷が発生したのである。
それまで木製・鋼製艇で、1軸当たり1000馬力級のものは多数の建造例があったが、そのような損傷例はなかったし、プロペラのチップ・クリアランスのかなり狭いものも多かったが、そのための振動等も余り問題とはなっていなかった。
高速エンジンのバランスが良くなった今日においては、高速艇の船内最大の振動源はプロペラであり、チップクリアランスを大きくとることがその起振力を小さくする決め手であることは広く認識されている。
プロペラ付近の圧力変動については三菱長崎船型試験場(当時)の谷口中氏の研究2)があり、これによって実例を整理して設計標準を求めた。あわせて鋼船についても高速艇の例を含んで実例を解析し、標準を求めた。
プロペラ付近の圧力変動は、谷口氏によれば
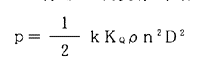
である。係数kは翼数、スリップレシオ及び翼端間隙などにより変化する。スリップレシオの影響は余り大きくないし、また、スリップレシオそのものが実船においてそれほど大きな開きがないのでこれを無視し、翼数及び翼端間隔のみの影響を考えることにする。対象として取り上げた実例は全て3翼であり、我々の取扱う船の大部分が3翼であるのでこの標準では3翼プロペラ、スリップレシオ0.25に対するkを使用することとし、図5.14に示す。
翼数が多くなるとkの値は低くなり、5翼の場合は3翼の約1/2程度になる。必要ならば原論文を参照すること。
谷口氏によれば、プロペラ中心から前後方向にはそれぞれ半径程度、左右方向にはそれぞれ直径程度離れれば、変動圧力は実質的に消滅するという。この減少の状況は翼端間隙によって異なる。図5.15,5.16に翼端間隙20%及び12%に対するものを示した。
鋼構造に対しては、実際に損傷した例を解析すると、この法則によく一致する。
ところがアルミニウム合金艇の場合には、それよりはるかに広い範囲に高い外板応力が記録された。そこで実艇の応力計測値を参考としてアルミニウム合金構造用の応力分布曲線図5.17、
前ページ 目次へ 次ページ
|

|