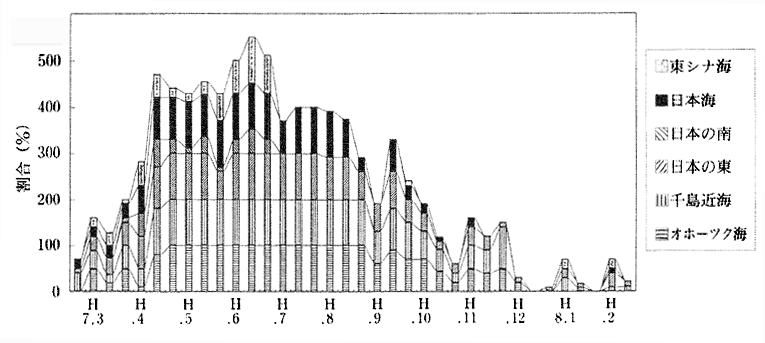
<図1>
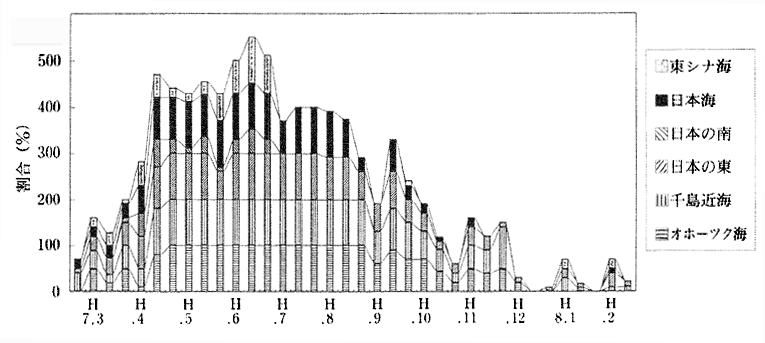
(記号:ASAS)に示されたFOGと表示されている海上濃霧警報の発表頻度を図1に示します。
この図は、日本近海を東シナ海、日本海、日本の南、日本の東、千島近海、オホーツク海の六つに分け、その海域内にFOGの対象海域が存在した回数を旬。ことに調べたものです。この発表頻度は、各旬(約十日)に対するFOG発表日の割合として算出していますので、それぞれの海域について旬すべての日にFOGが発表されていた場合は一〇〇パーセント、全く発表されていなければ〇パーセントになります。
この図から海霧の発生頻度は五〜八月、特に六月中旬から七月上旬にかけて多いことがわかります。
また海域別に見ると、オホーツク海、千島近海、日本海など北日本近海で多く、一方で、東シナ海や日本の南では発生頻度が少なくなっています。
この発生頻度が多い海域である北日本の周辺海域の海霧の発生について原因を考えると次の三つに大別されます。
①オホーツク海高気圧圏内の海霧
②「やませ」による海霧
③夏型気圧配置の時の移流霧
①は、オホーツク海高気圧の影響で湿った寒気が北日本に入り込み、この寒気に比べて比較的暖かいオホーツク海や千島近海などの海面から水蒸気の補給を受けて発生する「蒸発霧」です。
②の「やませ」とは、主に夏場に東北地方の三陸沖で東から吹き寄せる冷たく湿った局地風をいい、農業などに大きな被害をもたらす冷夏と関連があるといわれています。オホーツク海高気圧の南縁で吹く東風が親潮の影響で冷たく湿った大気となり、海霧が発生します。
③は、太平洋高気圧から吹き出す暖かく湿った空気が比較的冷たい親潮海域の海面で冷やされて発生する「移流奏」です。このように海域および気圧配置により海霧の成因が異なるため、船舶は航行する海域および周辺の気圧配置等に注意する必要があります。
四、日本の沿岸で発生する霧
日本沿岸では北海道釧路沖、鹿島業から房総付近、伊豆大島などで夏季によく海霧が発生するといわれています。また瀬戸内海においても春から夏にかけて頻繁に発生します。これらの海霧については、住民の日常生活に密接にかかわっており、その地域特有の呼称で呼ばれる場合もあります。ここでは、海霧のそのような特有な名称とその特徴について主なものを紹介したいと思います。
(1)「晴れ霧」と「雨霧」
「晴れ霧」も「雨霧」も主に瀬戸内海地方で呼ばれているものです。このうち「雨霧」は二節で述べた「前線霧」のことです。「晴れ霧」については、瀬戸内海で四月〜七月ごろにみられるもので、晴れた日の早朝に発生し、日照の増加とともに消滅していく霧のことをこのように呼んでいます。この「晴れ霧」は「放射霧」、「移流霧」