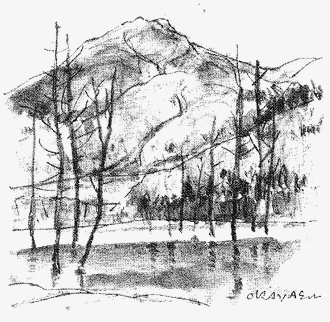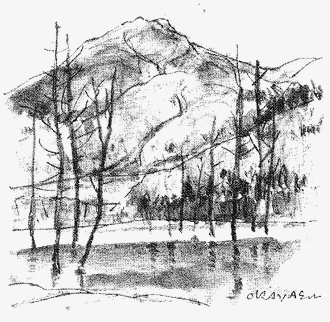い五人と、若い三人のグループが、沢を横切っている丸木橋を渡っていった。少し休んだ私たちも急坂の林の中を登ってゆく。途中、下りてくる何人かと出合う。足の早い二人の青年が私たちを追い越していった。
急坂の林を抜けると視野がひらけてくる。上の方には稜線が望まれ、下の方には上高地周辺の風景が眺められる。九時四十分頃右に岩があって少し切れこんだ所に出る。下に鉄板を敷いてあり、左側に手すりついた所を通り過ぎる。続いて少しまわりこんだ所にある松の木の下の短い鉄梯子を登る。
急な登りの道をしばらく行くと、右側に大きな岩壁のある所に出る。傾斜の角度が約七十度、高さ二十メートルほどの鉄梯子を登り切ると、周りの見晴らしの良く利く草原の斜面の道になる。ジグザグになっている登山道の両側には、紫色のリンドウ、黄色いオオマツヨイグサ、ゴゼンタチバナの赤い実などが見えてくる。
ここちよい風の吹きわたる草原状の中の道を、いくつか曲がりながら登って行くとハイマツ地帯に出る。間もなく新中尾峠にある山小屋の屋根が見えてくる。新しい噴火を生ずる前は、上高地から岐阜県の上宝村の中尾に通ずる途中の中尾峠に山小屋があったが、火山の爆発によってこわれたので、旧山小屋跡より約一軒北方の西穂高等りの新中尾峠に、長野県安長村の村営の山小屋が出来ている。
私が山小屋の前に着いた時は、五人ほどの登山者が休んでいた。安雲村村営焼岳小屋という看板があり、まわりは静かなたたずまいであった。山小屋から左へまわって少し登ってゆくと、焼岳展望台と標識のある台地に着いた。十人ほどが広場の一隅に座り込んで大きな声で話ながら屍岳を眺めていた。
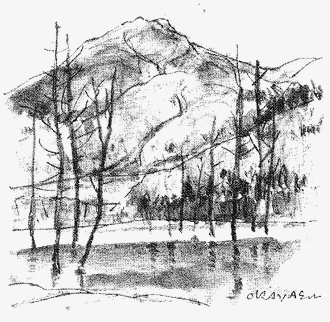
焼岳は鐘状の成層火山で、大正四年(一九一五年)以来、記録に残る火山活動は百回を越している。昭和三十七年六月十六日に山頂部をとりまくゴツゴツした円頂ドーム周辺で、噴火の爆発が起こり溶岩流が新旧かさなりあって、生々しくその姿をさらけ出している。
旧中尾峠にあった山小屋の主人、上條武さんが爆発当時に飛騨側へ這い下り、九死に一生を得たといわれている。随分おそろしい思いをしたことであろう。
焼岳展望台のまわりにはいくつかの噴火口がある。手を当ててみるとかなりの熱気がつたわってくる。また笹原の中には、イタドリ、リンドウ、ヤマハハコなどの花が咲いているのが見えた。
私たちが休憩している間に沢山の登山者が通り過ぎていった。頂上に向かう人、山麗に下りる人々である。私たちは頂上にゆくことをやめて、荒々しい焼岳の山容を展望台から充分ながめることにして、二時間半ほどの休憩時間をとった。展望台から北し方に見える錫杖岳の山なみははっきりしているが、笠ケ岳のあたりは雲がかかってよく見えない。東側の霞沢岳から三本槍、六百山にかけての山の稜線がよく見える。
焼岳のドームの南側のピークが最高部で二、四五五・四メートルを示す三角点があるという。溶岩国頂岳の頂上周辺は常に雲が動いており、刻々とその表情に変化がある。展望台から二時間余り眺めた焼岳であるが、一刻としてその構図はとどまっていない。
荒々しく見える活火山の赤茶けた肌の所々に緑衣をつけている姿には、新しく変化した山の息吹きを感じる。
前ページ 目次へ 次ページ