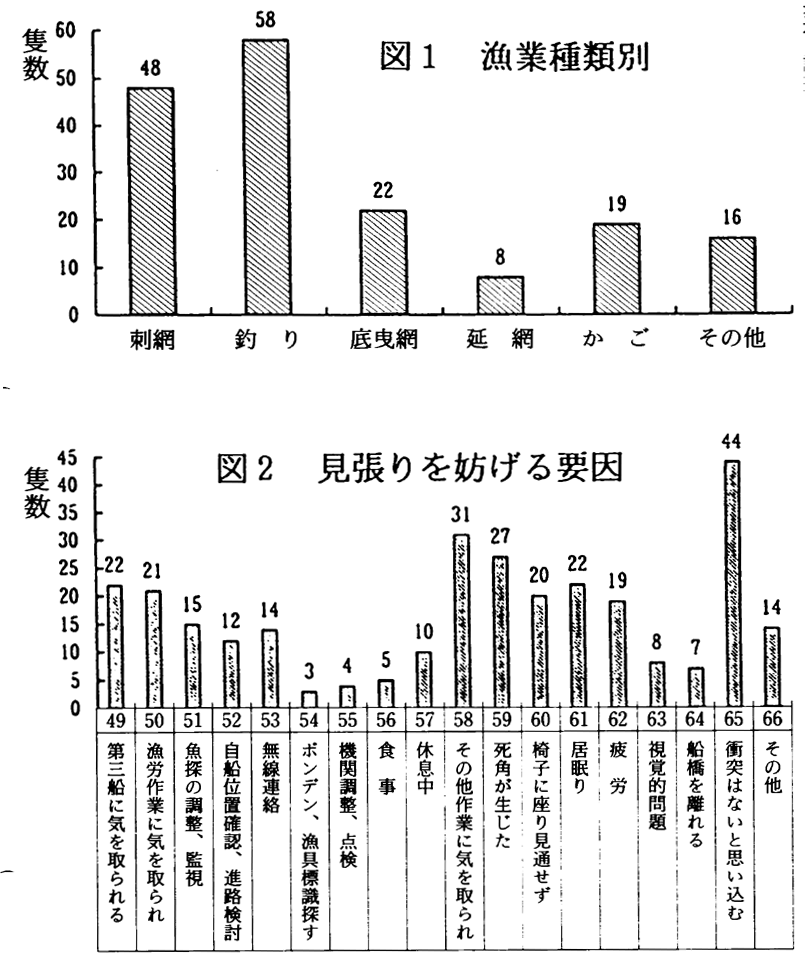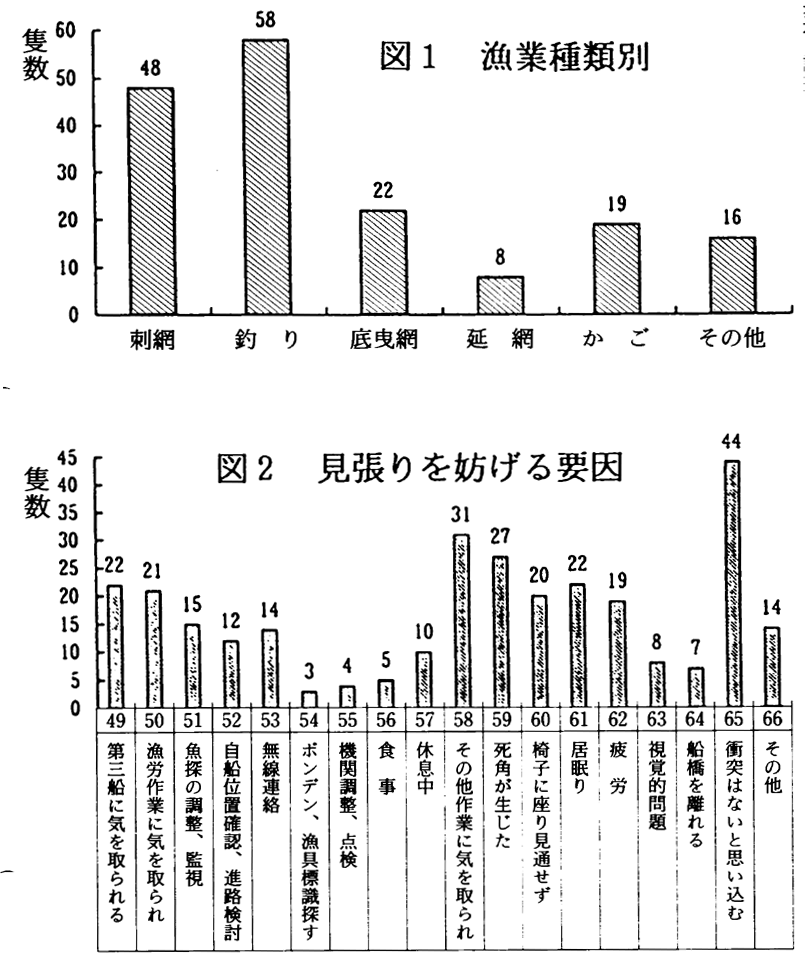操船不適切が事故の直接原因である場合を除いた一七〇隻の漁船(図1)について、事故発生の時間帯、運航状況、対象漁船に対し共通に調査できる漁労環境として事故発生月(三〜五月、六〜八月、九〜+一月、十二〜二月)、事故発生時間帯((08〜06時、06〜12時、12〜18時、18〜00時)、事故発生海域(日本海側、津軽海峡、噴火湾、その他太平洋、オホーツク海)、出港してからの経過時間(一時間未満、一〜六時間、六〜十二時間、十二〜二十四時間、二十四時間以上)、風力(〇〜一、二〜三、四〜五、六〜)、総トン数(五トン未満、五〜一〇、一〇〜二〇、二〇トン以上)、漁業種類(刺し網、釣り、底びき網、延縄、かご、その他)、運航状況(漁労作業前、漁労作業中、休息・待機中、漁場移動中、漁労作業後、出入港時)、操舵(自動、手動、その他)、白船船速(全速、半速、微速、漂泊=停止=中)、相手船船種(同種漁船、異種漁船、他船舶)の一一項目四八要因について、また裁決録の内容から把握できる見張りを妨げる要因として図2に示した49〜66の一八要因を調査した。
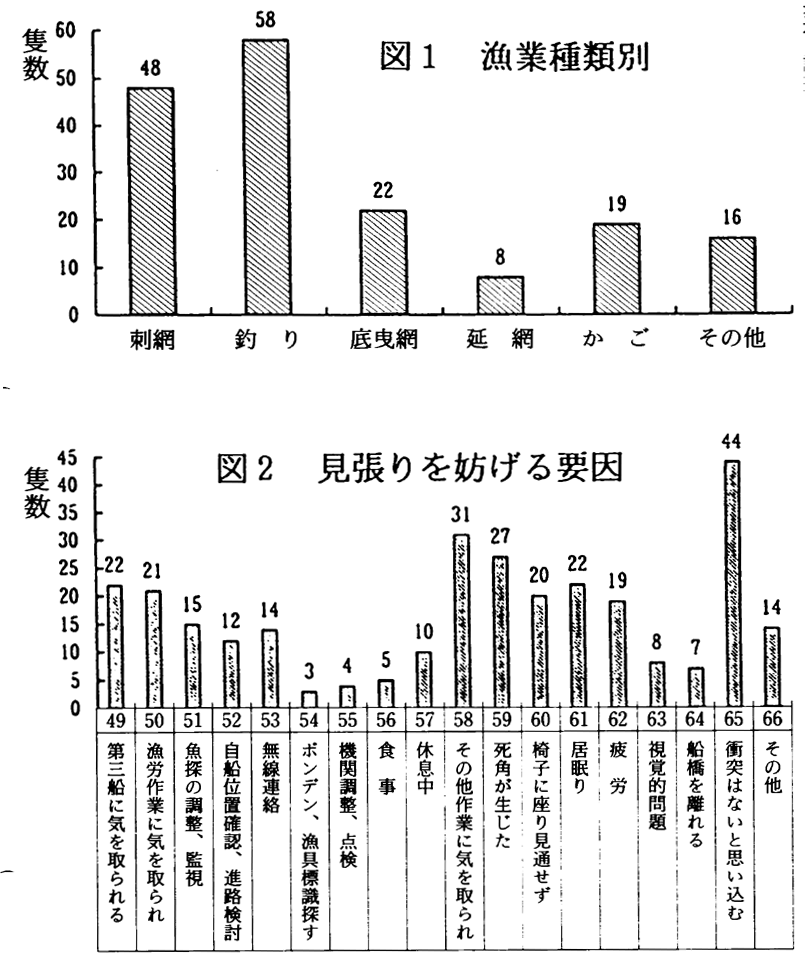
ここで62に「疲労」は、連日の操業や寝不足等による操船者の疲労状況が裁決録中に記載されている場合に該当し、64の「船橋を離れる」は航走時に船橋を離れた場合であり、65の「衝突はないと思いこむ」は相手船を事故前に一度は視認したが、操船者が衝突はないと判断し、見張りを行わなかった場合である。
図1、2に示すように、漁業種類では釣り、刺し網が多く、見張りを妨げる要因では「衝突はないと思いこむ」「その他作業に気を取
前ページ 目次へ 次ページ