
|
となる。上式を一般化し、 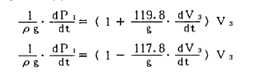
とし、dv/dtについて解きα(t,v)とすれば 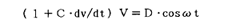
である。 上式にルンゲ・クッタ法を用い、初期値をt=t1(t1=Sin−1(h0/a)/ω)にてZ0=0、V0=0.1とし、t=t3(t3=T/2+sin−1(dc/a)/ω)までT/200ステップで繰返し計算を行い、Zmaxを求める。次にt=t3にてZが0ないし負であるか、またはZが正であっても次の波が空気室天井に当たるまでの時間(t=T+t1)に海水が自然落下する事を確認する。 海水ための高さは上のZmax以上に設定すればよい。 なお、設置場所の条件により、海水ための直径を変更して高さを再計算し、設置条件に合わせることも場合によっては必要となる。 ?パイプの取付位置、配管方法検討 空気室から発電装置までのパイプは、波が出来る限り作用しないよう水平部分は堤体に埋め、官制器室の裏側で立ち上がるようにする。下の図−6.3の様にパイプを防波堤の上の港内側に取り付ければ、通常は沖合からの波浪の作用はない。設置場所により海水が海水ため等に作用する場合は、図−6.4に示す取付板とボルト及び溶接部等の強度計算が必要になる。 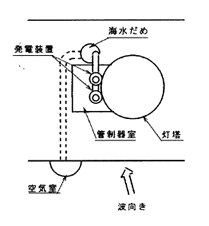
図−6.3 配管方法
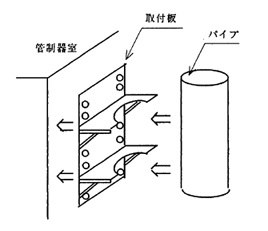
図−6.4 海水だめの取付
(2)簡易設置の場合 ?安全弁の大きさ (1)発電装置を管制器室等の上に設置する場合と同様、空気室と発電装置を結ぶ空気流路の間に安全弁を設置する。その大きさは「(1)発電装置を管制器室等の上に設置する場合?安全弁の大きさ」と同様である。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|