
|
服部名人のフィッシュ・オン
アングラーにとってはたまらないオーストラリア、ニュージーランド沖のマダイ釣り
相模湾も、紀伊水道も、今マダイが盛んに釣れている。 マダイと言えば海魚のシンボル。アングラーなら誰でも釣ってみたい憧れの魚だ。 ところで資源は有限である。マダイだって釣りまくるばかりでは、やがて資源は枯渇してしまう。そこで20年程前から神奈川など各地でマダイの稚魚放流事業が始まり、今では釣れるマダイの3分の1以上が放流魚とさえ言われている。 それでもマダイ釣りの現実は厳しい。確かに一日で5尾も釣れて大漁気分を満喫する日もあるけれど、こうした日は稀で、むしろ一日中一生懸命釣っても釣果ゼロの日が多い。 稚魚を放流していても絶対量が少ないのに攻め手は多いのだから、アングラー達は皆アノ手コノ手。釣り具に万金を投じ、高価な餌を惜し気も無く注ぎ込んで“タイ子様”のゴキゲンを伺う。 正に“娘一人に聟七人”の状態だ。 こんなマダイもアジやサバのように沢山いて、釣る人が少なければどうなるか。 当然、生存競争が激しくなるから餌の選り好みなど贅沢は言っていられないし、餌に太い糸が連なっていて「変ダナ」と気付いても空腹には勝てぬからパチリと飛び付いてしまう。 こんなアングラーとマダイの立場が日本とは全く逆の夢のような海が南半球のオーストラリアやニュージーランドにある。 俗に「ゴウシュウマダイ」と呼び、解剖学的に日本のマダイと多少の差異があり一応別種とされているが、両種は一見した所瓜二ツでアマチュアは見分け難い。 このゴウシュウマダイ、はるばる南半球から毎日のように空輸され、日本の市場でもマダイ並みに評価されている。 ゴウシュウマダイも日本のマダイ同様温帯系の魚だからオーストラリアは南部の海、ニュージーランドは北島に釣り場が集中しており、釣りのシーズンは夏、つまり日本の12月から2月へかけてが盛期だ。と、言うことは厳寒のシーズン・オフの時、ジェットでひと飛びすれば憧れのマダイがガンガン釣れる訳で日本のアングラーにとっては好都合と言う訳。 釣り方はいろいろだが最もイージーなのは「カカリのフカセ釣り」。水深5〜10メートル、岩場や藻場等が散在する浅海にアンカーでボートを据える。メタルジグを2、3回キャストすれば簡単にカウアイ(ボラとサバのハーフの様な魚)が釣れる。これを細かくカットしてパラパラと海に撒く。と、10分もしないうちに何処からともなく魚 オーストラリア・ニュージーランドのマダイ釣り場
“南緯30°〜40°の間に集中” 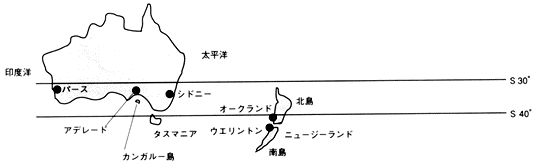
前ページ 目次へ 次ページ
|

|